 ひよこ生徒
ひよこ生徒「高校受験って、中学校の出席日数は関係ない」って本当?
中学の欠席日数が多くて、高校受験にどう影響するか不安…
出席日数が不利になる目安や、今からできる対策が知りたい!
高校受験で「出席日数は関係ない」と聞いて、安心したい気持ちがあるかもしれませんが、実際には調査書(内申書)を通じて合否に影響するケースがほとんどです。
しかし、欠席日数が多いからといって、すぐに志望校をあきらめる必要はありません。この記事では、中学校の出席日数が高校受験にどう影響するのか、不利になる目安、公立と私立の違い、そして今からできる具体的な対策まで詳しく解説します。



欠席日数が不安でも、正しい情報を知って対策を立てれば大丈夫です。
学力検査でカバーする方法や、面接での伝え方、志望校の選び方など、合格の可能性を高める方法を一緒に見ていきましょう。
- 高校受験で出席日数が「関係ない」が嘘である理由
- 不利になりやすい欠席日数の目安(年間・3年間)
- 公立高校と私立高校での出席日数の扱いの違い
- 欠席日数が多くても合格するための具体的な対策6選
- 出席日数が不安な場合の志望校の選び方
高校受験で出席日数が関係ないは嘘!ただし影響度は高校による
高校受験において、出席日数が「関係ない」は嘘ですが、影響の度合いはさまざまです。高校受験と出席日数の関係性について、まず知っておくべき点を以下の項目に分けて解説します。
ひとつずつ見ていきましょう。
高校受験の合否は学力だけで決まるわけではない
高校受験の合否は、学力検査の点数だけで決まるわけではありません。多くの高校、とくに公立高校では、学力検査の点数と「調査書(内申書)」を総合して合否を判断します。
調査書には各教科の成績だけでなく、部活動や資格、そして「出欠の記録」も記載されます。そのため、中学校の出席日数が少ない場合、内申点の評価が下がり、受験で不利になる可能性があります。
公立高校と私立高校で出席日数の扱いは異なる
高校受験において、公立高校と私立高校では出席日数の扱いが異なります。公立高校は、内申書を重視する傾向が強いため、出席日数の影響が大きくなりやすいです。
一方、私立高校は学校独自の基準で合否を判断します。推薦入試では厳しい出席基準を設けている学校が多いですが、一般入試では学力検査の結果を最優先し、出席日数をあまり問わない学校もあります。
「出席日数は関係ない」と言われる理由
高校受験で「出席日数は関係ない」と言われる理由として、入試形態によっては学力検査の結果がほぼすべてを占めるケースがあるためです。
たとえば、一部の私立高校が行う「オープン入試」や「一般入試」では、調査書は参考程度とし、当日の学力検査の点数のみで合否を決める場合があります。
ただし、これは一部のケースであり、多くの高校受験では出席日数を含む内申書が影響することを理解しておきましょう。
まずは正しい情報を知って冷静に対策しよう
お子さまの高校受験で出席日数に不安がある場合、まずは正しい情報を知って冷静に対策を講じることが不可欠です。
「欠席日数が多いから」とすぐにあきらめる必要はありません。欠席日数が多くても、その理由や中学3年生での改善状況、当日の学力検査の結果次第で合格できる可能性は十分にあります。
まずは中学校の先生や塾に相談し、志望校の募集要項を正確に把握することから始めましょう。



不安な時こそ、まずは正確な情報を集めることが大切ですよ。
中学校の欠席日数が高校受験で不利になる3つの理由
中学校の欠席日数が多いとなぜ高校受験で不利になるのか、その主な理由を3つ解説します。
詳しく解説します。
理由①調査書(内申書)に欠席日数が記載されるから
中学校の欠席日数が高校受験で不利になる1つ目の理由は、調査書(内申書)に欠席日数が記載されるからです。調査書は、中学校が作成し高校に提出する公式な書類であり、合否判定の重要な資料となります。
「出欠の記録」の欄に学年ごとの欠席日数や遅刻・早退の回数が明記されるため、高校側はこの記録を見て生徒の学校生活の様子を判断します。
欠席日数が多ければ、マイナスの印象を与える可能性は否定できません。
理由②学習意欲や生活態度を判断する材料になるから
中学校の欠席日数が高校受験で不利になる理由として、学習意欲や中学校での生活態度を判断する材料になる点も挙げられます。
高校側は、入学後に学校のルールを守り、まじめに通学してくれる生徒を求めているからです。欠席日数が多いと、以下のように懸念され、入学後の学校生活への適応を不安視されることにつながります。
- 学習意欲が低いのではないか
- 自己管理能力に課題があるのではないか
- 入学後も休みがちになるのではないか
理由③面接で欠席理由を聞かれる可能性があるから
中学校の欠席日数が高校受験で不利になる3つ目の理由は、面接で欠席理由を聞かれる可能性があるためです。調査書を見て欠席日数が多いと判断された場合、面接試験でその理由を質問されることがあります。
その際、病気やけがなどのやむを得ない理由を説明できれば問題ないケースも多いです。しかし、明確な理由を答えられなかったり、前向きな意欲を示せなかったりすると、評価に影響する可能性も否定できません。



面接で聞かれたらどう答えれば良いか不安です…。



大丈夫ですよ。前向きな意欲と改善点を伝えられればOKです。
【危険信号は何日?】高校受験で不利になりやすい欠席日数の目安
「欠席日数が何日以上だと危険なの?」と不安に思う人に向けて、ここでは高校受験で不利になりやすい欠席日数の目安を解説します。
ひとつずつ解説します。
目安は年間30日・3年間で合計90日以上
高校受験で不利になりやすい欠席日数の目安は、年間30日、3年間で合計90日以上と言われることが多いです。これは、全日制の公立高校における一般的な目安とされています。
年間の欠席が30日(おおむね月3日程度)を超えると、高校側に「不登校傾向」と判断され、合否判定で不利になるリスクが高まります。
3年間の合計で90日を超える場合も同様に注意が必要です。
「審議の対象」になると合格が難しくなる場合も
高校受験では、中学校の欠席日数が一定基準を超えると「審議の対象」になる場合があります。「審議の対象」とは、学力検査や内申点が合格ラインに達していても、欠席日数の多さなどを理由に、合否を慎重に検討される状態のことです。
場合によっては、定員割れしていても不合格になる可能性があります。この基準は高校ごとに設定されており、公表されていないことも多いです。
あくまで目安であり高校や都道府県によって基準は異なる
高校受験で不利になりやすい欠席日数はあくまで目安であり、高校や都道府県によって基準は異なります。たとえば、進学校や人気の高い高校では、年間10日程度の欠席でも評価に影響する場合があります。
一方で、欠席日数が30日を超えていても、その理由(病気やけがなど)を考慮してくれる高校もあります。必ず志望校の募集要項を確認したり、中学校の先生に相談したりしましょう。



志望校の基準はどうなっているか、早めに確認しましょう。
欠席日数だけでなく遅刻・早退の回数も影響する場合がある
高校受験では、欠席日数だけでなく遅刻・早退の回数も影響する場合があります。遅刻や早退も調査書に記載されるため、回数が多いと生活リズムの乱れや学習意欲の低さを懸念される可能性があります。
自治体や学校によっては、「遅刻・早退を3回で欠席1日扱い」のように換算するルールを設けている場合もあるため、欠席と同様に注意が必要です。
高校受験では中学何年生からの出席日数が重視される?
高校受験の調査書には、中学1年生から3年生までの出席日数が記載されます。とくに何年生の記録が重視されるのか、ポイントを解説します。
- 基本は中学3年間の合計日数が見られる
- 特に中学3年生の欠席状況が重要視される傾向
- 中学1・2年で休みが多くても3年生で改善すれば評価されることも
- いつまでの欠席が影響する?一般的には3年生の12月頃まで
順にみていきましょう。
基本は中学3年間の合計日数が見られる
高校受験で重視される出席日数は、基本は中学3年間の合計日数が見られます。調査書には1年生から3年生(の途中まで)の出欠状況がすべて記載されるため、特定の学年だけが良ければいいわけではありません。
とくに公立高校では、3年間の記録が内申点の一部として評価対象となることが一般的です。3年間を通して、安定して通学できていることが理想とされます。
特に中学3年生の欠席状況が重要視される傾向
高校受験で見られる出席日数として、特に中学3年生の欠席状況が重要視される傾向にあります。中学3年生の状況は、受験直前の学習意欲や生活態度を最も反映すると見なされるためです。
高校側も「直近の状況」を最も気にしており、「入学後も問題なく通学できるか」を判断する材料にします。1・2年生で欠席が少なくても、3年生で急に増えると懸念材料となり得ます。
中学1・2年で休みが多くても3年生で改善すれば評価されることも
高校受験では、中学1・2年で休みが多くても3年生で改善すれば評価されることもあります。過去に不登校などで欠席が多くても、3年生になってから欠席日数が大幅に減ったり、皆勤になったりした場合、学習意欲の回復や精神的な成長が認められることがあるからです。
面接などで、欠席していた時期の反省と、3年生で努力した点を前向きにアピールできるといいでしょう。



3年生での頑張りは、しっかり評価してもらえることが多いです。
いつまでの欠席が影響する?一般的には3年生の12月頃まで
高校受験の出席日数として影響するのは、一般的に中学3年生の12月頃(2学期末)までです。これは、高校に提出する調査書を作成する時期が関係しています。
年明けの1月以降の欠席は、調査書に反映されないケースが多いです。ただし、私立高校の推薦入試などは出願時期が早いため、11月末時点の記録で判断される場合もあります。
正確な時期は中学校の先生に確認しましょう。
【病気や不登校】高校受験で考慮される欠席・されにくい欠席
同じ欠席でも、その理由によって高校側の受け止め方は異なります。ここでは、高校受験で考慮されやすい欠席と、不利になりやすい欠席について解説します。
詳しく解説します。
考慮されやすい欠席理由|感染症・病気・怪我・忌引など
高校受験で考慮されやすい欠席理由の1つ目は、やむを得ない事情です。たとえば、以下のようなケースが該当します。
- インフルエンザなどの出席停止扱いになる感染症
- 入院や手術、通院が必要な病気や怪我
- 近親者の不幸(忌引)
これらは本人の責任ではないため、欠席日数が多くても不利になりにくいと言えます。ただし、事情は中学校に正しく伝えておく必要があります。
不利になりやすい欠席理由|明確な理由のない欠席・怠惰
高校受験で不利になりやすい欠席理由として、明確な理由のない欠席や怠惰とみなされる休みが挙げられます。具体的には、「なんとなく行きたくない」「寝坊した」といった理由での欠席が多いと、学習意欲や自己管理能力が低いと判断されかねません。
高校側は、継続して学習に取り組む姿勢を重視します。そのため、理由の不明確な欠席はマイナス評価につながりやすいです。
不登校の場合の扱いは高校によって異なる
高校受験において、不登校の場合の扱いは高校によって異なります。いじめや人間関係のトラブル、起立性調節障害など、本人の意思だけでは解決が難しい事情を配慮してくれる高校もあります。
一方で、理由が何であれ、欠席日数として一律に評価する高校も存在します。不登校経験者の受け入れ実績が豊富な高校や、別室登校(保健室登校など)を出席として認めてくれる高校を選ぶことも重要です。
欠席理由を証明する診断書などの重要性
高校受験でやむを得ない欠席を考慮してもらうには、理由を証明する診断書などの客観的な書類が重要になる場合があります。
病気や怪我、起立性調節障害などで長期欠席した場合は、医師の診断書を中学校に提出しておきましょう。診断書があることで、中学校側も調査書の備考欄に「病気療養のため」といった事情を記載しやすくなります。
診断書をもらうことにより、高校側に正当な理由として伝わりやすくなるでしょう。



やむを得ない事情は、診断書などで客観的に伝わるようにしましょう。
【公立・私立別】高校受験への出席日数の影響度の違い
高校受験では、公立高校と私立高校で、出席日数の影響度が異なります。志望校選びにも関わるため、それぞれの特徴を理解しておきましょう。
ひとつずつ見ていきましょう。
公立高校は内申書を重視するため影響が大きい傾向
高校受験への出席日数の影響度として、公立高校は内申書(調査書)を重視するため影響が大きい傾向にあります。多くの公立高校では「学力検査:内申点」の比率(例:6:4、5:5など)が明確に定められています。
内申点の一部である出欠状況が悪いと、学力検査で高得点を取っても、総合点で挽回するのが難しくなる場合があります。
まじめな学校生活が評価される傾向が強いです。
私立高校は学校独自の基準で判断するため様々
高校受験への出席日数の影響度として、私立高校は学校独自の基準で判断するため様々です。とくに推薦入試では、内申点の基準とあわせて「欠席日数は年間10日以内」など、公立高校以上に厳しい基準を設けている学校も少なくありません。
一方で、一般入試では出席日数をあまり重視しない学校もあり、方針は学校によって大きく異なります。
私立高校の一般入試は学力重視で影響が少ないことも
高校受験への出席日数の影響度について、私立高校の一般入試では学力重視で影響が少ないこともあります。「オープン入試」と呼ばれる、当日の学力検査の結果のみで合否を決めるタイプの入試では、調査書は参考程度で、出席日数が合否にほぼ関係ないケースもあります。
欠席日数に不安がある場合は、このような学力重視の私立高校を狙うのもひとつの戦略です。



欠席が多くても、テストの点数が良ければ大丈夫な場合もあるんですね!



そうです。学力検査重視の学校も選択肢になりますよ。
通信制高校や定時制高校は出席日数に寛容な場合が多い
高校受験への出席日数の影響度として、通信制高校や定時制高校は中学時代の出席日数に寛容な場合が多いです。これらの学校は、不登校経験者やさまざまな事情を抱える生徒を積極的に受け入れているため、中学時代の出欠状況を選考で重視しないことがほとんどです。
選考方法も、面接や作文が中心で、学力検査や調査書の比重が低い、あるいは無い場合もあります。
欠席日数が多くても高校受験で合格するための具体的な対策6選
欠席日数が多い場合でも、高校受験をあきらめる必要はありません。今からできる具体的な対策を実行することで、高校受験で合格を勝ち取る可能性は高められます。
- まずは学校の先生に相談して事情を正直に伝える
- 保健室登校やフリースクールを活用して出席扱いにする
- 定期テストは必ず受けて学力をアピールする
- 提出物をきちんと出して学習意欲を示す
- 学力検査で高得点を取って内申点をカバーする
- 面接で欠席理由と今後の意欲を前向きに伝える
詳しく解説します。
対策①まずは学校の先生に相談して事情を正直に伝える
欠席日数が多くても高校受験で合格するための対策の1つ目は、まず学校の先生(担任や進路指導担当)に相談して事情を正直に伝えることです。
なぜ休んでいるのか(体調面、友人関係、学習面の不安など)を保護者から共有することで、学校側も配慮しやすくなります。
調査書の備考欄に事情を記載してもらえたり、後述する出席扱いの方法を提案してもらえたりする可能性があります。抱え込まずに早めに相談することが、次の一歩につながるでしょう。
対策②保健室登校やフリースクールを活用して出席扱いにする
欠席日数が多くても高校受験で合格するための対策として、保健室登校やフリースクールを活用して出席扱いにできるか相談する点も挙げられます。
学校(校長)が認めれば、教室に行けなくても保健室や相談室、適応指導教室での学習を「出席」としてカウントできる制度があります。
また、学校が連携するフリースクールへの通所を出席扱いにする場合もあります。出席日数の不安を少しでも減らす方法を学校と探しましょう。
対策③定期テストは必ず受けて学力をアピールする
欠席日数が多くても高校受験で合格するためには、定期テストはできるだけ受けて学力をアピールすることも対策になります。
授業に出席できていなくても、定期テストで一定の点数を取ることで「基礎学力はある」と評価され、内申点(評定)の極端な低下を防げる可能性があります。
また、テストを受ける姿勢自体が、学習意欲の証明にもつながります。体調が許す限り、テストだけでも受験できないか検討しましょう。
対策④提出物をきちんと出して学習意欲を示す
欠席日数が多くても高校受験で合格するための対策4つ目は、提出物をきちんと出して学習意欲を示す点です。内申点の評価には、テストの点数だけでなく「関心・意欲・態度」も含まれます。
授業に出られなくても、自宅で課題やワークに取り組み、期限内に提出することで、学習意欲があると評価してもらえます。
先生に課題を受け取りに行くなど、前向きな姿勢を見せることも有効です。



提出物など、できることで学習意欲を示すことが大切です。
対策⑤学力検査で高得点を取って内申点をカバーする
欠席日数が多くても高校受験で合格するための対策として、学力検査(入試本番のテスト)で高得点を取って内申点をカバーする方法があります。
この対策を採るには、内申点の比重が低い高校や、学力検査重視の高校を志望校に選ぶことが前提となります。欠席による内申点の不利を、当日のテストの点数で覆せるだけの高い学力を身につける必要があります。
学習の遅れを取り戻すため、塾や家庭教師の活用も有効です。
対策⑥面接で欠席理由と今後の意欲を前向きに伝える
欠席日数が多くても高校受験で合格するための対策6つ目は、面接で欠席理由と今後の意欲を前向きに伝えることです。
欠席理由を聞かれた際は、正直に伝えつつも、他人のせいにしたり、言い訳に終始したりするのは避けましょう。以下の点を具体的に話すことが重要です。
- 欠席した理由(例:体調管理がうまくできなかった)
- 改善のために努力したこと(例:中学3年になってからは改善に努めた)
- 高校入学後の前向きな意欲(例:高校では3年間休まず通学したい)
出席日数が不安な中学生の志望校の選び方
中学時代の出席日数に不安がある場合、志望校選びにも工夫が必要です。不利な条件をカバーできるような高校の選び方について、5つのポイントを紹介します。
- 内申書より学力検査の比重が高い高校を選ぶ
- 「審議の対象」の基準が緩やかな高校を探す
- 不登校経験者の受け入れに積極的な高校を調べる
- 私立高校の一般入試やオープン入試を狙う
- オープンスクールや説明会に積極的に参加する
ひとつずつ見ていきましょう。
選び方①内申書より学力検査の比重が高い高校を選ぶ
出席日数が不安な中学生の志望校の選び方として、まず内申書より学力検査の比重が高い高校を選ぶことが挙げられます。
公立高校でも、自治体や学校によって「学力検査:内申点」の比率は異なります(例:7:3、6:4など)。学力検査重視の高校であれば、入試本番の得点で内申点の不利をカバーしやすくなります。
私立高校の一般入試も、この傾向が強いです。
選び方②「審議の対象」の基準が緩やかな高校を探す
出席日数が不安な中学生の志望校の選び方のポイントとして「審議の対象」となる欠席日数の基準が緩やかな高校を探すことも挙げられます。
欠席日数が多い生徒を合否判定の「審議」に回す基準は、高校によって異なります。この基準が緩やかな高校であれば、欠席日数が多くても即不合格とはなりにくいです。
基準は公表されていないため、中学校の先生や塾に、過去の進路指導の経験からアドバイスをもらうといいでしょう。
選び方③不登校経験者の受け入れに積極的な高校を調べる
出席日数が不安な中学生の志望校の選び方では、不登校経験者の受け入れに積極的な高校を調べることも重要です。具体的には、以下のような特徴を持つ学校が挙げられます。
- 不登校の生徒専用の入試枠(不登校枠)を設けている
- 調査書の内容よりも面接や作文で意欲を評価する方針である
- 入学後のサポート体制が整っている
こうした学校は、お子さまが再スタートしやすい環境と言えるでしょう。
選び方④私立高校の一般入試やオープン入試を狙う
出席日数が不安な中学生の志望校の選び方として、私立高校の一般入試やオープン入試を狙う方法もあります。一般入試やオープン入試は、当日の学力検査の結果を最優先することが多いです。
調査書(内申書)は参考程度で、出席日数が合否に直結しにくいケースも少なくありません。入試本番の点数で実力を示せるお子さまには有効な選択肢です。
選び方⑤オープンスクールや説明会に積極的に参加する
出席日数が不安な中学生の志望校の選び方として、オープンスクールや説明会に積極的に参加することも挙げられます。
実際に足を運ぶことで、以下のようなメリットがあります。
- 学校の雰囲気やサポート体制を直接確認できる
- お子さま自身が「ここなら通えそう」と感じられるかどうかがわかる
- 説明会後の個別相談会で、出席日数に関する高校側の方針を具体的に質問できる
不安な点は、勇気を出して直接確認してみましょう。



不安な点は、説明会などの個別相談で直接聞くのが一番です。
全日制だけじゃない!出席日数に不安があっても進学できる高校の種類
中学校の出席日数に不安がある場合、全日制高校だけが進学先ではありません。中学時代の出席状況に寛容で、自分のペースで学べる高校の種類を紹介します。
ひとつずつ解説します。
通信制高校|自分のペースで学習できる
中学校の出席日数に不安があっても進学できる高校の種類として、通信制高校が挙げられます。通信制高校は、自宅でのレポート作成(添削指導)を中心に学習を進める学校です。
毎日通学する必要がなく、年に数回のスクーリング(対面授業)で単位を取得するのが基本となります。中学時代の出席日数を問われないことがほとんどで、自分の体調やペースにあわせて学習できるのが最大の魅力です。



毎日通わなくても高校に行けるんですね。



はい。通信制高校など、自分に合った学び方も探せますよ。
定時制高校|働きながらでも通える
出席日数に不安があっても進学できる高校の種類には、定時制高校もあります。定時制高校は、夜間や昼過ぎなど、全日制とは異なる時間帯に授業を行う学校です。
1日の授業時間が4時間程度と短く、働きながら通う生徒も多く在籍しています。中学時代の出席日数に寛容な学校が多く、選考も面接や作文が中心の場合があるため、学力に不安があるお子さまでも挑戦しやすい選択肢です。
サポート校|学習面・精神面の支援が手厚い
出席日数に不安があっても進学できる高校の種類として、サポート校も知っておくといいでしょう。サポート校は、通信制高校の卒業を支援するための民間の教育機関です(サポート校単体では高校卒業資格は得られません)。
サポート校では、以下のような手厚い支援が受けられます。
- 通信制高校のレポート作成支援
- 学習の遅れのフォロー
- メンタルケア
- 生活リズムの相談
不登校経験者への支援実績が豊富な場合も多く、安心して学習を再開したいお子さまに向いています。
出席日数が不安なお子様の高校受験のために保護者ができる3つのサポート
中学生のお子さまの出席日数が不安なときに、高校受験のために保護者ができる主なサポートを3つ紹介します。
ひとつずつ見ていきましょう。
サポート①正確な情報を集めて冷静に進路を検討する
出席日数が不安なお子様の高校受験のために保護者ができるサポートの1つ目は、正確な情報を集めて冷静に進路を検討することです。
「欠席が多いから」と感情的になったり、あきらめたりするのではなく、まずは冷静になることが求められます。中学校の先生や塾と連携し、志望校の募集要項や過去の入試データ(欠席日数の扱いなど)を集めましょう。
正確な情報に基づいて、お子さまの現状でも目指せる高校の選択肢を親子で冷静に話し合うことが重要です。
サポート②子供を責めずに心に寄り添い一番の味方でいる
出席日数が不安なお子様の高校受験のために保護者ができるサポートとして、子供を責めずに心に寄り添い一番の味方でいる点も挙げられます。
欠席日数が多いことで、お子さま本人が一番不安や焦りを感じている可能性があります。「どうして学校に行けないの」と責めるのではなく「あなたの味方だよ」というメッセージを伝え、安心できる家庭環境を作ることが不可欠です。
精神的な安定が、学習意欲や次の行動へのエネルギーにつながります。
サポート③学習の遅れを取り戻す環境を整える【塾や家庭教師の活用】
出席日数が不安なお子様の高校受験のために保護者ができるサポートの3つ目は、学習の遅れを取り戻す環境を整えることです。
欠席日数が多いと、授業が受けられず学習の遅れが生じがちです。学力検査で高得点を取って内申点の不利をカバーするためにも、学習の遅れを取り戻す必要があります。
お子さまのペースにあわせて指導してくれる個別指導塾や、自宅で学べる家庭教師(オンライン家庭教師)の活用も有効な選択肢です。
お子さまに合った学習環境を整えてあげましょう。



欠席中の学習の遅れは、塾や家庭教師で効率的に取り戻せます。
【出席日数で高校受験が不安なら】不登校支援にも強いおすすめ塾・家庭教師
高校受験の出席日数に不安があり、学習の遅れを取り戻したい場合、不登校支援に強い塾や家庭教師の活用がおすすめです。お子さまの状況に合ったサポートを紹介します。
ひとつずつ見ていきましょう。
出席日数が不安な中学生におすすめの塾
高校受験の出席日数に不安がある中学生におすすめの塾として、3つのサービスを紹介します。自宅で学べるオンライン塾や、不登校支援専門の塾があります。
順に見ていきましょう。
すらら


出典:surala.jp
| 対象年齢 | 小学生・中学生・高校生 |
|---|---|
| 授業形態 | オンライン教材(eラーニング)と「すららコーチ」による学習サポートを組み合わせた形式 |
| 入会金 | 11,000円 ※キャンペーンにより変動する場合あり |
| 料金 | 小学生:8,800円~/月 中学生:8,800円~/月 高校生:8,800円~/月 |
| 無料体験 | ◯ |
| 講師 | 「すららコーチ」と呼ばれる、現役の塾講師が学習をサポート。 |
| 特徴 | ・学年に縛られず、さかのぼり学習や先取り学習が自由自在な「無学年式」 ・キャラクターとの対話形式で進むレクチャーで、飽きずに学習を継続できる ・AI搭載ドリルが、つまずきの原因を自動で特定し、一人ひとりに合った問題を出題 ・不登校生の出席扱い制度にも対応 |
高校受験の出席日数に不安がある中学生におすすめの塾1つ目は、すららです。すららは、AIを活用した無学年式のオンライン教材で、お子さまの学力に合わせて小学校の範囲からさかのぼって学習の遅れを取り戻せるのが特徴です。
現役塾講師である「すららコーチ」が学習計画から進捗管理までサポートし、不登校のお子さまの出席扱いを実現した実績もあります。
自宅で自分のペースで学習を進めながら、高校受験の基礎学力をしっかり固めたい人におすすめです。
\ 資料請求・無料体験はこちら /
東大毎日塾


出典:toudain.com
| 対象年齢 | 中学生・高校生 |
|---|---|
| 授業形態 | 個別指導(学習管理型コーチング塾) |
| 入会金 | 4万円(全額キャッシュバックキャンペーン実施中) |
| 料金 | サポートプラン:43,780円/月 スタンダードプラン:65,780円/月 合格プレミアムプラン:87,780円/月 |
| 無料体験 | ◯ ※14日間体験指導、無料個別相談会あり |
| 講師 | 東大、京大等の最難関大生 |
| 特徴 | ・3年連続東大合格 ・志望校合格率90.3% ・あなた専用の学習計画を提案 ・毎日の徹底した学習管理で着実にプランを実行 ・24時間質問し放題の仕組みで疑問を徹底解決 |
高校受験の出席日数に不安がある中学生におすすめの塾2つ目は、東大毎日塾です。東大毎日塾は、現役東大生コーチによるLINEでの学習管理とオンライン個別指導が特徴です。
365日いつでもLINEで質問ができるため、自宅学習でわからないことがあっても安心です。学習の遅れを取り戻すだけでなく、効率的な勉強法や学習習慣の確立までサポートしてもらえます。
学校に通えていなくても、自宅で質の高い指導を受け、学力検査での高得点を目指したい人におすすめです。
\ LINEで無料相談会申し込みはこちら /
キズキ共育塾


出典:kizuki.or.jp
| 対象年齢 | 小学生〜社会人 ※不登校、ひきこもり、発達障害、中退、通信制高校などで学習にブランクがある人 |
|---|---|
| 授業形態 | 1対1の完全個別指導(対面・オンライン) |
| 入会金 | 入会金:16,500円、事務手数料:5,500円、選抜費:11,000円〜(コースによって変動) |
| 料金 | 「1回80〜110分の授業を、月4回受講」して月額28,000円から |
| 無料体験 | ◯ |
| 講師 | 登校・中退・ひきこもりなど、様々な困難を乗り越えた経験を持つ講師が多数在籍。 |
| 特徴 | ・不登校・中退・ひきこもりなど、挫折経験のある方を専門にサポート ・一人ひとりの状況に合わせた完全オーダーメイドの学習計画 ・授業を何度でもやり直せる「授業の再設定」が可能 ・進路相談や生活面のサポートも行う「総合支援」 |
高校受験の出席日数に不安がある中学生におすすめの塾3つ目は、キズキ共育塾です。キズキ共育塾は、不登校や中退を経験した人のための個別指導塾で、オンラインと通塾に対応しています。
生徒一人ひとりの事情や学習状況に寄り添い、ゼロからの学び直しを徹底的にサポートしてくれるのが特徴です。学習支援だけでなく、メンタル面のケアや進路相談にも強みを持っています。
欠席期間が長く、学習の遅れだけでなく精神的な不安も抱えているお子さまに、特におすすめの塾です。
\ 無料見学・面談申し込みはこちら /
出席日数が不安な中学生におすすめの家庭教師
高校受験の出席日数に不安がある中学生には、家庭教師もおすすめです。1対1で、お子さまのペースにあわせて学習の遅れをサポートしてくれるサービスを順に紹介します。
オンライン家庭教師マナリンク


出典:manalink.jp
| 対象年齢 | 小学生 〜 高校生・浪人生・社会人 |
|---|---|
| 授業形態 | 完全オンラインのマンツーマン個別指導(Zoom/専用アプリ) |
| 入会金 | 19,800 円 |
| 料金 | 小学生:15,000〜18,000円/月 中学生:16,000〜20,000円/月 高校生:18,000〜25,000円/月 |
| 無料体験 | ◯ |
| 講師 | 塾経営者・プロ家庭教師・教員免許保持者など社会人プロ講師が中心 |
| 特徴 | ・入会金19,800円+授業料のみで教材費・管理費・解約金なしのシンプル料金体系 ・社会人プロ講師を事前動画で指名でき、相性が合わなければ交代無料 ・完全オンライン&最短当日スタート、45〜60分の無料体験からすぐに本授業へ移行可能 ・科目・学年・目的別に細分化されたコース(発達障害・海外子女・公務員試験など)でニーズに合わせやすい |
高校受験の出席日数に不安がある中学生におすすめの家庭教師1つ目は、オンライン家庭教師マナリンクです。マナリンクは、指導経験豊富なプロの家庭教師から、お子さまに合った先生を指名できるサービスです。
不登校支援の経験が豊富な先生も多数在籍しており、学習面だけでなく精神面もサポートしてくれます。授業は録画可能で、テスト前に何度も見返して復習できるのも魅力です。
自宅で安心して、経験豊富なプロの指導を受けさせたい人におすすめです。
\ 無料体験はこちら /
家庭教師のサクシード


出典:benkyo.co.jp
| 対象年齢 | 小学生、中学生、高校生 |
|---|---|
| 授業形態 | 対面指導:関東・関西・中部など主要都市圏で家庭教師が訪問 オンライン指導:全国どこからでも受講可能 |
| 入会金 | 0 円(無料) |
| 料金 | 小学生 3,080 円〜/時 中学生 3,630 円〜/時 高校生 4,290 円〜/時 |
| 無料体験 | ◯ |
| 講師 | 現役大学生・大学院生/社会人/プロ家庭教師 |
| 特徴 | ・入会金・教材費0円、体験授業も無料 ・学年が上がっても料金据え置き&複数教科OK ・対面とオンラインを自由に選択 ・16万人超の講師から最適マッチング |
高校受験の出席日数に不安がある中学生におすすめの家庭教師2つ目は、家庭教師のサクシードです。サクシードは、訪問型とオンライン型を選べる家庭教師サービスで「不登校サポートコース」が用意されているのが特徴です。
学習の遅れを取り戻すだけでなく、メンタルケアや生活リズムの改善まで幅広くサポートしてくれます。高校受験の進路相談にも強く、お子さまの状況に合った志望校選びも手伝ってもらえます。
勉強と生活の両面から手厚いサポートを受け、高校受験を乗り越えたい人におすすめです。
\ 無料体験はこちら /
ティントル


| 対象年齢 | 小学生・中学生・高校生 |
|---|---|
| 授業形態 | オンラインでの個別指導 |
| 入会金 | 28,600円 |
| 料金 | 小学生 1,100円〜/月 中学生 1,650円/月 高校生 2,750円/月 |
| 無料体験 | ◯ |
| 講師 | 大学生講師、社会人講師 |
| 特徴 | ・不登校の生徒を専門としたオンライン家庭教師 ・学習支援だけでなく、精神的なサポートや進路相談にも対応 ・一人ひとりの状況に合わせた個別カリキュラムを作成 ・保護者との連携を密にし、家庭学習のサポートも行う |
高校受験の出席日数に不安がある中学生におすすめの家庭教師3つ目は、ティントルです。ティントルは、「授業をしない」家庭教師サービスで、お子さま専用の学習計画を作成し、LINEで毎日の自習を徹底管理するのが特徴です。
不登校支援にも力を入れており、出席日数の不安や内申点対策についても相談できます。先生が隣にいなくても、毎日の学習習慣を確立し、自走できる力を身につけさせたい人におすすめです。
\ 無料体験・面談予約はこちら /
高校受験の出席日数に関するよくある質問(FAQ)
高校受験の出席日数に関するよくある質問と回答をまとめました。出席日数に関してよくある疑問や不安を解消しましょう。
中学校の出席日数が足りない場合はどうなる?高校入試自体受けられない?
中学校の出席日数が足りない場合でも、高校入試自体を受けられないケースはまれです。ただし、公立高校では欠席日数が多いと「審議の対象」となり、定員割れしていても不合格になる可能性があります。
私立高校の推薦入試では、出願基準として欠席日数の上限(例:年間10日以内)が定められていることが多く、基準を満たさないと出願できません。
しかし、一般入試や通信制・定時制高校など、出席日数を問わない入試形態も多く存在します。
高校受験で推薦入試を考えているけど出席日数は影響する?
高校受験で推薦入試を考えている場合、出席日数は合否に大きく影響します。多くの高校では、推薦入試の出願資格として「内申点〇〇以上」といった成績基準に加え、「3年間の欠席日数が合計〇〇日以内」といった出席状況の基準を設けています。
この基準を満たしていないと、推薦入試に出願すること自体ができません。公立・私立問わず、推薦入試は一般入試よりも厳しい出席基準が求められると理解しておきましょう。
高校受験の調査書には中学校で欠席した理由まで詳しく書かれる?
高校受験の調査書に、欠席した理由まで詳しく書かれることは一般的ではありません。調査書には「出欠の記録」として学年ごとの欠席日数が数字で記載されるのが基本です。
ただし「備考欄」があり、担任の先生が「病気療養のため(診断書あり)」といった特記事項を簡潔に記載する場合があります。
病気やけがなど、やむを得ない事情がある場合は、事前に診断書を提出し、先生に事情を伝えておくことが望ましいです。
中学校の時の遅刻や早退は何回で欠席1日扱いになる?
中学校での遅刻や早退を何回で欠席1日扱いにするかは、自治体や学校によってルールが異なります。「遅刻・早退を合計3回で欠席1日としてカウントする」と定めている地域もあれば、回数をそのまま記載し、欠席日数とは別に扱う地域もあります。
遅刻や早退の回数も調査書には記載されるため、欠席日数と同様に多い場合は評価に影響する可能性があります。
お子さまが通う中学校のルールについては、担任の先生に確認するのが確実です。
まとめ
高校受験で中学の出席日数が「関係ない」は嘘です。内申書に影響し、特に公立高校や推薦入試で不利になる可能性があります。
目安は年間30日・3年で90日以上ですが、欠席が多くてもあきらめる必要はありません。学力検査で高得点を取ってカバーする、面接で意欲を伝える、学力重視の私立高校や通信制高校を選ぶなどの対策は必ず存在します。
まずは先生に相談し、塾や家庭教師も活用して合格を目指しましょう。






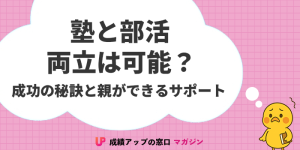

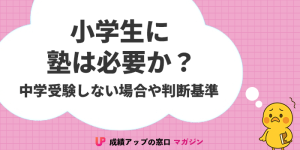


コメント