 ひよこ生徒
ひよこ生徒テスト前日ってどれくらい寝ればいいの?
テスト前の睡眠時間、みんなどれくらい取ってるんだろう…
テスト前日の睡眠時間は、最低でも何時間必要なの?
テスト前日になると「勉強が終わらないから徹夜(一夜漬け)しようか」「でも寝ないと記憶が定着しないって聞くし…」と、睡眠時間をどれだけ確保すべきか悩みますよね。
この記事では、テスト前日に必要な最低限の睡眠時間から、徹夜がNGな理由、そして睡眠時間を確保しつつ点数をアップさせる効率的な勉強法まで詳しく解説していきます。
テスト当日に実力を最大限発揮したい人は、ぜひ参考にしてみましょう。



テスト前日の睡眠は、勉強した内容を「記憶」に変えるための重要な時間です。
この記事で紹介する時間帯別の勉強のコツや睡眠の質を高める方法を実践し、万全の態勢でテスト本番を迎えましょう。
- テスト前日に必要な最低限の睡眠時間と理想の時間
- テスト前日の徹夜(一夜漬け)がNGな理由とメリット
- 睡眠時間を確保する効率的な勉強法
- テスト前日の睡眠の質を高める方法
- テスト当日の朝にスッキリ目覚めるコツ
テスト前日の睡眠時間はどれくらい必要?ベストは何時間?
結論として、記憶の定着とテスト当日のパフォーマンスを考えると、最低でも6時間は睡眠時間を確保するのがおすすめです。
ここでは、テスト前日に必要な睡眠時間について、理想と最低ライン、学年別の推奨時間などを解説します。
ひとつずつ見ていきましょう。
理想の睡眠時間は6時間から7時間半
テスト前日の睡眠時間として理想的なのは、6時間から7時間半です。睡眠には、浅い眠りの「レム睡眠」と深い眠りの「ノンレム睡眠」があり、約90分の周期で繰り返されます。
このサイクルにあわせて、6時間(90分×4サイクル)や7時間半(90分×5サイクル)の睡眠をとることで、脳に記憶が定着しやすくなります。
スッキリと目覚めやすくなるため、テスト当日の午前中から脳をしっかり働かせられます。



記憶の定着と翌日の集中力には、睡眠の質と量が大切ですよ。
最低でも確保したい睡眠時間のラインは?
テスト前日に最低でも確保したい睡眠時間は、6時間です。勉強が終わらず焦る気持ちから睡眠時間を削りたくなるかもしれませんが、6時間を下回ると、脳の疲労が回復しきれません。
結果として、勉強した内容が記憶として定着しにくくなるだけでなく、テスト当日に集中力が続かず、ケアレスミスを連発する可能性が高まります。
どれだけ勉強が残っていても、最低6時間の睡眠は死守する意識を持ちましょう。
睡眠時間がテストの点数に与える影響
睡眠時間は、テストの点数に直接的な影響を与えます。睡眠は、日中に学習した情報を脳内で整理し、記憶として定着させるために不可欠な時間だからです。
十分な睡眠時間を確保するほど、暗記した内容や解法パターンが長期的な記憶として残りやすくなります。逆に睡眠時間が不足すると、記憶が定着しないばかりか、当日の集中力や思考力が低下し、本来の実力を発揮できなくなる恐れがあります。
【中学生・高校生別】定期テスト期間で推奨される睡眠時間
テスト期間中に推奨される睡眠時間は、中学生と高校生で異なります。一般的に、成長期にある中学生のほうが、高校生よりも長い睡眠時間を必要とします。
| 学年 | 推奨される睡眠時間 | 概要 |
|---|---|---|
| 中学生 | 7時間~8時間 | 成長と記憶定着の両方に必要な時間を確保することが望ましいです。 |
| 高校生 | 6時間~7時間半 | 受験勉強などで忙しくなりますが、記憶効率を維持するために最低6時間は必要です。 |
もちろん個人差はありますが、自分の学年にあわせて、テスト当日のパフォーマンスが最大になる睡眠時間を確保するよう心がけましょう。
テスト前日は寝るべきか?徹夜(一夜漬け)か?
テスト前日は基本的には睡眠をとるべきですが、状況によっては徹夜(一夜漬け)を選択せざるを得ない場合もあります。
ここでは、寝るべきかの判断基準と、学習の定着度別のケーススタディを紹介します。
詳しく解説します。
テスト前日に寝るべきかの判断基準
テスト前日に寝るべきかの判断基準は、主に「目標点数と現在の理解度」および「翌日のテスト教科」の2つです。
- 目標点数と現在の理解度
- 翌日のテスト教科|暗記系か思考系か
これらのバランスを見て、睡眠時間をどれだけ確保するか、あるいは徹夜するかの最終判断をしましょう。詳しく見ていきます。
判断基準①目標点数と現在の理解度
テスト前日に寝るべきかを判断する基準の1つ目は、目標点数と現在の理解度のギャップです。たとえば、目標が80点なのに対して、現在の理解度が20%程度であれば、睡眠時間を削ってでも勉強時間を確保する(徹夜する)選択肢も現実的になります。
逆に、すでに80%程度の理解度があり、ケアレスミスをなくして100点を目指す状況であれば、新たな知識を詰め込むよりもしっかり睡眠をとり、当日の集中力を高めるほうが合理的です。
判断基準②翌日のテスト教科|暗記系か思考系か
テスト前日に寝るべきかを判断する基準として、翌日のテスト教科が暗記系か思考系かも挙げられます。歴史や英単語などの暗記系科目は、一夜漬けでもある程度の点数上乗せが期待できます。
知識を詰め込む絶対量が点数に反映されやすいためです。一方、数学や物理などの思考系科目は、睡眠不足による集中力や思考力の低下が致命的になります。
解法をひらめく力や、複雑な計算をやり遂げる力は、脳がしっかり休息していないと発揮できません。
【ケース別】テスト前日の睡眠時間の指標
テスト前日の睡眠時間の指標を、学習の定着度と目標点数に応じた3つのケーススタディで紹介します。
- 定着度20%で目標80点を目指す場合
- 定着度60%で目標80点を目指す場合
- 定着度90%で目標100点を目指す場合
ご自身の状況に近いものを参考にしてください。
ケーススタディ①定着度20%で目標80点を目指す場合
テスト前日の睡眠時間の指標として、定着度20%で目標80点を目指す場合は、徹夜または仮眠(1時間~3時間)を視野に入れてもいいでしょう。
この状況は、明らかに勉強の絶対量が不足しています。睡眠による記憶の定着を期待する段階ではなく、まずはテスト範囲の知識を少しでも多く頭に詰め込むことが最優先となります。
ただし、徹夜明けは集中力が続かないため、ケアレスミスで点数を落とすリスクも高まります。あくまで最終手段と考えましょう。
ケーススタディ②定着度60%で目標80点を目指す場合
定着度60%で目標80点を目指す場合は、テスト前日の睡眠時間の指標として4時間半程度の睡眠を確保するのがひとつの目安です。
基本的な内容は理解しているものの、応用問題や細かい知識が不足している状態です。睡眠サイクルの3周期分(90分×3回=4時間半)の睡眠を確保し、最低限の記憶の定着と脳の休息を行います。
そして、寝る直前まで暗記項目を確認し、起床後も早めに起きて思考系の問題演習を行うなど、睡眠時間以外をすべて勉強に充てる必要があります。
ケーススタディ③定着度90%で目標100点を目指す場合
定着度90%で目標100点を目指す場合は、テスト前日に6時間以上の十分な睡眠をとるべきです。この段階では、新たな知識を詰め込むよりも、当日の集中力を最大化し、ケアレスミスを防ぐことが最も重要です。
十分な睡眠をとることで、脳がクリアな状態でテストに臨め、覚えた知識を正確にアウトプットできます。直前は新しい問題に手を出さず、これまで間違えた箇所の最終確認にとどめ、早めに就寝しましょう。



自分の状況に合わせて睡眠時間を決めるのも戦略のひとつです。
テスト前日の睡眠不足や徹夜がNGな理由【デメリット】
テスト前日の睡眠不足や徹夜は、勉強した努力を無駄にする可能性があり、基本的におすすめできません。ここでは、テスト前日の睡眠不足や徹夜がNGな4つのデメリットを解説します。
ひとつずつ解説します。
デメリット①勉強した内容が記憶として定着しにくい
テスト前日の睡眠不足や徹夜がNGな理由の1つ目は、勉強した内容が記憶として定着しにくいからです。脳は、私たちが寝ている間(とくにノンレム睡眠中)に、日中に学習した情報を整理し、短期記憶から長期記憶へと移行させる作業を行っています。
テスト前日に徹夜すると、この記憶を定着させるプロセスが省略されてしまいます。せっかく時間をかけて覚えたことも、脳に定着しないままテスト本番を迎えることになり、非常に効率が悪いです。



徹夜で頑張ったのに、テスト中に思い出せないのはなぜですか?



睡眠中に記憶を整理する時間が取れていないからかもしれませんね。
デメリット②集中力や思考力が大幅に低下する
テスト前日の睡眠不足や徹夜がNGな理由として、集中力や思考力が大幅に低下する点も挙げられます。睡眠不足の状態では、脳が十分に休息できておらず、パフォーマンスが著しく低下します。
具体的には、以下のようなミスを連発しがちです。
- テストの問題文が頭に入ってこない
- 簡単な計算ミスを繰り返す
- 漢字や英単語を思い出せない
とくに数学や国語の読解問題など、高い集中力と思考力を要する科目では、睡眠不足が致命傷となります。
デメリット③テスト当日の体調不良につながる
テスト前日の睡眠不足や徹夜がNGな理由には、テスト当日の体調不良につながることも挙げられます。徹夜をすると自律神経が乱れ、以下のような不調を引き起こす可能性があります。
- 頭痛
- 腹痛、吐き気
- 免疫力の低下による風邪
テスト当日に万全の体調で臨めなければ、どれだけ勉強していても実力を発揮できません。体調管理もテスト勉強の重要な一部です。
デメリット④長期的な記憶に残りづらい
テスト前日の睡眠不足や徹夜がNGな4つ目の理由は、勉強した内容が長期的な記憶に残りづらいからです。一夜漬けで詰め込んだ知識は、あくまで一時的な「短期記憶」にとどまりがちです。
テストが終わった瞬間に、覚えた内容のほとんどを忘れてしまう可能性が高いです。定期テストの勉強は、本質的には大学受験や将来のための土台作りです。
その場しのぎの勉強では、次の学年や受験期に結局苦労することになります。
テスト前日の一夜漬けで得られるメリット
テスト前日の徹夜(一夜漬け)はデメリットが多い一方、状況によってはメリットをもたらす場合もあります。ここでは、テスト前日の一夜漬けで得られる3つのメリットを解説します。
詳しく見ていきましょう。
メリット①一時的に高い集中力を発揮できる
テスト前日の一夜漬けで得られるメリットの1つ目は、一時的に高い集中力を発揮できることです。「明日がテスト本番」という切迫した状況が、脳を一種の興奮状態にします。
この興奮作用により、普段はなかなか集中できない人でも、驚くほどの集中力で勉強に取り組める場合があります。いわゆる「火事場の馬鹿力」のような状態で、短時間で大量の情報をインプットできる可能性があります。



徹夜はあくまで最終手段。頼りすぎないことが大切ですよ。
メリット②何もしないよりは点数を上乗せできる
テスト前日の一夜漬けのメリットとして、何もしないよりは点数を上乗せできる点も挙げられます。勉強がまったく手についておらず、理解度が0%に近い状況の場合、そのまま寝てしまえば当然0点です。
しかし、徹夜してでも教科書の太字や重要語句だけでも詰め込めば、選択問題や穴埋め問題で数点でも稼げる可能性が生まれます。
赤点を回避したい場合など、最低限の点数確保には有効な手段といえます。
メリット③副教科など暗記中心の科目には有効な場合も
テスト前日の一夜漬けは、副教科など暗記中心の科目には有効な場合がある点もメリットです。保健体育、技術・家庭科、美術などの副教科は、主要5教科に比べてテスト範囲が狭く、知識の暗記が中心となるケースが多いです。
このような暗記科目は、思考力よりも知識のインプット量が点数に直結しやすい傾向があります。そのため、寝る直前に詰め込んだ短期記憶でも、翌日のテストでそのまま解答できる可能性が高いです。
テスト前日の睡眠時間を確保する効率的な勉強法
テスト前日に十分な睡眠時間を確保するには、それまでの勉強をいかに効率良く進めるかが鍵となります。やみくもに勉強するのではなく、ポイントを絞って短時間で成果を出す工夫が必要です。
ここでは、テスト前日の睡眠時間を確保するための効率的な勉強法を5つの手順で解説します。
- まずテスト範囲の全体像と重要箇所を把握する
- 解けなかった問題や苦手分野に絞って復習する
- 教科書やノートで先生が強調した部分を見返す
- 提出物や課題は先に終わらせておく
- 休憩時間や移動などのスキマ時間を活用する
各ステップを順に見ていきましょう。
手順①まずテスト範囲の全体像と重要箇所を把握する
テスト前日の睡眠時間を確保する効率的な勉強法の最初の手順は、まずテスト範囲の全体像と重要箇所を把握することです。
勉強を始める前に、テストの範囲表や授業中の配布プリント、先生のコメントなどを確認し「どこが重要か」「どこが配点が高そうか」を特定します。
全体像をつかんで優先順位をつけることで、出題される可能性の低い部分に時間を浪費するのを防ぎ、効率的な学習計画を立てられます。



効率よく勉強するには、まず計画を立てることから始めましょう。
手順②解けなかった問題や苦手分野に絞って復習する
テスト前日の睡眠時間を確保する効率的な勉強法として、解けなかった問題や苦手分野に絞って復習する点も挙げられます。
すでに解ける問題を何度もやり直すのは非効率です。テスト前日にやるべきことは、自分の「できない」を「できる」に変える作業です。具体的には、以下の点に集中しましょう。
- 問題集や小テストで間違えた問題
- 解答を見るまで解き方が思い浮かばなかった問題
- 以前に苦手だと感じた単元
点数の伸びしろは苦手分野にこそあるため、ここに絞って復習するが点数アップの近道です。
手順③教科書やノートで先生が強調した部分を見返す
テスト前日の睡眠時間を確保するには、教科書やノートで先生が強調した部分を見返すのも効率的な勉強法です。先生が授業中に「ここはテストに出るぞ」「重要だ」と強調した部分や、何度も繰り返して説明した部分は、実際に出題される可能性が非常に高いです。
テスト前日は時間が限られているため、教科書やノートを最初からすべて読み返すのは得策ではありません。重要箇所に絞って見返すことで、短時間で得点源となる知識を確実に復習できます。
手順④提出物や課題は先に終わらせておく
テスト前日の睡眠時間を確保する効率的な勉強法の4つ目の手順は、提出物や課題は先に終わらせておくことです。テスト範囲に関わるワークやプリントなどの提出物は、成績(内申点)に含まれるだけでなく、それ自体がテスト対策にもなります。
これらをテスト前日や当日の朝に慌ててやると、本来やるべき復習の時間が奪われるうえ、焦りから精神的な余裕もなくなります。
提出物は数日前までに終わらせておき、前日は純粋なテスト勉強に集中できる環境を整えましょう。
手順⑤休憩時間や移動などのスキマ時間を活用する
テスト前日の睡眠時間を確保する効率的な勉強法として、休憩時間や移動などのスキマ時間を活用することも挙げられます。
まとまった勉強時間だけでなく、日常生活のなかの短い時間も有効に使いましょう。たとえば、以下のような時間の活用が可能です。
- 通学の電車やバスでの英単語や古文単語の暗記
- 学校の10分休みでのノートの見直し
- 食事後の5分間での歴史の年号チェック
このような「チリも積もれば」式の勉強が、夜の勉強時間を確保し、結果として十分な睡眠時間につながります。
【時間帯別】テスト前日の勉強スケジュールのコツ
テスト前日は、時間帯ごとに勉強する内容を工夫すると効率が上がります。脳の働きにあわせて、暗記系と思考系の勉強を戦略的に配置しましょう。
ここでは、テスト前日の勉強スケジュールのコツを時間帯別に解説します。
時間帯別のコツを詳しく解説します。
【夜・就寝前】暗記科目を中心に勉強する
テスト前日の勉強スケジュールのコツとして、夜・就寝前は暗記科目を中心に勉強するのがおすすめです。睡眠には、勉強した情報を記憶として定着させる働きがあります。
そのため、寝る直前にインプットした内容は、睡眠中に脳内で整理され、忘れにくくなります。具体的には、以下のような科目が向いています。
- 英単語や古文単語
- 歴史の年号や出来事
- 理科や社会の重要語句
思考力が必要な数学の問題を夜遅くまで解くよりも、暗記科目を寝る前に集中して詰め込み、そのまま寝て記憶の定着を図るほうが効率的です。



夜遅くまで数学を解くのと、英単語を覚えるのはどちらが良いですか?



寝る直前は、睡眠中に記憶が定着しやすい暗記科目がおすすめですよ。
【朝】思考力が必要な数学などの復習をする
テスト前日の勉強スケジュールのコツとして、朝は思考力が必要な数学などの復習をするといいでしょう。睡眠によって脳の疲労が回復した朝は、1日のなかで最も集中力や思考力が高まるゴールデンタイムです。
朝の時間帯には、以下のような頭を使う科目の復習に取り組むのが適しています。
- 数学の応用問題
- 物理の計算
- 国語の読解問題
テスト当日の朝も、早めに起きて思考系の科目を見直すと、本番に向けて脳の準備運動になります。
わからないことは早めに解決するのが基本
テスト前日の勉強スケジュールを立てるうえで、わからないことは早めに解決しておくのが基本です。テスト前日になって「わからない」と焦っても、先生や友人にすぐに質問できるとは限りません。
勉強を進めるなかで疑問点が出てきたら、付箋を貼るなどして印をつけ、翌日(遅くともテスト2日前まで)には学校で先生に質問して解決しておきましょう。
「わからない」を放置したまま前日を迎えると、そこが気になって他の勉強が手につかなくなることもあります。早めに対処しておくことが、前日の効率的な復習と睡眠時間の確保につながります。
テスト前日の睡眠の質を高める4つの方法
テスト前日は、睡眠時間を確保するだけでなく「睡眠の質」を高めることも点数アップには不可欠です。ぐっすり眠ることで、脳は効率よく記憶を定着させられます。
ここでは、テスト前日の睡眠の質を高める4つの方法を紹介します。
ひとつずつ解説します。
方法①就寝する1時間前までに入浴を済ませる
テスト前日の睡眠の質を高める方法の1つ目は、就寝する1時間前までに入浴を済ませることです。入浴で一時的に上がった体の深部体温が、下がり始めるタイミングで人は自然な眠気を感じます。
就寝の約1時間前までに、ぬるめのお湯にゆっくり浸かることで、ベッドに入るころにちょうど良く体温が下がり、スムーズな入眠につながります。
熱すぎるお湯や、寝る直前のシャワーは交感神経を刺激してしまうため、避けるのが賢明です。



睡眠の「質」を高める工夫も、点数アップにつながる大切な行動です。
方法②食事は就寝する3時間前までに終える
テスト前日の睡眠の質を高める方法として、食事は就寝する3時間前までに終える点も挙げられます。寝る直前に食事をとると、睡眠中も胃腸が消化活動を続けることになり、脳や体が十分に休まりません。
結果として眠りが浅くなり、記憶の定着が妨げられる可能性があります。とくに脂っこいものや消化に悪いものは避け、勉強で小腹が空いたときは温かいミルクやハーブティーなど、消化に良くリラックスできるものを選びましょう。
方法③カフェインなど覚醒作用のある飲み物や食べ物を避ける
テスト前日の睡眠の質を高めるには、カフェインなど覚醒作用のある飲み物や食べ物を避けることも必要です。カフェインには脳を興奮させる作用があり、入眠を妨げるだけでなく、睡眠を浅くしてしまいます。
カフェインの効果は数時間続くため、テスト前日の午後は以下のような飲み物や食べ物を控えるようにしましょう。
- コーヒー
- 紅茶、緑茶
- エナジードリンク
- チョコレート
眠気覚ましに頼りたくなりますが、質のいい睡眠のためには我慢が必要です。
方法④スマホやゲームは早めに切り上げてリラックスする
テスト前日の睡眠の質を高める4つ目の方法は、スマホやゲームは早めに切り上げてリラックスすることです。スマートフォンやゲーム機などの画面が発するブルーライトは、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌を抑制してしまいます。
SNSや動画、ゲームの内容が脳を興奮させ、寝つきを悪くする原因にもなります。遅くとも就寝30分前にはスマホやゲームをやめ、音楽を聴いたり、軽いストレッチをしたりするなど、心身ともにリラックスできる時間を過ごしましょう。
テスト当日の朝にスッキリ目覚める3つのコツ
テスト当日の朝にスッキリ目覚めることは、テストのパフォーマンスを大きく左右します。脳をしっかり覚醒させ、万全の態勢で本番に臨むための簡単なコツがあります。
ここでは、テスト当日の朝にスッキリ目覚める3つのコツを紹介します。
ひとつずつ見ていきましょう。
コツ①テスト開始の3時間前には起きる
テスト当日の朝にスッキリ目覚めるコツの1つ目は、テスト開始の3時間前には起きることです。脳が完全に覚醒し、最高のパフォーマンスを発揮できるようになるまでには、起床から約3時間かかると言われています。
たとえば、1限目のテストが9時に始まるなら、朝6時に起きるのが理想です。起きてすぐに頭が働くわけではないため、ギリギリまで寝ていると、テストが始まったときにまだ脳が寝ぼけた状態になりかねません。
早く起きることで、朝ごはんを食べたり、最終確認をしたりする時間も確保でき、心にも余裕が生まれます。



当日の朝バタバタしないよう、脳が目覚める時間も逆算しましょう。
コツ②起きたらすぐにカーテンを開けて光を浴びる
テスト当日の朝にスッキリ目覚めるコツとして、起きたらすぐにカーテンを開けて光を浴びる点も挙げられます。人間の体は、朝日を浴びることで睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が止まり、体内時計がリセットされて活動モードのスイッチが入ります。
アラームで無理やり起きただけでは、体はまだお休みモードのままです。起きたらまずカーテンを開け、太陽の光を部屋に取り込みましょう。
光の刺激が脳を目覚めさせ、自然な覚醒を促します。曇りや雨の日でも、窓際で外の明るさを感じるだけでも効果があります。
コツ③朝ごはんをしっかり食べて脳にエネルギーを送る
テスト当日の朝にスッキリ目覚める3つ目のコツは、朝ごはんをしっかり食べて脳にエネルギーを送ることです。脳が活動するための唯一のエネルギー源はブドウ糖です。
寝ている間に消費されたブドウ糖を補給しないと、脳はエネルギー不足のままテストに臨むことになります。朝ごはんを抜くと、集中力が続かず、思考力も低下してしまいます。
とくにご飯やパンなどの炭水化物は、消化されてブドウ糖に変わるため、必ず摂取しましょう。あわせて、タンパク質やビタミンもバランス良く摂ることで、脳の働きを長時間サポートできます。
テスト前日の睡眠時間に関するよくある質問(FAQ)
テスト前日の睡眠時間に関するよくある質問と回答をまとめました。睡眠時間に関する疑問や不安を解消しましょう。
テスト前日に3時間や4時間の睡眠でも大丈夫?
テスト前日に3時間や4時間の睡眠をとることは、おすすめできません。理想は6時間以上の睡眠です。3時間や4時間の睡眠では、勉強した内容の記憶が定着しにくいだけでなく、当日の集中力や思考力が大幅に低下します。
その結果、問題文を読み間違えたり、簡単な計算ミスをしたりするなど、ケアレスミスを連発する可能性が高くなります。
勉強が間に合わない場合でも、睡眠サイクル(約90分)にあわせた4時間半を最低ラインとし、3時間台は避けるのが賢明です。
テスト前日に睡眠時間を削るかオールするか迷ったらどっちがいい?
テスト前日に睡眠時間を削るかオール(徹夜)するかで迷った場合は、短時間でも睡眠時間を確保するほうがいいでしょう。
徹夜をすると、記憶を定着させる脳の働きが完全に止まってしまいます。さらに、当日は極度の集中力低下や体調不良に見舞われるリスクがあります。
たとえ3時間や4時間半だけでも睡眠をとれば、最低限の脳の休息と記憶の整理が行われます。理想は6時間以上ですが、徹夜よりは短時間睡眠のほうがテスト本番のダメージは少ない可能性が高いです。
テスト前日にどうしても眠れない時はどうしたらいい?
テスト前日にどうしても眠れない時は、焦らずリラックスすることを最優先にしましょう。無理に「寝なければ」と考えると、かえって脳が興奮してしまいます。
一度ベッドから出て、ノンカフェインの温かい飲み物を飲んだり、静かな音楽を聴いたりするのもひとつの方法です。
このとき、勉強道具を見ると脳が覚醒してしまうため、目に入れないようにしましょう。ベッドに戻ったら、目をつむって横になるだけでも体は休まります。
数学のテスト前日もやっぱり寝たほうがいい?
数学のテスト前日こそ、しっかり睡眠をとるべきです。数学は、知識の暗記以上に、論理的な思考力や計算の正確性、解法をひらめく力が求められます。
これらの高度な脳の働きは、睡眠不足によって最も低下しやすい能力です。徹夜で問題演習を詰め込んでも、当日に脳が疲弊していては実力を発揮できません。
解法パターンや公式の最終確認を終えたら早めに就寝し、脳を万全の状態で本番に臨ませましょう。
まとめ
テスト前日の最適な睡眠時間や、徹夜のデメリット、効率的な勉強法について解説しました。テストで高得点を狙うには、勉強時間を確保するだけでなく、勉強した内容を記憶に定着させるための「睡眠時間」が不可欠です。
徹夜(一夜漬け)は、記憶が定着しないばかりか、当日の集中力低下や体調不良を招き、実力を発揮できなくなるリスクがあります。
理想は6時間~7時間半、最低でも6時間(難しい場合でも4時間半)の睡眠を確保できるよう、計画的に勉強を進めることが重要です。
この記事で紹介した時間帯別の勉強法や、睡眠の質を高めるコツも参考にして、万全の状態でテスト本番に臨みましょう。





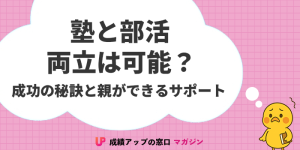

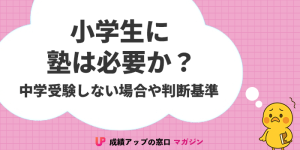



コメント