 ひよこ生徒
ひよこ生徒「子供が勉強しない理由は100%親にある」って本当?
うちの子が勉強しないのも、私のせいなのかな…
親がどう関われば、子供は勉強するようになるの?
「子供が勉強しない理由は100%親にある」という言葉を見て、ドキッとしている親御さんも多いと思います。 子供が勉強しない背景には、親の関わり方だけでなく、子供自身の心理や環境など様々な要因が関係しています。
そこで、この記事では「子供が勉強しない理由は100%親にある」と言われる背景や、子供のやる気を奪う親のNG行動、やる気を引き出すサポート術について詳しく解説していきます。



すべてを親のせいだと抱え込む必要はありません。
この記事で子供が勉強しない本当の理由と、親ができるサポート方法をしっかり学んでいきましょう。
- 「子供が勉強しない理由は100%親にある」の真偽
- 子供のやる気を奪う親のNG行動12選
- 子供が勉強しない親以外の理由
- 子供のやる気を引き出す親の具体的なサポート術
「子供が勉強しない理由は100%親にある」は本当?
「子供が勉強しない理由が100%親にある」という言葉に、不安を感じる保護者の方もいるかもしれません。しかし、すべてを親のせいだと抱え込む必要はありません。
以下の項目に分けて、詳しく解説します。
ひとつずつ見ていきましょう。
「100%親のせい」と考えるのは親も子も辛い
子供が勉強しない理由が「100%親のせい」と考えるのは、親も子も辛くなるため避けるべきです。 保護者が「自分の育て方が悪かった」と過度に自分を責めると、その不安やプレッシャーが子供に伝わり、かえって勉強への抵抗感を強める可能性があります。
子供自身も「親のせいで勉強できない」あるいは「親を悲しませている」と感じ、自己肯定感が下がってしまうかもしれません。
「100%親のせい」という考えは、問題解決に向けた前向きな行動を妨げる恐れがあるため、まずは冷静に状況を受け止めることが大切です。
親の関わり方が子供の勉強意欲に影響するのは事実
子供が勉強しない理由として、親の関わり方が子供の勉強意欲に影響するのは事実です。 親が勉強に対して否定的な言葉を使ったり、過度に結果を求めたりすると、子供は勉強そのものにネガティブなイメージを持ってしまいます。
逆に、親が勉強の楽しさや学ぶことの価値を伝え、子供の小さな努力や成長を認める姿勢を見せることで、子供の「やってみよう」という意欲を引き出せます。
家庭でのコミュニケーションや学習への関わり方が、子供のモチベーションに良くも悪くも影響を与えることは理解しておく必要があります。
原因は親だけではない|子供の心理・環境・特性も影響
子供が勉強しない理由は親だけではなく、子供自身の心理状態、学習環境、個々の特性も複雑に影響しています。 たとえば、以下のような多様な要因が考えられます。
- 学校の授業についていけない苦手意識
- 友人関係の悩みやストレス
- ゲームやスマホなど他のことへの興味
- 勉強のやり方がわからない
- 発達特性による学習の困難さ
「親のせい」と一点だけを責めるのではなく、子供が置かれている状況や特性など、多角的な視点から原因を探ることが、解決の第一歩となります。



原因を一つに決めつけず、お子さまの全体を見てあげましょう。
勉強しない子供の親に見られる12のNG行動と特徴
子供が勉強しない背景には、親の無意識なNG行動が隠れている場合があります。お子さまのやる気を削がないためにも、日頃の関わり方を見直してみましょう。
- 頭ごなしに「勉強しなさい」と叱る・命令する
- 過干渉・過保護で口を出しすぎる
- 子供への期待を押し付ける・否定的な言葉を使う
- 「本人に任せている」と無関心・放置する
- 親自身が勉強する姿を見せない・学びに無関心
- 学校や塾に丸投げしている
- 夫婦仲が悪い・家庭環境が不安定
- 子供の気持ちを理解しようとしない
- 結果だけで評価する・子供の努力の過程を認めない
- 子供の小さな成功体験を奪っている
- 子供の個性を認めない
- 他人(兄弟・友達)と比較する
ひとつずつ解説します。
NG行動①頭ごなしに「勉強しなさい」と叱る・命令する
勉強しない子供の親に見られるNG行動の1つ目は、頭ごなしに「勉強しなさい」と叱る・命令することです。子供は「やらされている」と感じ、自主的なやる気を失ってしまいます。
命令や叱責は、一時的に子供を机に向かわせるかもしれませんが、勉強への抵抗感や反発心を育てるだけです。「勉強しなさい」は、子供にとっては「自分は信頼されていない」というメッセージにも聞こえがちです。
まずは子供の状況に関心を持ち、なぜ勉強に取り組めないのかを理解しようとする姿勢が求められます。



つい「勉強しなさい」って言っちゃう時はどうしたら…?



まずは「宿題終わった?」など、関心を示す言葉に変えてみましょう。
NG行動②過干渉・過保護で口を出しすぎる
勉強しない子供の親に見られるNG行動として、過干渉・過保護で勉強に口を出しすぎる点も挙げられます。勉強のスケジュール管理から宿題のやり方まで、親がすべて先回りして指示を出すと、子供は「自分で考える力」や「計画的に行動する力」を養う機会を失います。
「親に言われたとおりにやればいい」という受け身の姿勢が定着し、自分で問題を解決しようとする意欲が育ちません。
子供が自分で試行錯誤し、失敗から学ぶプロセスを見守ることも大切です。過度な手出しは、子供の自主性を奪うNG行動といえます。
NG行動③子供への期待を押し付ける・否定的な言葉を使う
勉強しない子供の親に見られるNG行動の3つ目は、子供への期待を押し付けたり、否定的な言葉を使ったりすることです。
以下のような言葉は、親の期待が子供にとって過度なプレッシャーとなります。
- 「あなたならできるはず」
- 「なんでこんな問題もわからないの?」
- 「どうせやっても無駄」
期待に応えられないと感じた子供は、失敗を恐れて勉強への挑戦そのものを避けるようになる可能性があります。否定的な言葉は、子供の自己肯定感を著しく傷つけ「自分はできないんだ」と思い込ませてしまいます。
NG行動④「本人に任せている」と無関心・放置する
勉強しない子供の親に見られるNG行動には「本人に任せている」と無関心・放置することも含まれます。過干渉が問題である一方、「子供の自主性を尊重する」という名目で勉強に一切関わらないのもNGです。
とくに小学生や中学生の場合、自分一人で学習計画を立て、継続して勉強するのは簡単ではありません。親が無関心だと、子供は「勉強しなくても何も言われない」「自分は気にかけてもらえていない」と感じ、学習意欲がさらに低下する恐れがあります。
適度な距離感を保ちつつ、学習状況に関心を持ち、必要なときにサポートできる体制を整えておくことが求められます。



自主性も大事ですが、中学生までは親御さんの関心が必要です。
NG行動⑤親自身が勉強する姿を見せない・学びに無関心
勉強しない子供の親に見られるNG行動の5つ目は、親自身が勉強する姿を見せず、学びに対して無関心なことです。子供に「勉強しなさい」と言いながら、親がテレビやスマホばかり見ているようでは説得力がありません。
子供は親の言動をよく見ており、親が学ぶことを楽しんでいないと感じ取れば、「勉強はつまらないものだ」と認識してしまいます。
親が資格の勉強をしたり、本を読んだりするなど、学ぶ姿勢を日常生活で見せることは、子供にとって何よりのお手本となります。
NG行動⑥学校や塾に丸投げしている
勉強しない子供の親に見られるNG行動として、学校や塾に勉強を丸投げしている点も挙げられます。「高い月謝を払っているのだから、塾が成績を上げてくれるはず」とすべてを任せきりにするのはNGです。
塾や学校はあくまで学習をサポートする場であり、最終的に勉強するのは子供自身です。家庭での学習習慣や精神的なサポートがなければ、塾の効果も半減します。
学校や塾の先生と定期的にコミュニケーションを取り、家庭での様子を共有し、連携して子供の学習を支える姿勢が大切です。
NG行動⑦夫婦仲が悪い・家庭環境が不安定
勉強しない子供の親に見られるNG行動には、夫婦仲が悪く、家庭環境が不安定なことも関係します。両親が頻繁に喧嘩をしていたり、家庭内の雰囲気がピリピリしていたりすると、子供は安心して勉強に集中できる環境を失います。
子供は親の感情に敏感であり、家庭が安全な場所だと感じられなければ、勉強どころではなくなってしまいます。精神的なストレスが学習意欲を阻害する大きな要因となるため、子供がリラックスして過ごせる安定した家庭環境を整えることは、勉強の前提条件として非常に重要です。
NG行動⑧子供の気持ちを理解しようとしない
勉強しない子供の親に見られるNG行動の8つ目は、子供の気持ちを理解しようとしないことです。子供が勉強しない背景には、以下のような子供なりの理由が隠されています。
- 「授業がわからない」
- 「友達関係で悩んでいる」
- 「部活で疲れている」
その気持ちに寄り添わず、一方的に「勉強しないのが悪い」と決めつけると、子供は心を閉ざしてしまいます。まずは親が子供の言い分や感情を受け止め、「何に困っているのか」をていねいに聞く姿勢が、信頼関係の構築と問題解決の糸口になります。
NG行動⑨結果だけで評価する・子供の努力の過程を認めない
勉強しない子供の親に見られるNG行動として、テストの点数や順位といった結果だけで評価し、子供の努力の過程を認めない点が挙げられます。
結果が出なかったときに叱責されると、子供は「努力しても無駄だ」と感じ、やる気を失います。たとえ点数が悪くても、「毎日コツコツと英単語を覚えていたね」「難しい問題にも挑戦していたね」と、頑張ったプロセス自体を具体的に認めてあげることが重要です。
努力を認められることで、子供は「次も頑張ろう」という意欲を持続できます。



点数だけでなく「ここまで頑張ったね」と過程を褒めるのが大切です。
NG行動⑩子供の小さな成功体験を奪っている
勉強しない子供の親に見られるNG行動の10個目は、子供の小さな成功体験を奪っていることです。子供が「宿題が終わった」と報告したときに「当たり前でしょ」「次はもっと難しい問題やりなさい」と返してしまうと、子供の達成感が損なわれます。
「できた!」という小さな成功体験の積み重ねが、勉強への自信とモチベーションにつながります。たとえば「昨日は1ページしかできなかったドリルが、今日は2ページできた」といった小さな進歩を見逃さず、「すごいね!」と認めてあげることで、子供は「やればできる」という感覚を育てることができます。
NG行動⑪子供の個性を認めない
勉強しない子供の親に見られるNG行動として、子供の個性を認めないことも挙げられます。たとえば、以下のようなケースが当てはまります。
- 視覚優位で図解で理解するのが得意な子に、ひたすら音読を強制する
- スポーツや芸術など、勉強以外の才能を「勉強の妨げになる」と否定する
子供の特性に合わない勉強法を押し付けるのはNGです。子供の興味や得意なことを認め、それを学習にどう活かせるかを一緒に考える姿勢が、子供の自己肯定感と学習意欲を守ります。
NG行動⑫他人(兄弟・友達)と比較する
勉強しない子供の親に見られるNG行動の12個目は、他人(兄弟・友達)と比較することです。親としては励ましているつもりでも、以下のような比較は子供のプライドを傷つけ、劣等感を植え付けるだけです。
- 「お兄ちゃんはもっとできたのに」
- 「〇〇ちゃんは塾に行かなくても成績がいいのに」
子供にとっては「自分は兄弟(友達)より劣っている」という否定的なメッセージとして伝わります。比較対象は常に「過去の子供自身」であるべきです。
「前はできなかった計算が早くなったね」と、子供自身の成長を認める言葉かけを心がけましょう。



比べる相手は「昨日のお子さま」です。小さな成長を見つけましょう。
親のせいだけじゃない!子供が勉強しない他の理由
子供が勉強しない理由は、親の関わり方以外にもさまざまです。お子さま自身の心理状態や環境面など、多角的に原因を探ってみましょう。
- 勉強する目的や必要性がわからない
- 学校の授業についていけず苦手意識がある
- 他のやりたいこと(ゲーム・スマホ)に夢中
- 部活や習い事で疲れている
- 自分に合った勉強方法がわからない
- 反抗期で親に反発したい(小学生高学年・中学生)
- 学校や友達との人間関係で悩んでいる(ストレス)
- 勉強する習慣が身についていない
詳しく解説します。
理由①勉強する目的や必要性がわからない
親のせいだけではなく、子供が勉強しない理由の1つ目として、勉強する目的や必要性がわからないことが挙げられます。
大人から「将来のために必要」と言われても、子供にとっては実感が湧かず、勉強へのモチベーションにつながりにくいです。
「なぜ数学を学ぶのか」「歴史を知って何になるのか」といった素朴な疑問に対し、親や周囲の大人が納得できる答えを示せないと、子供は勉強を「やらされる作業」としか認識できません。
勉強が自分の興味や将来の夢とどう結びつくのか、具体的なイメージを持てるようにサポートすることが求められます。
理由②学校の授業についていけず苦手意識がある
子供が勉強しない他の理由として、学校の授業についていけず苦手意識がある点も考えられます。 一度授業でつまずくと、その後の内容が理解できなくなり、勉強全体が嫌いになってしまうケースは多いです。
とくに積み重ねが重要な英語や数学では、一つの単元がわからないまま放置されると、取り返すのが困難になります。 「どうせやってもわからない」と諦めてしまい、机に向かうこと自体を避けるようになります。
子供がどの段階でつまずいているのかを把握し、基礎に戻って学び直すサポートが必要です。



「わからない」が続くと勉強が嫌いになります。早めの復習が鍵です。
理由③他のやりたいこと(ゲーム・スマホ)に夢中
子供が勉強しない理由には、ゲームやスマホ、SNSなど、勉強よりも魅力的な他のやりたいことに夢中になっている場合もあります。
これらは即座に楽しさや達成感を得られるため、地道な努力が必要な勉強よりも優先順位が高くなりがちです。本人の意志だけでゲームやスマホの時間をコントロールするのは難しく、「勉強しなさい」と叱るだけでは反発を招くだけです。
勉強を妨げている要因を否定するのではなく、子供自身が納得できる形でルール(例:1日1時間まで、宿題が終わってから)を一緒に決めることが、学習習慣を取り戻す一歩となります。
理由④部活や習い事で疲れている
子供が勉強しない理由として、部活や習い事で心身ともに疲れている可能性も挙げられます。 とくに中学生や高校生になると、部活動の練習時間が長くなり、帰宅後に勉強する体力や気力が残っていないケースは少なくないです。
親から見ると「だらだらしている」ように見えても、本人は疲労困憊で机に向かえない状態かもしれません。 子供の体力的な限界を考慮せず、無理に勉強を強制すると、かえって心身のバランスを崩す恐れがあります。
まずは十分な休息を確保し、隙間時間でできる勉強法を一緒に考えるなど、現実的な計画が必要です。
理由⑤自分に合った勉強方法がわからない
子供が勉強しない他の理由の5つ目は、自分に合った勉強方法がわからないことです。 「勉強しなさい」と言われても、具体的に「何を」「どのように」勉強すればいいのかわからず、途方に暮れている子供は多いです。
教科書をただ眺めているだけ、ノートを丸写ししているだけなど、非効率な勉強法を続けていても成果は上がらず、やる気を失ってしまいます。
子供の特性(視覚優位、聴覚優位など)を考慮しながら、ノートの取り方や暗記の方法、問題集の使い方など、具体的な勉強の「やり方」を一緒に見つけてあげることがサポートになります。



うちの子、勉強のやり方がわかってないみたいなんです…。



お子さまの特性に合ったやり方があります。一緒に探しましょう。
理由⑥反抗期で親に反発したい(小学生高学年・中学生)
子供が勉強しない理由として、反抗期で親に反発したいという心理が働いている場合もあります。 とくに小学生高学年から中学生にかけては、親からの自立を目指す時期であり、親の指示に素直に従うことに抵抗を感じやすくなります。
この場合、勉強そのものが嫌いなのではなく、「親から『勉強しなさい』と言われたからやりたくない」という動機が強いケースがあります。
親が躍起になって勉強させようとするほど、子供は意固地になって反発します。一時的に距離を置き、勉強に関しては本人に任せる姿勢を見せるほうが、かえって自主的に取り組み始めることもあります。
理由⑦学校や友達との人間関係で悩んでいる(ストレス)
子供が勉強しない理由には、学校や友達との人間関係で悩んでいるなど、強いストレスを抱えていることも考えられます。
以下のような学校生活での悩みは子供の心を大きく占め、勉強に集中する余裕を奪います。
- いじめ
- 友人とのトラブル
- 先生との相性
家に帰っても悩みが頭から離れず、無気力になってしまうことは珍しくありません。 最近、急に勉強しなくなった、元気がなく部屋にこもりがちになったなどの変化が見られる場合は、まずは勉強のことよりも、子供が何に悩んでいるのか、安心して話せる環境を作ってあげることが最優先です。
理由⑧勉強する習慣が身についていない
子供が勉強しない理由の8つ目は、そもそも勉強する習慣が身についていないことです。 小さいころから「決まった時間に机に向かう」という習慣が定着していないと、学年が上がって勉強が難しくなるにつれて、学習に取り組むこと自体が億劫になります。
勉強を特別な「嫌なこと」ではなく、歯磨きなどと同じ「当たり前の習慣」として生活に組み込むことが重要です。最初は1日10分からでもいいので、親子で一緒に時間を決め、毎日継続することをサポートしてあげる必要があります。
勉強しない子をほっとく・見捨てるとどうなる?予想される末路
お子さまが勉強しない状況を放置すると、学力だけでなく、将来の可能性にも影響が及ぶ恐れがあります。
ひとつずつ解説します。
末路①学力が低くなり進学できる学校の選択肢が狭まる
勉強しない子をほっとく・見捨てると、まず学力が低くなり進学できる学校の選択肢が狭まる可能性があります。 勉強しない状態が続くと、基礎学力が定着せず、学年が上がるにつれて授業についていけなくなります。
その結果、高校受験や大学受験において、内申点や学力試験の点数が足りず、希望する学校に進学できない事態になりかねません。
選択肢が限られることで、お子さまが将来やりたいことを見つけたときに、その道に進むためのスタートラインに立てない可能性も出てきます。



将来「やりたいこと」が見つかった時のため、選択肢は多い方が良いですね。
末路②将来の職業の選択肢が限定される
勉強しない子をほっとく・見捨てた場合の末路として、将来の職業の選択肢が限定される点も挙げられます。 多くの職業では、特定の学歴や資格が求められることがあります。
学力が不足していると、医師、弁護士、研究者など、高い専門知識が必要な職業に就くことが難しくなります。就職活動においても、一定の学力や学歴が採用基準の一つとなる企業は少なくありません。
勉強しないことで可能性の幅を自ら狭めてしまい、将来の夢を諦めざるを得ない状況になることも考えられます。
末路③勉強への苦手意識が定着し努力しなくなる
勉強しない子をほっとく・見捨てると、勉強への苦手意識が定着し、努力しなくなる可能性があります。 「どうせやってもわからない」「勉強はつまらない」というネガティブな感情が固定化されると、学ぶこと全般に対して意欲を失ってしまいます。
この状態が続くと、勉強に限らず、困難なことや新しいことへの挑戦を避けるようになり、「努力しても無駄だ」と考えるようになってしまう恐れがあります。
学ぶ意欲の低下は、社会に出てからも新しいスキルを習得する妨げになるかもしれません。
末路④自分に自信が持てず学歴コンプレックスを抱く
勉強しない子をほっとく・見捨てた結果、自分に自信が持てず、学歴コンプレックスを抱くようになることも考えられます。
周囲の友人や兄弟が自分より高い学歴を持っている場合、劣等感を抱きやすくなります。「自分は勉強ができなかった」という思いが自己評価を下げ、何事に対しても消極的になる原因になり得ます。
学歴がすべてではありませんが、コンプレックスが原因で自分の能力を過小評価し、社会での活躍の機会を自ら手放してしまうのは非常にもったいないことです。
子供の勉強のやる気を引き出す親の行動【3つのポイント】
子供が勉強しない状況を変えるには、親の関わり方が鍵となります。ここでは、お子さまのやる気を引き出すために親ができる行動のポイントを3つ紹介します。
詳しく見ていきましょう。
ポイント①まずは親子の信頼関係を整える
子供の勉強のやる気を引き出す親の行動、1つ目のポイントは、まずは親子の信頼関係を整えることです。子供が親を信頼し「自分の味方だ」と感じていなければ、どんな正論を伝えても反発するだけです。
「勉強しなさい」と叱る前に、まずは子供の話を否定せずに聞き、勉強以外の悩みや興味にも関心を持ちましょう。
子供が安心して本音を話せる関係性を築くことが、学習について話し合うための土台となります。
ポイント②勉強のモチベーションを親子で明確にする
子供の勉強のやる気を引き出す親の行動として、勉強のモチベーションを親子で明確にすることも挙げられます。子供は「何のために勉強するのか」がわからないと、やる気が出にくいものです。
「将来のため」といった漠然とした理由ではなく、子供の興味関心と結びつけてみましょう。たとえば、「好きなゲームのキャラクターを英語で理解したい」「旅行先で困らないため」など、身近な目標で構いません。
子供自身が「やりたい」と思える目的を見つける手伝いをすることが大切です。
ポイント③子供が集中できる学習環境を整える
子供の勉強のやる気を引き出すポイント3つ目は、子供が集中できる学習環境を整えることです。子供のやる気があっても、周囲が騒がしかったり、誘惑が多かったりすると集中力は続きません。
物理的な環境整備は、親が具体的にサポートできる行動の一つです。以下のように、子供が勉強に取り組みやすい環境を作りましょう。
- 勉強机の周りから漫画やゲームを片付ける
- テレビが視界に入らないようにする
- リビング学習を取り入れる場合は、親も近くで読書をする
お子さま本人と相談しながら、集中しやすい場所やルールを決めるのもおすすめです。



勉強モードに切り替えるためにも、環境づくりはとても重要です。
今日からできる!子供が勉強するようになる具体的なサポート術
勉強しないお子さまへの関わり方を少し変えるだけで、やる気を引き出せる可能性があります。ここでは、今日からできる具体的なサポート術を8つ紹介します。
- 子供の自己肯定感を高める声かけをする
- 「勉強しなさい」以外の言葉で関心を示す
- 結果より努力の過程を具体的に褒める
- 親も一緒に学ぶ・勉強する手本を見せる
- 小さな目標設定で成功体験を積ませる
- 勉強のやり方や計画を一緒に考える
- スマホやゲームのルールを子供と一緒に決める
- 勉強は「楽しいもの」と親が伝える
ひとつずつ見ていきましょう。
サポート術①子供の自己肯定感を高める声かけをする
子供が勉強するようになる具体的なサポート術の1つ目は、子供の自己肯定感を高める声かけをすることです。勉強への意欲は、「自分ならできるかもしれない」という自信から生まれます。
日頃から「いつもお手伝いしてくれてありがとう」「あなたのそういうところ、素敵だね」など、勉強以外の面でも子供の存在そのものを認める言葉をかけましょう。
子供が自分に自信を持てるようになると、勉強のような困難なことにも「挑戦してみよう」という前向きな気持ちが芽生えやすくなります。
まずは学習面以外で自己肯定感を育むことが、結果的に勉強への意欲にもつながります。



勉強以外の「できた」も自信になり、学習意欲につながります。
サポート術②「勉強しなさい」以外の言葉で関心を示す
子供が勉強するようになる具体的なサポート術として、「勉強しなさい」以外の言葉で関心を示すことも挙げられます。
「勉強しなさい」という命令口調は、子供の反発心を招くだけです。代わりに、以下のような勉強内容そのものに関心を示す声かけをしてみましょう。
- 「今日は学校でどんなこと習ったの?」
- 「その宿題、難しそうだね」
親が自分の学びに興味を持ってくれていると感じることで、子供は「話してみようかな」という気持ちになります。勉強を「やらせる」のではなく、親子共通の話題として捉え、関心を持っている姿勢を見せることが大切です。
サポート術③結果より努力の過程を具体的に褒める
子供が勉強するようになる具体的なサポート術の3つ目は、結果より努力の過程を具体的に褒めることです。テストの点数や順位といった結果だけを評価すると、結果が出なかったときに子供はやる気を失ってしまいます。
「100点ですごいね」だけでなく、「毎日1時間、机に向かって頑張ってたね」「前は苦手だった漢字練習をコツコツ続けたのがえらいね」と、目標達成までのプロセスや姿勢を具体的に認めましょう。
努力そのものを褒められることで、子供は「親は自分の頑張りを見てくれている」と感じ、次も努力しようという意欲が湧いてきます。
サポート術④親も一緒に学ぶ・勉強する手本を見せる
子供が勉強するようになる具体的なサポート術には、親も一緒に学ぶ・勉強する手本を見せることも含まれます。子供に「勉強しなさい」と言う一方で、親がスマホばかり見ているようでは説得力がありません。
親自身が学ぶことを楽しんでいる姿勢は、子供にとって一番のお手本となります。「勉強は大人になっても続く楽しいものだ」というメッセージが伝わり、子供も自然と机に向かいやすくなります。
リビング学習などで一緒に学ぶ時間を作るのもおすすめです。
サポート術⑤小さな目標設定で成功体験を積ませる
子供が勉強するようになる具体的なサポート術の5つ目は、小さな目標設定で成功体験を積ませることです。勉強しない子は、「どうせやってもできない」と自信を失っているケースが少なくありません。
いきなり高い目標を掲げるのではなく、以下のような簡単に達成できる小さな目標を一緒に立てましょう。
- 「今日は計算ドリルを1ページだけやる」
- 「英単語を5個覚える」
「できた!」という小さな成功体験を積み重ねることで、子供は「やればできる」という自信(自己効力感)を取り戻します。
その達成感が、次のステップに進むためのモチベーションになります。



高い目標を立てすぎても、続かないんですよね…。



まずは「ドリル1ページ」など、小さな達成感が自信になります。
サポート術⑥勉強のやり方や計画を一緒に考える
子供が勉強するようになる具体的なサポート術として、勉強のやり方や計画を一緒に考えることも挙げられます。子供は「勉強の仕方がわからない」ために、手が進まない場合も多いです。
親が一方的に計画を押し付けるのではなく、「どの時間なら宿題できそう?」「数学のこの単元、どうやって勉強したらわかりやすいかな?」と、子供の意見を聞きながら一緒に考えます。
「いつ」「何を」「どうやって」勉強するのかを具体的にすることで、子供は見通しを持って学習に取り組めるようになります。
親がサポートする姿勢を見せることで、子供も「一人じゃないんだ」と安心できます。
サポート術⑦スマホやゲームのルールを子供と一緒に決める
子供が勉強するようになる具体的なサポート術の7つ目は、スマホやゲームのルールを子供と一緒に決めることです。
スマホやゲームが勉強の妨げになっている場合、親が一方的に禁止したり取り上げたりするのは逆効果です。子供の反発を招き、隠れて使うようになる可能性があります。
「勉強も大事だけど、ゲームもやりたいよね」と子供の気持ちを受け止めたうえで、「宿題が終わったら1時間まで」「夜9時以降はリビングに置く」など、子供自身に納得感のあるルールを一緒に決めさせることが重要です。



一方的に禁止するより、お子さまが納得するルール作りが大切です。
サポート術⑧勉強は「楽しいもの」と親が伝える
子供が勉強するようになる具体的なサポート術として、勉強は「楽しいもの」と親が伝えることも挙げられます。多くの子供は「勉強=つまらない、面倒なもの」と捉えがちです。
親自身が「勉強しておけばよかった」「勉強は大変だ」といったネガティブな発言を避けましょう。日常生活のなかで、「この計算ができると買い物で役立つね」「歴史を知っていると旅行がもっと楽しくなるよ」など、学ぶことの楽しさやメリットを具体的に伝えてみてください。
親が学ぶことをポジティブに捉えている姿を見せることで、子供の勉強へのイメージも変わっていきます。
子供が勉強できないのは発達障害が理由なことも
子供が勉強しない理由として、本人のやる気や親の関わり方だけでなく、発達障害の特性による「勉強したくてもできない」困難さが関係している可能性もあります。
ひとつずつ見ていきましょう。
勉強の困難さに関連する発達障害の特性(ADHD・SLDなど)
子供が勉強できない理由として、ADHD(注意欠如・多動症)やSLD(限局性学習障害)などの発達障害の特性が関係している場合があります。
これらは本人の努力不足や親の育て方のせいではありません。
| 発達障害の例 | 主な特性と学習への影響(例) |
|---|---|
| ADHD(注意欠如・多動症) | 集中力が続きにくい、じっとしていられない、忘れ物が多いなどの特性から、学習に集中し続けることが難しい場合があります。 |
| SLD(限局性学習障害) | 知的な遅れはないものの、「読む」「書く」「計算する」など、特定の能力を習得したり使ったりすることに著しい困難さがある状態です。 |
| ASD(自閉スペクトラム症) | 特定のこだわりが強い、感覚が過敏(例:特定の音や光が苦手)、コミュニケーションが苦手などの特性が、学校の教室など集団での学習環境への適応を難しくする場合があります。 |
発達障害やグレーゾーンが疑われるサイン
子供が勉強できない理由が発達障害やグレーゾーンかもしれないと疑われるサインとして、本人の努力や工夫だけではカバーしきれない、以下のような特定の困難さが挙げられます。
- 集中力が極端に続かない、忘れ物やケアレスミスが(年齢に比べて)非常に多い(ADHDの傾向)
- 教科書の音読がたどたどしい、文字や行を飛ばして読んでしまう(読字障害の傾向)
- 板書をノートに写すのに極端に時間がかかる、文字の形や大きさが整わない(書字表出障害の傾向)
- 簡単な計算が暗算できない、筆算で位を間違えやすい(算数障害の傾向)
これらのサインが複数当てはまるからといって、必ずしも発達障害と診断されるわけではなく、特性の強弱によって「グレーゾーン」と呼ばれる場合もあります。



努力不足と決めつけず、気になるサインは専門家への相談も大切です。
気になる場合は学校や専門機関への相談を検討する
子供が勉強できない理由として発達障害の特性が気になる場合、保護者だけで抱え込まず、学校や専門機関へ相談を検討することが大切です。
まずは、学校での様子や学習面の困難さについて、担任の先生やスクールカウンセラーに相談してみましょう。より専門的な相談先としては、以下のような機関があります。
- 市町村の保健センターや子育て支援センター
- 発達障害者支援センター
- 児童相談所
- 医療機関(小児科、児童精神科など)
専門機関に相談することで、お子さまの特性に合った学習方法や環境調整のアドバイスが受けられ、適切なサポートにつなげることができます。
子供が勉強せずイライラする・疲れた時の親のストレス対処法
お子さまが勉強しないと、親も「なぜやってくれないの?」とイライラしたり、サポートに疲れたりするものです。しかし、親がストレスを抱えすぎると、かえって悪循環になります。
ここでは、親御さま自身の心を守るための対処法を解説します。
対処法①「子供を愛せない」と自分を責めない
子供が勉強せずイライラする・疲れた時の親のストレス対処法1つ目は「子供を愛せない」「ダメな親だ」と自分を責めないことです。
イライラしてしまうのは、それだけお子さまのことを真剣に心配し、将来を考えている証拠でもあります。一時的にネガティブな感情を抱いてしまうのは、人間として自然なことです。
「こんなことでイライラするなんて」と自分を責めると、さらにストレスが溜まり、お子さまへの接し方も厳しくなってしまう悪循環に陥ります。
まずは「イライラしても当然だ」と自分の感情を受け入れましょう。
対処法②親も完璧を目指さずハードルを下げる
子供が勉強せずイライラする・疲れた時の対処法として、親も完璧を目指さずハードルを下げることが挙げられます。
「毎日必ず1時間勉強させる」「親がスケジュールを完璧に管理する」など、高い理想や目標を設定すると、できなかったときに親自身のストレスが増大します。
「今日は宿題が1ページできたら十分」「とりあえず机に向かえたらOK」など、親が期待するハードルを少し下げてみてください。
親の心に余裕が生まれることが、結果としてお子さまへのプレッシャーを減らすことにもつながります。
対処法③子供と一時的に距離を置き冷静になる
子供が勉強せずイライラが募る時は、子供と一時的に距離を置き冷静になる対処法も有効です。感情的になって「勉強しなさい!」と叱りつけても、お子さまは反発するか萎縮するだけで、根本的な解決にはなりません。
イライラがピークに達しそうだと感じたら、深呼吸をする、別の部屋へ移動するなど、意識的に物理的・心理的な距離を置きましょう。
親が一度冷静になることで、「なぜこの子は今やれないのか」と別の視点で考える余裕が生まれます。
対処法④親自身のストレスケアを優先する
子供が勉強せずイライラする・疲れた時の対処法4つ目は、親自身のストレスケアを優先することです。親のイライラや不安は、言葉にしなくてもお子さまに伝染します。
お子さまの学習環境を整える前に、まずは親御さま自身の心が健康であることが大切です。以下のように、意識的にリフレッシュする時間を確保しましょう。
- 好きな音楽を聴く、温かい飲み物を飲む
- 10分だけでも一人で散歩する
- 友人やパートナーに話を聞いてもらう
親が笑顔でいられる時間を増やすことが、結果的にお子さまが安心して勉強に取り組める家庭環境につながります。
対処法⑤塾や家庭教師など第三者(プロ)を頼る
子供が勉強せずイライラする・疲れた時は、塾や家庭教師など第三者(プロ)を頼るのも対処法の一つです。親子関係が近すぎると、勉強を教える際にどうしても感情的になりがちです。
「勉強しなさい」「なんでわからないの?」というやり取りが続き、親子の信頼関係が悪化する前に、学習のサポートはプロに任せる選択も有効です。
親は勉強の管理から解放され、精神的なサポートに集中できます。家庭教師や塾の先生という第三者のほうが、お子さまも素直に話を聞くケースも多く、親のストレス軽減にも直結します。



親子だからこそ感情的になりがちです。プロを頼るのも良い選択ですよ。
勉強しない子供におすすめの学習塾3選
勉強しないお子さまのやる気を引き出すには、学習環境や指導方法がお子さまに合っていることが重要です。ここでは、勉強への苦手意識があるお子さまや、学習習慣が身についていないお子さまへのサポートに定評がある学習塾を3社厳選して紹介します。
各塾の指導方針やサポート体制、特徴を比較し、お子さまに最適な塾を見つけるための参考にしてください。
森塾


出典:morijuku.com
| 対象年齢 | 中学生・高校生・既卒生 |
|---|---|
| 授業形態 | 先生1人に生徒2人までの個別指導 |
| 入会金 | 20,000円 |
| 料金 | 小学生 5,880 円〜/30分 中学生 1 1,700円/30分 高校生 1 5,300円/30分 |
| 無料体験 | ◯ |
| 講師 | 大学生講師中心(一部社会人) |
| 特徴 | ・講師変更制度あり ・毎回の確認テストと無料補講「特訓部屋」 ・成績保証制度(1科目20点アップ保証) ・学校授業や定期テストに直結したカリキュラム |
勉強しない子供におすすめの学習塾1つ目は、森塾です。森塾は、先生1人に生徒2人までの個別指導で、「わかる」まで丁寧に教え、「できる」まで繰り返す指導法が特徴です。
また、生徒のやる気を引き出す「ほめる指導」を徹底しており、勉強への苦手意識をなくし、自信を持たせます。勉強のやり方がわからず自信を失っているお子さまや、ほめられて伸びるタイプのお子さまにおすすめです。
\ 無料体験・お問い合わせはこちら /
明光義塾


| 対象年齢 | 小学生・中学生・高校生 |
|---|---|
| 授業形態 | 講師1名に対し生徒3名程度の個別指導 |
| 入会金 | 11,000円(税込) ※キャンペーンにより無料になる場合あり |
| 料金 | 学年、受講教科、週の授業回数、学習プランに応じて個別に設定 |
| 無料体験 | ◯ |
| 講師 | 大学生、大学院生が中心。採用時に学力試験や面接を実施。 |
| 特徴 | ・一人ひとりに合わせたオーダーメイドの学習プランを作成 ・「わかる・話す・身につく」を重視した対話型の授業(MEIKO式コーチング) ・全国No.1の教室数で、豊富な受験情報を提供 ・定期的なカウンセリングで生徒・保護者をサポート |
勉強しない子供におすすめの学習塾2つ目は、明光義塾です。明光義塾は、生徒との「対話」を重視したMEIKO式コーチングで、生徒自身が「わかった」ことを言葉にするプロセスを大切にしています。
生徒一人ひとりに合わせたオーダーメイドの学習プランと「振り返りノート」で、わかったつもりを防ぎ、学習習慣の定着をサポートします。
勉強のやり方がわからないお子さまや、自主的に考える力を養いたいお子さまにおすすめです。
\ 資料請求・無料体験はこちら /
そら塾


出典:sorajuku.jp
| 対象年齢 | 小 3 ~ 高 3 |
|---|---|
| 授業形態 | オンライン個別 |
| 入会金 | 11,000 円 |
| 料金 | 小学生 5,800 円/60分 中学生 7,500 円/60分 高校生 8,800 円/60分 |
| 無料体験 | ◯ |
| 講師 | 難関大生・社会人 |
| 特徴 | ・入会時以降の追加費用ゼロ ・定期テスト~受験まで全科目対応 ・保護者用ダッシュボードで進捗可視化 |
勉強しない子供におすすめの学習塾3つ目は、そら塾です。そら塾は、AIを活用した効率的な学習プランと、講師によるオンライン個別指導を組み合わせたハイブリッドな指導が特徴です。
自宅で受講できるため、部活や習い事で忙しいお子さまでも、リラックスした環境で学習に取り組めます。共働きで塾への送迎が難しいご家庭や、効率的に学習習慣を身につけたいお子さまにおすすめです。
\ 無料体験はこちら /
子供が勉強しない理由に関するよくある質問(FAQ)
子供が勉強しない理由に関するよくある質問と回答をまとめました。お子さまへの関わり方についての疑問や不安を解消しましょう。
勉強しない子供に絶対言ってはいけない言葉は?
勉強しない子供に絶対言ってはいけない言葉は、子供の個性や人格、存在自体を否定する言葉や、他人と比較する言葉です。
たとえば、「なんでできないの?」「本当にダメな子ね」といった人格否定や、「〇〇ちゃんはできるのに」といった比較、「勉強しないならゲーム捨てるよ」といった脅し文句が挙げられます。
これらの言葉は、子供の自己肯定感を著しく下げ、親への不信感を抱かせます。勉強への意欲をさらに失わせる逆効果となるため、避けるべきです。
子供にストレスが溜まっているサインはある?
子供にストレスが溜まっているサインとして、以前と比べて以下のような行動や態度の変化が見られる場合は注意が必要です。
- イライラしやすくなった、口数が減った、急に泣き出すなど、感情の起伏が激しくなる
- 「お腹が痛い」「頭が痛い」など、体調不良を訴える回数が増える
- 食欲が極端に増えたり減ったりする
- 夜なかなか寝付けない、または寝すぎて起きられない
- 爪を噛む、髪を抜くなどの癖が出る
- 好きだった趣味(ゲームなど)に興味を示さなくなる
これらは勉強のプレッシャーや学校生活での悩みなどが原因の可能性があります。
子どもをダメにする父親の3つの特徴は?
子どものやる気を削ぎ、成長の妨げとなり得る父親の特徴として、主に「無関心(放置)」「過干渉(支配的)」「一貫性のない態度(気分屋)」の3つが挙げられます。
| 特徴 | 具体的な内容(例) |
|---|---|
| 無関心(放置) | 育児や勉強を母親に丸投げし、子供の活動や悩みに一切関心を示さない。 |
| 過干渉(支配的) | 父親の価値観を一方的に押し付け、子供の意見や選択を認めず、高圧的にコントロールしようとする。 |
| 一貫性のない態度(気分屋) | その日の機嫌によって言うことや叱る基準が変わり、母親と意見が食い違うことが多い。 |
これらの関わり方は、子供の自主性や自己肯定感の育成を妨げ、精神的な安定や学習意欲に悪影響を与える可能性があります。
まとめ
子供が勉強しない理由や、親のNG行動、今すぐできるサポート術について解説しました。「子供が勉強しない理由は100%親にある」とすべてを抱え込む必要はありませんが、親の関わり方が子供の意欲に影響するのは事実です。
子供が勉強しない理由は、親のNG行動以外にも、子供自身の心理状態や環境、勉強方法がわからないなど様々です。
まずは頭ごなしに「勉強しなさい」と叱るのをやめ、子供の気持ちに寄り添い、結果よりも努力の過程を認めてあげることが大切です。
親子関係だけで勉強のサポートが難しいと感じたら、親のストレスケアのためにも、塾や家庭教師など第三者のプロを頼ることも検討しましょう。
この記事で紹介したサポート術を参考に、お子さまの自己肯定感を高め、勉強へのやる気を引き出す関わり方を試してみてください。

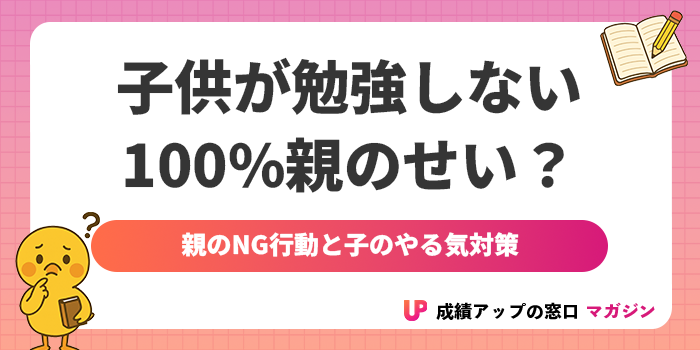

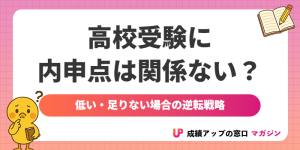
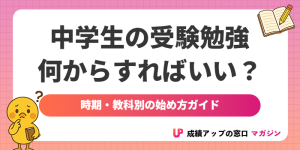
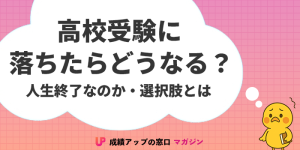
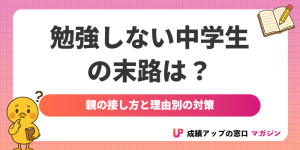
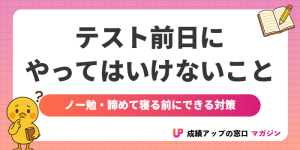
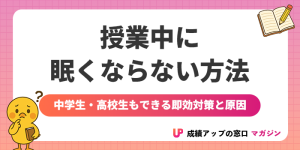


コメント