 ひよこ生徒
ひよこ生徒高校受験って内申点関係ないって本当?
内申点が低くて志望校を諦めるしかないのかな・・・
内申点が足りなくても逆転合格できる戦略が知りたい!
「高校受験は内申点が関係ない」と聞いたことがある人もいるかもしれませんが、結論として、ほとんどの高校受験で内申点は関係あります。
しかし、内申点が低いからといって、志望校を諦める必要はまったくありません。内申点の影響が小さい入試方式を選んだり、当日点で逆転したりする戦略は十分に可能です。
この記事では、高校受験における内申点の扱いや、内申点が足りない場合に逆転合格するための具体的な戦略について詳しく解説していきます。



内申点が足りないと不安に思っている人のほとんどは、正しい戦略を知らないだけです。
内申点の影響が小さい受験方法や、当日点で逆転する方法を知れば、合格の可能性は大きく広がりますよ。
\2026年最新!/
高校受験向け学習塾おすすめTOP3
高校受験向けの学習塾を徹底比較し、厳選したおすすめ3社は以下のとおりです。すべて無料体験が可能なため、自分に合うサービスを見つけるために積極的に活用しましょう。


・志望校合格から逆算したオーダーメイドの年間学習計画を作成
・週1回のコーチングで学習の進捗管理と勉強法を指導
・「スタディサプリ」の映像授業が見放題で、参考書学習と組み合わせる
・受験科目全てを対象に、総合点を最大化するための戦略的な指導


・通塾生の94.5%が成績アップ
・講師変更制度あり
・毎回の確認テストと無料補講「特訓部屋」
・成績保証制度(1科目20点アップ保証)
・学校授業や定期テストに直結したカリキュラム


・一人ひとりに合わせたオーダーメイドの学習プランを作成
・「わかる・話す・身につく」を重視した対話型の授業
・全国No.1の教室数で、豊富な受験情報を提供
・定期的なカウンセリングで生徒・保護者をサポート
- 高校受験で内申点が関係あるかどうかの結論
- 内申点が関係ない・影響が小さい高校や入試方式
- 内申点が足りない中学生が逆転合格するための戦略
- 今からでも内申点を1点でも上げる具体的な方法
高校受験で内申点は関係ない?
高校受験で内申点がどのように関係するのか、その仕組みや影響度を正しく理解することが、合格への第一歩です。ここでは、内申点と高校受験の関係性について、基本から解説します。
ひとつずつ見ていきましょう。
結論:ほとんどの高校受験で内申点は関係ある
「高校受験で内申点は関係ないのでは?」と疑問に思うかもしれませんが、結論として、ほとんどの高校受験で内申点は関係あります。
公立高校はもちろん、私立高校でも推薦入試や併願優遇制度を利用する場合は、出願基準として内申点が設定されているケースが一般的です。
内申点が全く関係ないのは、一部の私立高校が実施するオープン入試や、当日点(学力検査)のみで合否を判定する学校に限られます。
内申点が合否にどの程度影響するかは学校や入試方式によって異なりますが、多くの受験生にとって内申点は無視できない要素です。
高校受験で「内申点は関係ない」と言われる理由
ほとんどの高校受験で内申点が関係あるにもかかわらず「内申点は関係ない」と言われる理由として、主に一部の私立高校が実施する「一般入試(オープン入試)」を指している場合が多いです。
オープン入試とは、内申点に関係なく、当日の学力検査の点数のみで合否を決める入試方式です。内申点が足りずに推薦や併願優遇が取れない生徒でも、当日点さえ取れれば合格できるチャンスがあるため、「内申点は関係ない」というイメージにつながっています。
ただし、すべての私立高校がこの方式を採用しているわけではないため、注意が必要です。
公立高校と私立高校での内申点の扱いの違い
高校受験における内申点の扱いは、公立高校と私立高校で違いがあります。公立高校の一般入試では、ほとんどの都道府県で「内申点(調査書点)」と「当日点(学力検査点)」を合計して合否が判定されます。
内申点と当日点の比率は自治体によって異なり(例:7:3、5:5、3:7など)、内申点が合否に直結します。一方、私立高校は学校ごとに方針が大きく異なります。
推薦入試や併願優遇では内申点の基準を設けている場合がほとんどですが、一般入試では「当日点のみで判定する」「内申点を参考程度に見る」など、内申点の影響が小さい、あるいは全く関係ない学校も存在します。
一般入試と推薦入試での影響度の違い
高校受験で内申点が関係あるといっても、一般入試と推薦入試では影響度が異なります。推薦入試(単願推薦・併願優遇など)では、内申点の影響度は非常に大きいです。
「9教科で合計〇〇以上」や「5教科で〇〇以上」といった出願基準が設けられており、その基準を満たさなければ受験することすらできません。
一方、一般入試では、推薦入試ほど内申点が絶対的な基準になることは少ないです。公立高校では当日点との合計で評価され、私立高校では前述のとおり当日点重視の学校も多いため、推薦入試に比べれば内申点の影響度は下がるといえます。
内申点が関係ない・影響が小さい高校や入試方式
「高校受験で内申点が足りないかも…」と不安な人も、進学を諦める必要はありません。内申点の影響が小さい、あるいは全く関係ない高校や入試方式も存在します。
ここでは、内申点が関係ない、または影響が小さい高校や入試方式の選択肢を4つ紹介します。
ひとつずつ見ていきましょう。
私立高校の一般入試・オープン入試
内申点が関係ない・影響が小さい高校や入試方式の1つ目は、私立高校の一般入試・オープン入試です。私立高校の一般入試のなかには、内申点を合否判定に含めず、当日の学力検査の点数のみで合否を決める「オープン入試」を採用している学校があります。
推薦入試や併願優遇で必要な内申点の基準に届かない場合でも、オープン入試であれば当日のテストで高得点を取ることで逆転合格が可能です。
「内申点は関係ない」環境で実力勝負をしたい人に適した方式といえます。ただし、すべての私立高校が実施しているわけではないため、募集要項の確認が必須です。
当日点(学力検査)の比率が高い公立高校
内申点が関係ない・影響が小さい高校として、当日点(学力検査)の比率が高い公立高校も挙げられます。多くの公立高校入試は「内申点」と「当日点」を合計して合否を決めますが、その比率は都道府県や学校によって異なります。
たとえば、「内申点4:当日点6」や「内申点3:当日点7」のように、当日点の比率が高い高校では、内申点の不足分を当日の学力検査でカバーしやすくなります。
内申点に自信がなくても、学力検査で高得点を取れば合格の可能性は十分あります。志望校を選ぶ際は、各自治体の教育委員会が公表している選抜基準を確認し、当日点重視の高校を探してみましょう。
通信制高校・定時制高校
内申点が関係ない・影響が小さい高校には、通信制高校や定時制高校もあります。これらの高校の入試は、学力検査を課さず「書類選考(内申書含む)」「面接」「作文」などで合否を判定するケースが多いです。
内申書(調査書)の提出は必要ですが、全日制高校の入試ほど評定(内申点)が厳しく合否に影響することは少なく、生徒の学習意欲や面接での態度が重視される傾向にあります。
中学時代の内申点に不安がある人や、自分のペースで学びたい人にとって、有力な選択肢となるでしょう。
チャレンジスクール・エンカレッジスクール
内申点が関係ない・影響が小さい高校の選択肢として、チャレンジスクールやエンカレッジスクールも挙げられます。
これらは主に東京都や大阪府などに設置されている学校で、不登校を経験した生徒や、基礎から学び直したい生徒を積極的に受け入れています。
入試の特徴は、内申書(調査書)を点数化せず、「面接」「作文」「実技検査」などで生徒の意欲や熱意を多角的に評価する点です。
中学時代の内申点に関係なく、高校で頑張りたいという気持ちを評価してくれるため、内申点に自信がない生徒も挑戦しやすい学校です。
なぜ高校受験で内申点(調査書)が重視されるのか
高校受験で内申点(調査書)が重視されるのには、合否判定や入試制度の根幹に関わる、はっきりとした理由があります。
ここでは、高校受験で内申点が重視される主な理由を4つ解説します。
ひとつずつ見ていきましょう。
内申点が重視される理由①公立高校の合否判定で「内申点+当日点」が使われるから
高校受験で内申点が重視される理由の1つ目は、公立高校の一般入試は「内申点(調査書点)+当日点(学力検査点)」の合計点で合否が判定されるからです。
内申点が合否判定に含まれる理由は、ペーパーテストだけでは測れない中学3年間の学習成果や取り組みを評価に加えるためです。
当日点(学力検査)の点数がどんなに高くても、内申点が極端に低ければ合計点で及ばず不合格になる可能性があります。
逆に、内申点が高ければ、当日点のビハインドをカバーできることもあります。このように、内申点は合否に直接影響するため、公立高校受験において非常に重視されます。
内申点が重視される理由②私立高校の推薦・併願優遇の基準になるから
高校受験で内申点が重視される理由として、私立高校の推薦入試や併願優遇の出願基準になる点も挙げられます。多くの私立高校では、推薦入試や併願優遇(公立高校が第一志望の場合に、合格を確約または優遇してもらえる制度)を利用するための条件として、「9教科の内申点合計が〇〇以上」といった基準を設けています。
この基準を満たさなければ、推薦や併願優遇で受験することができません。私立高校側にとっては、内申点を基準にすることで、入学後に学業についていける基礎学力や、真面目な学習態度を持つ生徒を確保する狙いがあります。
内申点が重視される理由③中学3年間の学校生活を総合的に評価するため
高校受験で内申点が重視される理由には、中学3年間の学校生活を総合的に評価する目的もあります。高校側は、当日の学力検査の点数だけではわからない、生徒の日常的な学習態度や生活態度を知りたいと考えています。
調査書では、内申点(評定)だけでなく、以下のような記録も含めて評価されます。
- 出欠席の記録
- 特別活動の記録(委員会活動や部活動など)
- 行動の記録
これらは、生徒が中学生活で培ってきた責任感や協調性、主体性などを判断する材料となります。3年間の積み重ねを評価するため、内申点(調査書)は重視されるのです。
内申点が重視される理由④面接試験での質問の参考資料になるため
高校受験で内申点が重視される理由の4つ目は、面接試験での質問の参考資料になるためです。推薦入試や一部の一般入試で実施される面接では、面接官の手元にある調査書(内申書)の内容に基づいて質問がされます。
たとえば面接官は、以下のような具体的な質問が可能です。
- 「調査書を見ると、3年間〇〇係を続けたようですが、どのようなことを学びましたか?」
- 「〇〇(教科)の成績が特に素晴らしいですが、どのような努力をしましたか?」
このように、調査書は生徒の個性や長所、学習意欲などを深掘りし、多角的に評価するための基礎資料として活用されます。
今さら聞けない高校受験における「内申点」の仕組みとは?
高校受験で内申点が重要だとわかっていても、その仕組みは複雑でわかりにくいものです。ここでは、内申点(調査書)と通知表(評定)の関係や、成績がいつから影響するのか、どのように評価が決まるのかなど、内申点の基本的な仕組みを解説します。
- 内申点とは?調査書(内申書)と通知表(評定)の関係
- 内申点はいつからいつまでの成績が影響する?
- 要注意「観点別評価」で評定が決まる3つのポイント
- 内申点の計算方法は都道府県によって全く違う
- 実技4教科(副教科)の評価は2倍になる?
ひとつずつ見ていきましょう。
高校受験の内申点とは?調査書(内申書)と通知表(評定)の関係
高校受験における内申点とは、一般的に「調査書(内申書)」に記載される「各教科の評定(通知表の5段階評価など)」を点数化したものを指します。
調査書(内申書)は、中学校が作成し、高校に提出する公式な書類です。調査書には評定以外にも、以下のような内容が記載されます。
- 出欠席の記録(欠席日数など)
- 特別活動の記録(委員会活動、部活動など)
- 行動の記録
生徒が学期ごとにもらう「通知表」に記載される評定(例:1~5)が、調査書に記載される内申点の元になります。つまり、「通知表の評定」を、各都道府県や学校のルールに基づいて計算したものが「高校受験で使われる内申点」となります。
高校受験内申点はいつからいつまでの成績が影響する?
高校受験における内申点において、いつの成績が影響するかは、受験する都道府県(公立高校)や学校(私立高校)によって大きく異なります。
たとえば、公立高校の場合、以下のように地域によってさまざまです。
- 中学3年間の評定すべてが対象になる地域(例:大阪府、兵庫県)
- 中学2年生と3年生の評定が対象になる地域(例:神奈川県)
- 中学3年生の評定のみが対象になる地域(例:東京都)
- 中学1年:2年:3年で比重が異なる地域(例:埼玉県 1:1:2)
※最新の情報は各自治体の公表内容をご確認ください。
私立高校の場合は、「中学3年生の2学期(または前期)の成績」を推薦・併願優遇の基準にすることが多いです。中学1年生の成績から評価対象になる可能性もあるため、早期から対策することが望ましいです。
要注意「観点別評価」で評定が決まる3つのポイント
高校受験の内申点の仕組みを理解するうえで、評定(通知表の5段階評価)がどのように決まるかを知ることは不可欠です。
2021年度から中学校で全面実施された新学習指導要領により、評定は「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の3つの観点別評価に基づいて決定されてます。
単に定期テストの点数だけ良ければ「5」が取れるわけではなく、以下の3つの要素が総合的に評価されます。
- 知識・技能|定期テストや小テストの点数
- 思考・判断・表現|レポートや発表
- 主体的に学習に取り組む態度|授業態度や提出物
各要素を以降で詳しく解説します。
評定が決まるポイント①知識・技能|定期テストや小テストの点数
「観点別評価」で評定が決まるポイントの1つ目は「知識・技能」です。これは、ペーパーテストの結果が大きく影響する項目です。
定期テストや小テストで、基礎的な知識(英単語、漢字、公式など)が身についているか、基本的な技能(計算、英文法など)を習得できているかが評価されます。
評定を上げるためには、まず定期テストなどで高得点を取ることが基本となります。
評定が決まるポイント②思考・判断・表現|レポートや発表
「観点別評価」で評定が決まるポイントとして「思考・判断・表現」も挙げられます。これは、知識や技能を活用して、課題を解決したり自分の考えを表現したりする力が評価されます。
たとえば、以下のような場面での取り組みが評価対象です。
- 定期テストの応用問題や記述問題
- 授業中のグループディスカッションや発表
- レポートや作品の提出
これらの場面で、自分の考えを論理的に組み立てたり、わかりやすく伝えたりする力が求められます。
評定が決まるポイント③主体的に学習に取り組む態度|授業態度や提出物
「観点別評価」で評定が決まる3つ目のポイントは「主体的に学習に取り組む態度」です。これは、授業への積極的な参加や提出物への取り組みが評価される項目で、内申点に大きく影響します。
具体的には、以下のような行動が評価されます。
- 授業中の積極的な発言や挙手
- ノートをていねいにとる
- 提出物(宿題、レポート)の期限を守り、質の高い内容を提出する
- 忘れ物をしない
定期テストの点数が良くても、この「主体的に学習に取り組む態度」の評価が低いと、評定が「4」や「3」に下がる可能性があるため注意が必要です。



テストの点数以外の努力も、しっかり評価されますよ。
高校受験内申点の計算方法は都道府県によって全く違う
高校受験における内申点の仕組みとして、内申点の計算方法が都道府県によって全く違う点も理解しておきましょう。
内申点(調査書点)の計算方法は、受験する公立高校がある都道府県によって全く異なります。たとえば、以下のように計算方法や満点が異なります。
| 都道府県(例) | 対象学年 | 教科間の比重(例) | 満点(例) |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 中学3年生のみ | 主要5教科:1倍、実技4教科:2倍 | 65点満点 |
| 神奈川県 | 中学2年生、中学3年生 | 中2(9教科):1倍、中3(9教科):2倍 | 135点満点 |
| 埼玉県 | 中学1年~3年 | 中1:中2:中3 = 1:1:2(学校により異なる場合あり) | – |
※最新の情報は各自治体の公表内容をご確認ください。
このように、どの学年の成績が、どの教科の比重で計算されるかが異なります。自分の住んでいる地域の計算方法を、各都道府県の教育委員会のホームページなどで必ず確認する必要があります。



お住まいの地域の計算方法を、まず確認しましょう。
実技4教科(副教科)の評価は2倍になる?
高校受験における内申点の仕組みに関して「実技4教科(副教科)の評価は2倍になる」と聞いたことがある人もいるかもしれません。
結論として、これは東京都など一部の自治体で採用されている計算方法であり、すべての都道府県に当てはまるわけではありません。
実技4教科(音楽、美術、保健体育、技術・家庭)の評価を、主要5教科(国語、数学、英語、理科、社会)よりも重視(例:1.5倍や2倍)する計算方法を採用している自治体は確かに存在します。
実技4教科を重視する理由には、実技教科の努力も公平に評価しようとする狙いがあります。ただし、5教科と実技4教科を平等に(すべて1倍で)扱う自治体も多くあります。
副教科が苦手だと不利になるかどうかは、自分の受験する都道府県の計算ルール次第です。
高校受験において内申点制度が「バカバカしい」「意味不明」と言われる理由
高校受験の内申点制度は、その仕組みの複雑さや公平性への疑問から、ときに「バカバカしい」「意味不明」といった批判を受けることもあります。
ここでは、なぜ内申点制度がそのように言われてしまうのか、代表的な4つの理由を解説します。
ひとつずつ見ていきましょう。
理由①評価基準が曖昧で先生の「ひいき」を感じる
高校受験の内申点制度が「バカバカしい」と言われる理由の1つ目は、評価基準が曖昧で、先生の「ひいき」があるように感じられる点です。
とくに「主体的に学習に取り組む態度」の評価は、授業中の挙手回数や発言内容、ノートの取り方など、数値化しにくい部分が対象となります。
生徒や保護者から見ると、評価の具体的な根拠が見えにくいため「先生のお気に入りかどうか」で評定が左右されているのではないか、という不信感につながりやすいです。
この主観的に見える評価基準が、理解しづらいと感じさせる一因となっています。
理由②定期テストの点数が良くても評定が低い
高校受験の内申点制度が「バカバカしい」と言われる理由として、定期テストの点数が良くても評定が低い場合がある点も挙げられます。
内申点の評定は、以下の3つの観点で総合的に決まります。
- 定期テストの点数(知識・技能)
- レポートや発表(思考・判断・表現)
- 授業態度や提出物(主体的に学習に取り組む態度)
そのため、テストで高得点を取っていても、提出物が出ていなかったり、授業態度が悪かったりすると、評定が「3」や「4」になることも珍しくありません。
テストの点数という客観的な結果がそのまま反映されない点が「不満」と感じられてしまう要因となっています。



テスト頑張ったのに、なんで評定が低いんですか?



テスト以外の「態度」や「提出物」も見られているんですよ。
理由③学校間のレベル差が考慮されず不公平に感じる
高校受験の内申点制度が「バカバカしい」と言われる理由には、学校間のレベル差が考慮されないことへの不公平感もあります。
たとえば、生徒の学力レベルが非常に高い中学校で評定「4」を取るのと、平均的な学力の中学校で「4」を取るのとでは、その難易度は異なります。
しかし、高校受験の内申点としては、どちらも同じ「4」として扱われるのが一般的です(一部、地域や学校で補正がある場合を除く)。
学力競争が激しい中学校に通う生徒ほど、「内申点が取りにくい」と感じ、学校間のレベル差が考慮されない制度を不公平だと感じやすくなります。
理由④副教科が苦手だと全体の評定が下がりやすい
内申点制度が「バカバカしい」と言われる理由の4つ目は、副教科(実技4教科)が苦手だと全体の評定が下がりやすい点です。
音楽、美術、保健体育、技術・家庭といった副教科は、個人の才能や得意・不得意が大きく影響することがあります。
主要5教科の成績が良くても、特定の副教科が極端に苦手なために内申点全体の足を引っ張ってしまうケースは少なくありません。
とくに、東京都のように副教科の評定を2倍にして計算するような地域では、その影響は甚大です。学力検査に関係ない教科のせいで志望校の選択肢が狭まることが「意味不明」だという不満につながっています。
内申が足りない中学生が高校受験で逆転合格するための戦略
内申点が足りないから高校受験に合格できないと落ち込むのはまだ早いです。内申点のビハインドをカバーし、高校受験で逆転合格を果たすための戦略は存在します。
ここでは、内申点が足りない中学生が実践すべき5つの戦略を紹介します。
- 当日点(学力検査)重視の高校を志望校にする
- 私立高校の一般入試・オープン入試に切り替える
- 学力検査で高得点を取る勉強法に集中する
- 面接や自己PRで学習意欲や熱意を伝える
- 安全校(滑り止め)とチャレンジ校を賢く併願する
ひとつずつ見ていきましょう。
戦略①当日点(学力検査)重視の高校を志望校にする
内申点が足りない中学生が高校受験で逆転合格するための戦略の1つ目は、当日点(学力検査)重視の高校を志望校にすることです。
公立高校の入試では、「内申点」と「当日点」の比率が都道府県や学校によって定められています。「内申点3:当日点7」や「内申点4:当日点6」のように、当日点の比率が高い高校を選べば、内申点の不足分を当日のテスト結果でカバーしやすくなります。
自分の学力と内申点を冷静に分析し、どのくらいの点数を当日取れば逆転できるのかをシミュレーションしてみましょう。
各都道府県の教育委員会のホームページなどで選抜基準を確認し、当日点重視の高校をリストアップすることが、逆転合格への第一歩となります。



内申点が足りなくても、当日点重視の高校なら逆転可能です。
戦略②私立高校の一般入試・オープン入試に切り替える
内申点が足りない中学生が高校受験で逆転合格するための戦略として、私立高校の一般入試・オープン入試に切り替える方法も挙げられます。
私立高校のなかには、推薦や併願優遇とは別に、当日の学力検査の点数のみで合否を判定する「一般入試(オープン入試)」を実施している学校が多くあります。
この方式であれば、中学時代の内申点は合否に関係ありません。公立高校の内申点基準に届かず悩んでいる場合でも、私立高校のオープン入試に照準を合わせれば、実力勝負での合格が可能です。
内申点を気にせず、自分の得意科目を活かして高得点を狙える学校を探してみましょう。
戦略③学力検査で高得点を取る勉強法に集中する
内申点が足りない中学生が高校受験で逆転合格するには、学力検査で高得点を取る勉強法に集中することも戦略のひとつです。
内申点が足りない事実は変えられないため、その状況で逆転合格を狙うには、当日点でライバルをごぼう抜きにするしかありません。
まずは以下のステップで勉強計画を立てましょう。
- 志望校の過去問を徹底的に分析し、出題傾向や難易度を把握する。
- 自分の苦手分野を潰す。
- 得点源となる得意分野をさらに伸ばす。
内申点対策にかけていた時間をすべて当日点の対策に振り分ける覚悟で、1点でも多く得点するための勉強法に集中することが求められます。
戦略④面接や自己PRで学習意欲や熱意を伝える
内申点が足りない中学生が高校受験で逆転合格するための戦略4つ目は、面接や自己PRで学習意欲や熱意を伝えることです。
とくに、当日点重視の高校や、通信制・定時制高校、チャレンジスクールなどの入試では、面接や自己PRが課される場合があります。
内申点が低い理由を正直に反省しつつも、それを上回る「高校入学後にいかに頑張りたいか」という前向きな意欲や熱意を、自分の言葉で具体的に伝えることができれば、評価を挽回できる可能性があります。
「内申点は足りないかもしれないが、この生徒は入学後に伸びそうだ」と面接官に感じさせることが逆転の鍵となります。
戦略⑤安全校(滑り止め)とチャレンジ校を賢く併願する
内申点が足りない中学生が高校受験で逆転合格するための戦略として、安全校(滑り止め)とチャレンジ校を賢く併願することも挙げられます。
内申点が足りない状況で第一志望(チャレンジ校)に特攻するのは非常にリスクが高いです。まずは、自分の内申点や学力でも確実に合格が見込める「安全校(滑り止め)」を確保することが精神的な安定につながります。
そのうえで、当日点重視の公立高校や、オープン入試を実施している私立高校を「チャレンジ校」として受験する戦略を立てましょう。
安全校が確保できていれば、「落ちても行くところがある」という安心感から、チャレンジ校の入試本番でもリラックスして実力を発揮しやすくなります。
今からでも間に合う?高校受験に向けて内申点を1点でも上げる方法
「もう内申点は変えられない」と諦めるのは早いです。高校受験に向けて、中学3年生の今からでも内申点を1点でも上げるためにできる具体的な対策はあります。
ここでは、内申点を1点でも上げるための5つの方法を紹介します。
- 定期テストや小テストで高得点を目指す
- 提出物は期限を守り質にもこだわる
- 授業中は積極的に手を挙げる・ノートを丁寧にとる
- 英検・漢検・数検などの資格取得(学校による)
- 学級活動や委員会活動に真面目に参加する
ひとつずつ見ていきましょう。
対策①定期テストや小テストで高得点を目指す
高校受験に向けて内申点を1点でも上げる方法の1つ目は、定期テストや小テストで高得点を目指すことです。なぜなら、評定(内申点)を決める3観点のうち「知識・技能」は、ペーパーテストの点数が最も大きく影響するためです。
すでに終わったテストの結果は変えられませんが、これから行われる学年末テスト(中3の2学期または後期)で高得点を取れば、その学期の評定アップに直結します。
主要5教科はもちろん、副教科のテスト(ペーパーまたは実技)も手を抜かず、1点でも多く点数を稼ぐ努力が内申点アップにつながります。
対策②提出物は期限を守り質にもこだわる
高校受験に向けて内申点を1点でも上げる方法として、提出物は期限を守り質にもこだわる点も挙げられます。これは、評定の3観点のうち「主体的に学習に取り組む態度」の評価に直結するからです。
期限を守るのは当然として、内容が雑だったり、空欄が多かったりすると評価は下がります。逆に、ていねいな字で書き、調べ学習なども自主的に補足するなど、質の高い提出物を心がければ、先生からの評価は上がります。
テストの点数が多少悪くても、提出物で意欲を示すことで評定が救われるケースもあります。



提出物は「主体的に学習に取り組む態度」として重要ですよ。
対策③授業中は積極的に手を挙げる・ノートを丁寧にとる
高校受験に向けて内申点を1点でも上げるには、授業中は積極的に手を挙げる・ノートをていねいにとることも対策になります。
これも「主体的に学習に取り組む態度」の評価を高めるためです。内気な性格で発言が苦手な人も、先生の話にうなずいたり、ていねいにノートを取ったりする姿は「授業に真面目に参加している」証拠として評価されます。
先生は意外と生徒の様子をよく見ています。「この教科を頑張りたい」という意欲を行動で示すことが、内申点アップにつながる最後のひと押しとなります。
対策④英検・漢検・数検などの資格取得(学校による)
高校受験に向けて内申点を1点でも上げる方法の4つ目は、英検・漢検・数検などの資格取得です。ただし、資格の扱いは学校や自治体によって異なります。
内申点の評定そのものに直接加点される(例:英検3級で英語の評定に+1)ケースは多くありませんが、以下のような形で評価される可能性があります。
- 調査書の「諸活動の記録」欄に記載でき、面接でのアピール材料になる
- 私立高校の推薦入試などで、「英検準2級以上で加点」のように評価される
志望校の募集要項を確認し、加点対象になるようであれば挑戦する価値はあります。
対策⑤学級活動や委員会活動に真面目に参加する
高校受験に向けて内申点を1点でも上げる方法として、学級活動や委員会活動に真面目に参加することも挙げられます。
評定(5段階評価)に直接影響するわけではありませんが、調査書の「特別活動の記録」や「行動の記録」欄に、生徒の責任感や協調性として記載されます。
たとえば、委員会でリーダーシップを発揮した、学級活動で熱心に役割を果たした、などの記録は、とくに推薦入試や面接がある入試において評価の対象となります。
学校生活全体に真面目に取り組む姿勢が、内申書(調査書)全体の評価を高めることにつながります。
【地域別】内申点が関係ない・影響が小さい高校の探し方
内申点が合否に関係ない、または影響が小さい高校の探し方は、地域によって特徴があります。ここでは、主要な地域別に、内申点の影響が小さい高校を探すための具体的な方法を解説します。
ひとつずつ見ていきましょう。
東京で内申点が関係ない・影響が少ない高校を探す方法
東京での高校受験で内申点の影響を避けたい場合、主な選択肢は以下の2つです。
| 選択肢 | 特徴 |
|---|---|
| 私立高校の一般入試(オープン入試) | 調査書(内申点)を合否判定に用いず、当日の学力検査の結果のみで合否を決める入試方式です。 内申点に自信がなくても、実力勝負で逆転合格が可能です。 |
| 都立の「チャレンジスクール」 | 学力検査を実施せず、調査書(内申点)も合否判定に用いない学校です。 「志願申告書」「作文」「面接」によって、学習意欲や熱意を評価して合否を決めます。 |
具体的な探し方としては、東京都の私立中学高等学校協会のサイトや、各学校の募集要項で「オープン入試」の有無を確認するのが確実です。
大阪で内申点が関係ない・影響が少ない高校を探す方法
大阪で内申点が関係ない高校を探す場合も、最も有力な選択肢は「私立高校の一般入試(オープン入試)」を探すことです。
大阪府の公立高校入試は、内申点(調査書)と当日点(学力検査)を合計して判定するため、内申点が関係ないとは言えません。
しかし、多くの私立高校では、当日の学力検査の結果を重視する一般入試を実施しています。内申点が推薦基準に満たない場合でも、この方式なら実力で合格を目指せます。具体的な探し方は以下のとおりです。
- 大阪府の私立中学校高等学校連合会(私学連合会)のウェブサイトを確認する
- 各私立高校の入試情報ページで「オープン入試」の記載を探す
- 高校の合同説明会や、学校ごとの「個別相談会」に参加し、一般入試における内申点の扱いを直接確認する
神奈川・埼玉・京都・福岡など他の地域の場合
神奈川・埼玉・京都・福岡など他の地域においても、内申点が関係ない高校を探す基本戦略は「私立高校の一般入試(オープン入試)」を見つけることです。
公立高校入試は内申点と当日点の両方で評価されるのが一般的ですが、私立高校の一般入試なら内申点の影響を避けられる可能性が高いです。
具体的な探し方は、以下の2パターンです。
| 学校種別 | 探し方・戦略 |
|---|---|
| 私立高校の場合 | 各府県の私立中学高等学校協会(連合会)の公式サイトや、受験情報サイトを確認します。 「学力検査のみで判定」と記載されている学校が第一候補となります。 |
| 公立高校の場合 | 各都道府県の教育委員会のウェブサイトを確認し、「内申点:当日点」の比率を調べます。 当日点の比率が高い(例:3:7など)高校であれば、内申点の不足を当日点でカバーしやすくなります。 |
自治体や学校の募集要項を必ず確認しよう
内申点が関係ない・影響が小さい高校を探すうえで最も重要なのは、自治体や学校の募集要項を必ず確認することです。
思い込みで判断せず、一次情報を確認する習慣をつけましょう。募集要項の確認が必須な理由は以下のとおりです。
- 入試制度は年度によって変更される可能性があるため
- インターネット上の情報が古くなっている場合があるため
- 「内申点が関係ない」の定義が学校によって異なるため(例:「参考程度に見る」、「最低基準がある」、「面接の資料として使う」など)
- 私立高校は学校ごとの裁量が大きく、選抜方法の詳細は募集要項でしか確認できないため
- 公立高校も、内申点と当日点の比率や計算方法を公式資料で確認する必要があるため



ルールは変わることも。必ず最新の募集要項を確認しましょう。
内申点が不安でも高校受験で逆転合格を目指すなら塾に相談しよう
内申点が不安でも、塾と戦略を練れば逆転合格は可能です。ここでは、内申点に不安を抱える中学生におすすめの塾を3つ紹介します。
ひとつずつ見ていきましょう。
内申点が不安な中学生におすすめ塾①現論会


| 対象年齢 | 中学生・高校生・20歳までの既卒生 |
|---|---|
| 授業形態 | 個別コーチング指導(対面またはオンライン) |
| 入会金 | 55,000円 |
| 料金 | 49,500円~ ※コースによって料金は異なります。別途システム維持費が必要です。 |
| 無料体験 | ◯ |
| 講師 | 東大・京大・医学部・早慶などの難関大学に在籍する現役大学生コーチ |
| 特徴 | ・志望校合格から逆算したオーダーメイドの年間学習計画を作成 ・週1回のコーチングで学習の進捗管理と勉強法を指導 ・「スタディサプリ」の映像授業が見放題で、参考書学習と組み合わせる ・受験科目全てを対象に、総合点を最大化するための戦略的な指導 |
内申点が不安な中学生におすすめの塾1つ目は、現論会です。現論会は、志望校合格から逆算したオーダーメイドの学習計画を作成してくれるのが特徴です。
内申点が足りない場合でも、当日点で何点取れば逆転できるかを明確にし、そのための最短ルートを示してくれます。
専属のコーチが学習の進捗を徹底的に管理してくれるため、「内申点が低いから何から手をつければいいか分からない」という人におすすめです。
\ 資料請求・無料受験相談はこちら /
内申点が不安な中学生におすすめ塾②森塾


出典:morijuku.com
| 対象年齢 | 中学生・高校生・既卒生 |
|---|---|
| 授業形態 | 先生1人に生徒2人までの個別指導 |
| 入会金 | 20,000円 |
| 料金 | 小学生 5,880 円〜/30分 中学生 1 1,700円/30分 高校生 1 5,300円/30分 |
| 無料体験 | ◯ |
| 講師 | 大学生講師中心(一部社会人) |
| 特徴 | ・講師変更制度あり ・毎回の確認テストと無料補講「特訓部屋」 ・成績保証制度(1科目20点アップ保証) ・学校授業や定期テストに直結したカリキュラム |
内申点が不安な中学生におすすめの塾2つ目は、森塾です。森塾は、先生1人に生徒2人までの個別指導で、「わかる」まで「できる」ようになるまで徹底的に教えてくれるのが特徴です。
学校の授業の予習はもちろん、定期テスト対策にも強いため、内申点アップに直結します。一人ひとりの理解度に合わせて丁寧に指導してくれるので、基礎から着実に学力を伸ばし、内申点対策と当日点の勉強を両立させたい人におすすめです。
\ 無料体験・お問い合わせはこちら /
内申点が不安な中学生におすすめ塾③明光義塾


| 対象年齢 | 小学生・中学生・高校生 |
|---|---|
| 授業形態 | 講師1名に対し生徒3名程度の個別指導 |
| 入会金 | 11,000円(税込) ※キャンペーンにより無料になる場合あり |
| 料金 | 学年、受講教科、週の授業回数、学習プランに応じて個別に設定 |
| 無料体験 | ◯ |
| 講師 | 大学生、大学院生が中心。採用時に学力試験や面接を実施。 |
| 特徴 | ・一人ひとりに合わせたオーダーメイドの学習プランを作成 ・「わかる・話す・身につく」を重視した対話型の授業(MEIKO式コーチング) ・全国No.1の教室数で、豊富な受験情報を提供 ・定期的なカウンセリングで生徒・保護者をサポート |
内申点が不安な中学生におすすめの塾3つ目は、明光義塾です。明光義塾は、生徒が「わかったつもり」になるのを防ぐ、対話型の個別指導が特徴です。
生徒自身の言葉で説明してもらうことで、本質的な理解を促し、思考力を養います。内申点アップに必要な授業態度や提出物へのアドバイスも受けられるため、勉強のやり方そのものを見直したい人や、内申点と当日点の両方を効率よく伸ばしたい人におすすめです。
\ 資料請求・無料体験はこちら /
高校受験の内申点に関するよくある質問(FAQ)
高校受験の内申点に関して、多くの受験生や保護者が抱える疑問や不安について、よくある質問(FAQ)形式で回答します。内申点についての正しい知識を身につけ、不安を解消しましょう。
内申点が足りなくても高校受験で合格できる?
内申点が足りなくても高校受験で合格できる可能性は十分にあります。公立高校の場合は「内申点:当日点」の比率を確認し、当日点重視の高校を選んで学力検査で高得点を取れば逆転合格が可能です。
私立高校の場合は、内申点が関係ない「一般入試(オープン入試)」を実施している学校が多くあります。この方式なら、当日の学力検査の結果だけで合否が決まるため、内申点が足りなくても実力で合格を勝ち取ることができます。
諦めずに、内申点の影響が小さい入試方式を探すことが重要です。
私立高校の入試は本当に内申点関係ない?
私立高校の入試が「本当に内申点関係ないか」は、入試方式によります。推薦入試や併願優遇制度を利用する場合は、出願基準として内申点が設定されているため、内申点は大いに関係あります。
しかし「一般入試(オープン入試)」に限っては、内申点を合否判定に含めず、当日の学力検査の点数のみで合否を決める学校が多いです。
すべての私立高校の一般入試が内申点を全く見ないわけではなく「参考程度に見る」「最低基準がある」「面接資料として使う」といったケースも存在します。
志望校の募集要項を必ず確認しましょう。
一般入試でも内申点は影響する?
一般入試で内申点が影響するかどうかは、公立高校と私立高校で異なります。公立高校の一般入試では、ほとんどの都道府県で「内申点(調査書点)」と「当日点(学力検査点)」を合計して合否を判定するため、内申点は影響します。
一方、私立高校の一般入試(オープン入試)では、内申点の影響が小さい、あるいは全く関係ない(当日の学力検査のみで判定する)学校が多いです。
私立高校でも学校によっては内申点を考慮するため、志望校の募集要項で選抜方法を確認することが必須です。
高校受験で内申点が5点や10点足りない場合どうすればいい?
高校受験で内申点が志望校の基準に対して5点や10点足りない場合、まずは冷静に戦略を立て直す必要があります。
公立高校が第一志望の場合、その不足分を当日点(学力検査)でカバーできるかをシミュレーションします。当日点重視の高校であれば、学力検査で高得点を取ることに集中する戦略が取れます。
私立高校の場合は、内申点が関係ない「一般入試(オープン入試)」に切り替えるのが最も有効な戦略です。
また、推薦や併願優遇を希望する場合は、基準の見直し(加点要素がないか確認する、など)や、志望校のランクを再検討する必要も出てきます。
内申点の「ひいき」って本当にあるの?
内申点の「ひいき」については、制度上は存在しないはずですが、生徒や保護者がそのように感じてしまう要因はあります。
内申点の評定は、「知識・技能(テストの点数)」だけでなく「思考・判断・表現(発表など)」や「主体的に学習に取り組む態度(授業態度、提出物)」も評価対象となります。
とくに「主体的に学習に取り組む態度」は、数値化しにくい部分であり、評価する先生の主観が入る余地がゼロとは言い切れません。
この評価基準の曖昧さが「先生のお気に入りかどうか」で評定が左右されているのではないかという「ひいき」への不信感につながりやすいと言えます。
遅刻や早退は内申書に書かれて受験に響く?
遅刻や早退は、内申書(調査書)の「出欠席の記録」欄に記載され、受験に響く可能性があります。とくに推薦入試や併願優遇では、内申点の基準とあわせて「3年間の欠席日数が○日以内」といった出願基準を設けている学校が多いです。
遅刻や早退も、回数が多いと「欠席」として扱われる場合(例:遅刻3回で欠席1日とカウント)があります。一般入試であっても、合否ライン上に複数の生徒が並んだ場合、出欠席の記録が悪い生徒は不利になる可能性があります。
ただし、体調不良ややむを得ない理由がある場合は、中学校の先生を通じて高校側に事情を説明できる場合もあります。
内申書(調査書)を自分で見ることはできる?
原則として、生徒や保護者が内申書(調査書)の原本を直接見ることはできません。調査書は、中学校が作成し、高校へ提出する公的な書類(指導要録の写し)であり、厳封されて扱われるためです。
ただし、自分の評定(内申点)については、通知表を見ればわかります。また、先生との進路面談の際に、調査書にどのような評定が記載されているのか(または記載される見込みなのか)を口頭で教えてもらうことは可能です。
出願前に自分の内申点(評定)がいくつなのかを正確に把握しておくことは、志望校決定のために不可欠です。
まとめ
高校受験で内申点が関係ないケースは限定的であり、ほとんどの入試で内申点は合否に関係します。しかし、内申点が足りないからといって、高校受験を諦める必要はありません。
内申点が足りない場合の逆転合格戦略は次のとおりです。
- 当日点(学力検査)重視の高校を志望校にする
- 私立高校の一般入試・オープン入試(内申点が関係ない方式)に切り替える
- 学力検査で高得点を取る勉強法に集中する
- 面接や自己PRで学習意欲や熱意を伝える
内申点が足りない状況でも、当日の学力検査で高得点を取れば逆転合格は十分に可能です。また、定期テスト対策や提出物の質を高めるなど、今からでも内申点を1点でも上げる努力を続けることも大切です。
内申点に不安があり、逆転合格のための戦略を一人で立てるのが難しい場合は、塾のプロに相談するのも有効な手段です。
この記事で紹介した戦略を参考に、自分に合った方法で志望校合格を目指しましょう。

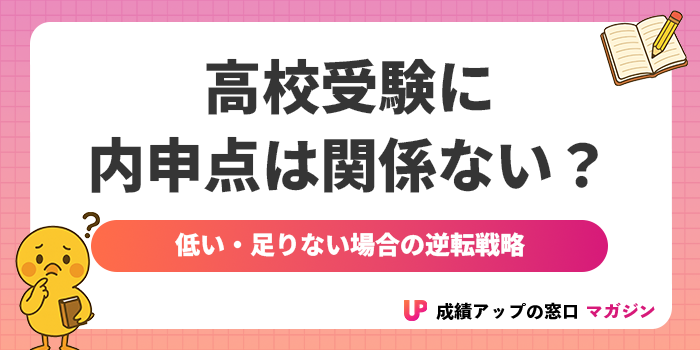

コメント