 ひよこ生徒
ひよこ生徒中学生だけど、受験勉強って何からすればいいの?
受験勉強の始め方がわからなくて不安…
中3からでも間に合うのかな?
中学生になって「受験勉強は何からすればいいんだろう」と不安を感じている人は多いでしょう。高校受験は定期テストとは異なり出題範囲が広く、内申点と学力検査の両方が重要になるため、早めの準備と正しい始め方が合否を分けます。
この記事では、中学生が受験勉強を始める時期や、まず何から手をつけるべきかの具体的なステップ、5教科の優先順位について詳しく解説します。



受験勉強の始め方に迷うのは当然のことです。まずは勉強の習慣化と、とくに英数の基礎固めからスタートしましょう。
この記事で紹介する時期別・教科別のポイントを押さえれば、効率よく対策を進められますよ。
- 中学生の受験勉強でまずやるべき3ステップ
- 受験勉強はいつから始めるべきか(学年別のポイント)
- 5教科の優先順位と教科別の始め方
- 効率的な学習計画の立て方とやる気が出ない時の対処法
中学生の受験勉強は何からすればいい?知っておくべきポイント
中学生が「受験勉強は何からすればいいか」と悩んだとき、まず知っておくべき基本的なポイントがあります。普段の勉強との違いや高校受験の仕組みを理解することで、対策の第一歩が明確になります。
ひとつずつ見ていきましょう。
受験勉強と普段の勉強の違い
中学生の受験勉強で知っておくべきポイントの1つ目は、受験勉強と普段の勉強(定期テスト)の違いを理解することです。
主な違いは「出題範囲の広さ」と「競争相手の存在」にあります。普段の定期テストは、出題範囲が直近の授業内容(例:教科書のP50〜P80まで)に限られています。
一方、高校受験の出題範囲は、原則として中学1年生から3年生までに習った内容すべてです。また、定期テストは設定された点数(例:80点)を目指す自分との戦いですが、受験は違います。
受験は、定員に対して他の受験生と点数を競い合い、合否が決まる「競争」です。そのため、広範囲の基礎を固め、応用力を身につける必要があります。
高校受験の仕組み|内申点と学力検査
中学生の受験勉強で知っておくべきポイントとして、高校受験の仕組みも挙げられます。多くの公立高校受験では、合否は「内申点(調査書点)」と「学力検査(入試当日点)」の合計点で決まります。
内申点は、中学の成績表(通知表)の評定を点数化したものです。都道府県によって異なりますが、中学1年生から3年生までの成績が影響する場合が多く、定期テストの点数だけでなく、授業態度や提出物なども評価対象です。
学力検査は、入試当日のペーパーテストの点数です。受験勉強は、当日の学力検査対策だけでなく、日々の授業や定期テストで内申点を確保することも含まれると理解しておきましょう。
まずは「勉強の習慣化」から始めよう
中学生が受験勉強を始めるうえで、まずは「勉強の習慣化」から始める点がポイントです。本格的な受験対策を始める前に、毎日決まった時間に机に向かう習慣を身につけることが、何より大切になります。
受験勉強は長期間にわたるため、いきなり「毎日3時間勉強する!」と高い目標を立てても続きません。「まずは5分だけ」「寝る前に15分だけ英単R単を覚える」「夕食後に必ず30分問題集を開く」など、ごく短い時間からで構いません。
学習を生活リズムの一部に組み込み、「勉強するのが当たり前」の状態を作ることが、長い受験勉強を乗り切るための土台となります。



まずは短い時間でも毎日続けることが大切ですよ。
中学生の受験勉強はいつから始めるのがベスト?
中学生の受験勉強の開始時期として、理想は早くから意識することですが、各学年で取り組むべき内容は異なります。
詳しく解説します。
中学1年生から意識すること
中学生の受験勉強は、中学1年生から意識し始めるのがベストです。なぜなら、多くの都道府県で高校受験の内申点に中学1年生の成績が含まれるためです。
とはいえ、中1から入試問題を解く必要はありません。この時期に最も大切なのは「日々の授業を大切にすること」と「学習習慣を定着させること」です。
具体的には、以下の点を意識しましょう。
- 授業に集中し、ノートをていねいに取る
- 提出物を期限内に必ず出す
- 定期テストで高得点を目指す
当たり前のことですが、これこそが内申点対策の基本であり、中3になってから本格的な受験勉強を始めるときに大きな土台となります。
中学2年生から始める受験準備(中2からでも遅くない)
中学生の受験勉強は、中学2年生から本格的に準備を始めても遅くはありません。中2は部活動の中心となり、学校生活で最も忙しくなる時期ですが、勉強面では「中だるみ」しやすい時期でもあります。
この時期に受験を意識できるかが、中3になってからの伸びを左右します。中2から始める受験準備としては、まず中学1年生の学習内容の総復習、とくに苦手単元の克服から手をつけるのがおすすめです。
中2で習う内容は、中1の基礎が定着している前提で進みます。中2の勉強と並行して、数学の計算や英語の文法など、忘れている中1の範囲を復習し、基礎を固め直しておきましょう。
中学3年生からでも間に合う?(中3からの逆転法)
中学生の受験勉強は、中学3年生から始めても間に合わせることは可能です。部活を引退してから本腰を入れる生徒も多く「中3からでは遅い」と諦める必要はまったくありません。
ただし、中1・中2からコツコツ準備してきた生徒に追いつくためには、効率的な学習計画が不可欠です。中3から逆転合格を目指す場合、まずは中学1・2年生の総復習を最優先で行います。
とくに中3の夏休みは、全範囲を復習できる最後のチャンスです。自分の苦手分野を徹底的に洗い出し、基礎固めに全力を注ぎましょう。
基礎が固まれば、秋以降の応用問題や過去問演習で一気に点数を伸ばせる可能性があります。



部活を引退した中3からでも間に合いますか?



もちろんです。夏休みの基礎固めが逆転の鍵ですよ。
中学生の受験勉強は何からすればいい?まずやるべき3ステップ
「中学生の受験勉強は何からすればいいか」と悩んだら、まず取り組むべき具体的な手順があります。効率的に受験勉強をスタートするために、以下の3つのステップを踏んで進めましょう。
各ステップを順に見ていきましょう。
手順①志望校と現在の学力を知る
中学生の受験勉強でまずやるべきことの第一手順は、志望校と現在の学力を知ることです。ゴール(志望校の合格ライン)とスタート地点(現在の実力)を明確にしなければ、何をどれだけ勉強すればいいかわかりません。
まずは、学校の成績や模試の結果、内申点などから自分の現状を客観的に把握しましょう。そのうえで、気になる高校の偏差値や必要な内申点を調べ、目標とのギャップを確認します。
「あと何点必要なのか」「どの教科を伸ばすべきか」を具体的に知ることが、受験勉強の第一歩です。
手順②学習計画を立てる
中学生の受験勉強でまずやるべきことの次の手順として、学習計画を立てましょう。志望校と現在の学力の差がわかったら、そのギャップを埋めるための「いつまでに」「何を」「どれだけやるか」の計画が必要です。
いきなり完璧な計画を立てる必要はありません。まずは入試本番までの長期的な目標(例:夏休みまでに1・2年の復習を終える)を決めます。
次に、月単位、週単位、日単位の短期的な目標に落とし込みます。「今日は数学の問題集をP10〜P15までやる」のように、毎日やるべきことが明確になれば、迷わず勉強に取り組めます。
手順③基礎固め|特に苦手分野の復習を優先する
中学生の受験勉強でまずやるべきことの3番目の手順では、基礎固め、特に苦手分野の復習を優先します。学習計画を立てたら、いきなり応用問題に手を出すのではなく、中学1・2年生の内容の総復習(基礎固め)から始めましょう。
高校受験の問題の多くは、基礎知識の組み合わせで解けるためです。とくに、自分がつまずいている苦手分野を放置すると、その後の応用学習も進みません。
まずは苦手な単元や教科の復習を最優先にし、基礎を徹底的に固めることが、受験勉強を効率よく進めるための鍵となります。



応用問題より先に、苦手な基礎を潰すのが近道です。
中学生の受験勉強における5教科の優先順位
「中学生の受験勉強は何からすればいいか」と考えたとき、5教科すべてを同時に完璧にしようとするとパンクしてしまいます。
教科ごとに優先順位をつけて、効率よく学習を進めましょう。
詳しく解説します。
数学と英語が最優先
中学生の受験勉強における5教科の中では、数学と英語が最優先です。なぜなら、この2教科は知識の「積み重ね」が最も重要な科目であり、基礎ができていないと応用問題がまったく解けなくなるためです。
たとえば、数学は中学1年生の方程式がわからないと中学2年生の連立方程式は解けません。英語も、基本的な単語や文法がわからなければ長文読解は不可能です。
他の教科に比べて習得に時間がかかるため、受験勉強を何から始めるか迷ったら、まずは数学と英語の基礎固め(とくに1・2年生の復習)から優先的に取り組みましょう。



5教科ぜんぶ、何からやればいいかわかりません…。



まずは積み重ねが大事な「英数」の復習から始めましょう。
理科と社会はいつから手をつける?
中学生の受験勉強の優先順位として、理科と社会はの対策は中3の夏休み以降でも間に合いやすい科目です。
理科と社会は、数学や英語と比べて「暗記」の比重が高い分野が多く、勉強した分だけ点数に直結しやすいためです。そのため、まずは英数の基礎固めを優先し、部活引退後などに集中して暗記時間を確保するのが効率的です。
ただし、理科の計算分野(物理・化学)や、社会の歴史の流れ、地理の資料読解などは暗記だけでは対応できません。
これらの分野が苦手な場合は、早めに基礎を押さえておくと安心です。
国語はすべての勉強の土台
中学生の受験勉強において、国語はすべての勉強の土台となる科目です。国語力が低いと、他の教科の成績も伸び悩む可能性があります。
なぜなら、数学の文章題、英語の長文読解、理科や社会の資料読み取りなど、すべての教科で「問題文や資料を正しく読み解く力」が求められるためです。
漢字や文法は毎日コツコツ進めるのがおすすめですが、読解力は一朝一夕には身につきません。日頃から問題文を正確に読む癖をつけたり、要約する練習をしたりすることが、受験勉強全体の効率アップにつながります。
【教科別】中学生の受験勉強!何からすればいいか徹底ガイド
中学生の受験勉強で「何からすればいいか」は、教科の特性によっても異なります。優先順位の高い英語や数学はもちろん、他の教科も効率よく対策を進めることが合格への鍵です。
ここでは、5教科それぞれについて、まず何から手をつけるべきかを徹底ガイドします。
- 【英語】まずは単語と文法の復習から始める
- 【英語】長文読解の練習方法
- 【英語】リスニング対策のコツ
- 【数学】計算力の徹底強化
- 【数学】公式の暗記と使い方マスター
- 【数学】文章題・証明問題の解き方
- 【国語】漢字・語彙・文法を毎日コツコツ
- 【国語】読解問題の解き方を身につける
- 【理科】1・2年生の総復習(苦手単元)から
- 【理科】暗記分野(生物・地学)のコツ
- 【理科】計算分野(物理・化学)のコツ
- 【社会】歴史・地理・公民の流れを掴む
- 【社会】重要語句の暗記と資料の読み取り
ひとつずつ見ていきましょう。
【英語】まずは単語と文法の復習から始める
中学生の受験勉強において、英語で何からすればいいか迷ったら、まずは英単語と英文法の復習から始めるのが基本です。
単語と文法は、英語の長文読解や英作文、リスニングすべての土台となるためです。とくに中学1・2年生で習った基本的な単語や、be動詞・一般動詞の違い、時制、助動詞などの文法があいまいなままでは、中3の内容や入試問題に対応できません。
まずは教科書や単語帳を使い、基本的な語彙を確実に覚えることからスタートしましょう。文法も、薄い問題集でいいので1・2年生の範囲を総復習し、知識の抜け漏れをなくすことが最優先です。
【英語】長文読解の練習方法
中学生の英語の受験勉強における長文読解の練習方法として、まずは短い文章から正確に読む練習をすることがおすすめです。
いきなり入試レベルの長文に挑戦しても、単語や文法がわからず挫折してしまいます。教科書レベルの比較的短い文章を使い、一文ずつ「主語」と「動詞」を見つけ、文の構造を理解しながら日本語に訳す練習(精読)をしましょう。
正確に読めるようになったら、徐々に文章量を増やし、読むスピードを意識します。長文読解は「単語力」「文法力」「読解スピード」の総合力が問われるため、基礎固めと並行して少しずつ取り組むのがコツです。
【英語】リスニング対策のコツ
中学生の英語の受験勉強におけるリスニング対策のコツは、毎日少しの時間でも英語の音声に触れることです。リスニング力は、短期間で一気に伸びるものではなく、継続的な練習によって耳が慣れていくためです。
以下の手順でリスニングの練習をしましょう。
- 教科書の付属CDやリスニング教材の文章(スクリプト)を見ながら音声を聞く
- 何を言っているか理解できたら、今度は文章を見ずに音声だけを聞く
- 慣れてきたら、聞いた音声をそのまま口に出して真似する「シャドーイング」を行う
1日5分でも10分でもいいので、毎日続けることが合格点を取るための鍵となります。
【数学】計算力の徹底強化
中学生の数学受験勉強で何からすればいいかといえば、計算力の徹底強化が挙げられます。計算力は、数学のすべての問題(方程式、関数、図形など)を解くための土台であり、この力が不足していると応用問題で太刀打ちできません。
とくに、正負の数、文字式の計算、連立方程式など、中学1・2年生で習った基本的な計算は、スピードと正確性の両方が求められます。
まずは計算ドリルや問題集の基本問題を使い、毎日一定量を解く練習をしましょう。ケアレスミスを減らし、スピーディーかつ正確に答えを導き出す力を養うことが、数学の得点アップへの第一歩です。
【数学】公式の暗記と使い方マスター
中学生の数学受験勉強において、公式の暗記と、その使い方のマスターも重要です。数学には図形の面積や体積、方程式の解の公式など、覚えるべき公式がいくつも存在します。
ただし、公式はただ丸暗記するだけでは意味がありません。大切なのは、「どのような問題のときに、どの公式を使えば解けるのか」を理解することです。
公式を覚えたら、必ず問題集の基本問題を解き、公式の使い方をセットで練習しましょう。公式の意味や導出過程もあわせて理解しておくと、応用問題にも対応しやすくなります。
【数学】文章題・証明問題の解き方
中学生の数学の受験勉強では、多くの受験生が苦手とする文章題や証明問題の解き方を身につけることも必要です。これらの問題は、計算力だけでなく読解力や論理的思考力が問われます。
それぞれの対策のポイントは、以下のとおりです。
| 問題の種類 | 対策のポイント |
|---|---|
| 文章題 | 問題文を読み、「何を求められているのか」「わかっている情報は何か」を正確に把握し、立式する練習を繰り返す。 |
| 証明問題 | まず「仮定」と「結論」を明確にする。次に結論を導くために必要な根拠(定義や定理)を書き出す練習から始める。 |
とくに証明問題は、まず教科書や問題集の解答を書き写す(写経する)ことから始め、解答の型を覚えるのがおすすめです。
【国語】漢字・語彙・文法を毎日コツコツ
中学生の国語の受験勉強で何からすればいいか迷ったら、漢字・語彙・文法を毎日コツコツ続けることから始めましょう。
これらの知識問題は、入試での得点源となりやすく、勉強した分だけ確実に点数に結びつきます。漢字は、読み書きだけでなく、部首や対義語・類義語などもあわせて確認しておくと語彙力アップにつながります。
文法(品詞の分類、助詞・助動詞の使い方など)も、一度総復習しておけば、読解問題で文章構造を正確に把握する助けになるでしょう。
1日10分でもいいので、専用の問題集やアプリを使い、入試本番まで毎日継続することが大切です。
【国語】読解問題の解き方を身につける
中学生の国語の受験勉強では、読解問題の解き方(テクニック)を身につける点も挙げられます。国語の読解問題は、感覚やセンスで解くものではなく、論理的な解き方が存在します。
文章の種類ごとの解き方の基本は、以下のとおりです。
| 文章の種類 | 解き方の基本 |
|---|---|
| 小説文 | 「登場人物の心情の変化」に注目し、そのきっかけとなった出来事やセリフを探す。 |
| 論説文(説明文) | 「筆者の主張(結論)」と「その理由・具体例」を区別しながら読む。 |
まずは問題集を解き、答え合わせの際に「なぜその答えになるのか」の根拠を解説でしっかり確認する作業を繰り返す必要があります。
【理科】1・2年生の総復習(苦手単元)から
中学生の理科の受験勉強で何からすればいいかといえば、まずは中学1・2年生の総復習、とくに苦手単元から手をつけることです。
理科は「物理」「化学」「生物」「地学」の4分野に分かれており、それぞれ学習内容が独立している単元も多くなっています。
そのため、全範囲を一度に復習するよりも、自分の苦手な単元(例:化学変化、電流、天気の変化など)を特定し、そこを集中的に潰していくほうが効率的です。
まずは教科書や参考書を読み直し、基本的な用語や原理を理解することから始めましょう。基礎が理解できたら、問題集の基本問題を解いて知識を定着させます。
【理科】暗記分野(生物・地学)のコツ
中学生の理科の受験勉強における暗記分野(おもに生物・地学)のコツとして、図や表と関連付けて覚えることが挙げられます。
生物の体のつくりや植物の分類、地層や火山の種類などは、文字だけで覚えようとすると非効率です。教科書や資料集に載っている図、写真、グラフなどを活用し、視覚的なイメージと一緒にインプットしましょう。
単語カードや一問一答形式の問題集を使い、スキマ時間に繰り返し復習するのも効果的です。知識が混同しないよう、単元ごとに整理しながら覚えていくことが大切です。
【理科】計算分野(物理・化学)のコツ
中学生の理科の受験勉強における計算分野(おもに物理・化学)のコツは、公式の意味を理解し、単位に注意しながら基本問題を繰り返し解くことです。
電流・電圧・抵抗の関係(オームの法則)や、化学変化の量的関係(質量保存の法則)、濃度計算などは、公式や法則の暗記が必須です。
ただし、丸暗記ではなく「なぜその式が成り立つのか」を理解することが応用力につながります。まずは簡単な計算問題を解き、公式の使い方をマスターしましょう。
計算ミスを防ぐため、単位($\Omega$, A, V, g, %など)を意識する癖をつけることも大切です。
【社会】歴史・地理・公民の流れを掴む
中学生の社会の受験勉強で何からすればいいか迷ったら、まずは歴史・地理・公民の全体の「流れ」を掴むことから始めましょう。
社会は暗記科目と思われがちですが、バラバラの知識を詰め込むだけでは入試に対応できません。とくに歴史は、「なぜその出来事が起こったのか」「その結果どうなったのか」という因果関係(時代の流れ)を理解することが最優先です。
地理は地域ごとの特徴、公民は現代社会の仕組みといった大枠をまず捉えましょう。教科書やマンガ教材などを通読し、全体像を把握してから詳細な語句の暗記に入ると、知識が定着しやすくなります。



暗記の前に、まず全体の「流れ」を掴むと効率的ですよ。
【社会】重要語句の暗記と資料の読み取り
中学生の社会の受験勉強において、流れを掴んだ後は重要語句の暗記と資料の読み取りがポイントです。一問一答の問題集や単語カードを活用し、基本的な人名、出来事、地名などを正確に覚えます。
同時に、高校受験では地図、年表、グラフ、写真などの資料を読み解く問題が必ず出題されます。暗記した重要語句が、資料中のどこに該当するのかを関連付けながら学習を進めましょう。
教科書や資料集をていねいに確認し、資料を読み解く練習を積んでおくことが高得点の鍵です。
【時期別】中学生の受験勉強スケジュール
中学生の受験勉強を「何からすればいいか」は、時期によっても優先順位が異なります。とくに中学3年生になってからは、計画的なスケジュール管理が合否を分けます。
ここでは、中学3年生の受験勉強について、時期別にやるべきことを解説します。
詳しく解説します。
中3の夏休み前まで(授業の復習と基礎固め)
中学生の受験勉強スケジュールにおいて、まず中3の夏休み前までは「授業の復習と基礎固め」が最優先です。この時期は、内申点に直結する中間・期末テスト対策と並行して、受験勉強の土台を作る大切な期間になります。
まずは学校の授業に集中し、その日のうちに習った内容を復習する習慣をつけましょう。とくに英語と数学は、中学1・2年生の範囲で苦手な単元があれば、早めに潰しておく必要があります。
部活動もまだ続いているため、スキマ時間を見つけて、単語や漢字などの基礎知識の定着も進めると効率的です。夏休み以降の本格的な受験勉強に備え、まずは学校の勉強をおろそかにせず、基礎を固めることに専念しましょう。
中3の夏休み(1・2年の総復習と苦手克服)
中学生の受験勉強スケジュールにおいて、中3の夏休みは「中学1・2年生の総復習と苦手克服」に全力を注ぐ時期です。
夏休みは、まとまった勉強時間を確保できる最後のチャンスであり、受験の天王山とも呼ばれます。この期間に、5教科すべての1・2年生の範囲を総復習する計画を立てましょう。
とくに、これまで放置してきた苦手単元を徹底的に洗い出し、基礎から理解し直すことが大切です。薄い問題集を1冊完璧にするなど、目に見える成果を意識するとモチベーション維持につながります。
この夏休みの頑張りが、秋以降の成績の伸びを大きく左右するといっても過言ではありません。



夏休みは「受験の天王山」!ここで基礎を固めきりましょう。
中3の秋(応用問題と演習)
中学生の受験勉強スケジュールとして、中3の秋(9月〜12月頃)は「応用問題と演習」に取り組む時期にあたります。
夏休みまでに固めた基礎知識を使い、実際に入試で得点できる力(応用力・実践力)を養う必要があるためです。
基礎問題集が終わったら、入試レベルの標準・応用問題が掲載されている問題集にステップアップします。学校の実力テストや模試も増えるため、結果に一喜一憂せず、間違えた問題を徹底的に復習して「解き直しノート」を作成するのがおすすめです。
この時期は内申点が決まる最後の定期テストもあるため、テスト勉強と受験勉強の両立が求められます。
中3の冬休み(過去問演習と弱点補強)
中学生の受験勉強スケジュールにおける中3の冬休みは、「過去問演習と弱点補強」を集中的に行う時期です。志望校の出題傾向を掴み、時間配分の感覚を身につけ、最後の追い込みをかけます。
志望校の過去問(第一志望・併願校)を少なくとも3〜5年分は解きましょう。解く際は必ず時間を計り、本番さながらの緊張感で取り組みます。
解き終わったら丸付けをし、間違えた問題や時間内に解けなかった原因を分析しましょう。過去問で見つかった弱点(例:数学の証明問題、英語の長文読解など)を、冬休み中に徹底的に補強する必要があります。
中3の直前期(最終確認と体調管理)
中学生の受験勉強スケジュールにおいて、中3の直前期(1月〜入試本番)は「最終確認と体調管理」が最も重要です。
新しいことに手を出すよりも、これまでやってきたことの精度を高め、万全のコンディションで本番を迎えることが合格につながります。
この時期にやるべきことは、以下のとおりです。
- 新しい問題集には手を出さず、これまで使ってきた問題集や「解き直しノート」の復習に徹する
- 暗記分野(理科・社会・英単語など)の最終チェックを行い、知識の抜け漏れをなくす
- 睡眠時間をしっかり確保し、生活リズムを崩さない
本番で100%の力を発揮できるよう、知識の確認と体調管理に細心の注意を払いましょう。
中学生が受験勉強の効率を上げる学習計画の立て方
「受験勉強は何からすればいいか」が理解できたら、次に効率を上げる学習計画の立て方が鍵となります。やみくもに勉強するのではなく、計画的に進めることで成果が出やすくなります。
ここでは、効率的な学習計画を立てるための3つのコツを紹介します。
ひとつずつ見ていきましょう。
長期(月単位)と短期(週・日単位)の目標を決める
中学生が受験勉強の効率を上げる学習計画の立て方のポイントは、長期(月単位)と短期(週・日単位)の目標を具体的に決めることです。
ゴールから逆算して計画を立てるのが基本となります。まずは「夏休みまでに1・2年の総復習を終える」「冬休みまでに過去問を5年分解く」といった長期的な目標(月単位)を設定します。
次に、その目標を達成するために「今週中に英語の問題集をP30まで進める」「今日は数学の計算練習を3ページやる」といった短期的な目標(週・日単位)に落とし込みます。
やるべきことが明確になれば、毎日の勉強に迷いがなくなり、達成感を積み重ねながら学習を進められます。
1日の勉強スケジュール(時間割)を作る
中学生が受験勉強の効率を上げる学習計画の立て方として、1日の勉強スケジュール(時間割)を作る点も挙げられます。
毎日の生活リズムの中に勉強時間を組み込むことで、学習の習慣化が進むためです。ポイントは、部活動や学校行事、食事や休憩時間も考慮し、無理のないスケジュールを立てることです。
「どの時間にどの教科をやるか」を決めておくと、スムーズに勉強を開始できます。平日のスケジュール例は以下のとおりです。
- 19:00〜20:00:夕食・休憩
- 20:00〜21:00:数学(計算・復習)
- 21:00〜22:00:英語(単語・文法)
- 22:00〜22:30:理科・社会(暗記)
このように時間割を決めておくと、メリハリをつけて学習に取り組めます。
参考書や問題集は「3周」する前提で選ぶ
中学生が受験勉強の効率を上げる学習計画を立てるには、参考書や問題集は「3周」する前提で選ぶことも大切です。
受験勉強では、たくさんの問題集に手を出すよりも、1冊を完璧に仕上げるほうが効果的です。1周目ですべてを理解しようとする必要はありません。
- 1周目:全体を把握し、解ける問題と解けない問題に仕分ける
- 2周目:解けなかった問題だけを解き直し、理解を深める
- 3周目:全範囲をもう一度解き、知識を完璧に定着させる
この「3周」を計画に組み込むためにも、自分のレベルに合い、最後までやり切れそうな厚さの問題集を選ぶようにしましょう。



問題集はたくさんの種類を解いたほうが良いですか?



いいえ、1冊を完璧にする方が効率的です。3周が目標です。
高校受験勉強のやる気が出ない時の対処法
高校受験の勉強は長期間にわたるため、誰でもやる気が出ない時期はあります。大切なのは、やる気がないときにどう行動するかです。
ここでは、勉強のやる気が出ない時の具体的な対処法を4つ紹介します。
順にみていきましょう。
対処法①勉強した内容を記録する(見える化)
高校受験勉強のやる気が出ない時の対処法の1つ目は、勉強した内容を記録して「見える化」することです。自分がどれだけ頑張ったかが視覚的にわかると、達成感が得られ、モチベーション維持につながります。
たとえば、勉強した時間を手帳やアプリに記録したり、終わらせた問題集のページを塗りつぶしたりする方法がおすすめです。
「これだけやったんだ」という自信が、次の勉強への意欲を引き出します。学習の成果が目に見える形になると、ゲーム感覚で楽しく続けられる可能性もあります。
対処法②まずは5分だけ取り組んでみる
高校受験勉強のやる気が出ない時の対処法として、まずは5分だけ取り組んでみる点も挙げられます。「勉強を始める」というハードルが最も高いため、一度始めてしまえば意外と集中できることは多いものです。
「単語を10個だけ覚える」「計算問題を1問だけ解く」など、ごく簡単なことから手をつけてみましょう。心理学で「作業興奮」と呼ばれるように、手を動かし始めると脳が活性化し、次第にやる気が出てくることが期待できます。
どうしてもやる気が出ない日は、5分で終えても構いません。まずは机に向かう習慣を途切れさせないことが大切です。



やる気が出ない日もあって当然です。5分からでOKですよ。
対処法③勉強する場所や環境を変えてみる
高校受験勉強のやる気が出ない時には、勉強する場所や環境を変えてみるのも対処法のひとつです。いつも同じ自分の部屋で集中できない場合、環境を変えることで気分転換になり、集中力が高まる可能性があります。
たとえば、以下のような場所で試してみるのもいいでしょう。
- リビングの食卓
- 学校の図書館
- 塾の自習室
場所を変えなくても、机の上を片付けてきれいにしたり、勉強中はスマートフォンを別の部屋に置いたりするだけでも、気分が変わり勉強に取り組みやすくなります。
対処法④ライバルや仲間を意識する
高校受験勉強のやる気が出ない時の対処法4つ目は、ライバルや仲間を意識することです。自分一人だけで勉強していると、孤独を感じたり、つい甘えが出たりしがちです。
同じ高校を目指す友人や、模試の成績で競い合っているライバルを意識することで、「あの人も頑張っているから自分も頑張ろう」という競争心や仲間意識が芽生えます。
塾に通って仲間と競い合いながら学ぶのも一つの方法です。適度な緊張感が生まれ、勉強への意欲が刺激されるでしょう。
ただし、他人と比較しすぎて自信を失わないよう注意は必要です。
高校受験勉強で「わからない」を解決するコツ
高校受験に向けて勉強を進めていると「わからない」問題に直面するのは当然のことです。大切なのは、その「わからない」を放置せず、解決する方法を知っておくことです。
ここでは、受験勉強で「わからない」を解決するための4つのコツを紹介します。
ひとつずつ見ていきましょう。
コツ①学校の授業と宿題を大切にする
高校受験勉強で「わからない」を解決するコツの1つ目は、学校の授業と宿題を大切にすることです。学校の授業は、すべての学習の基本であり、先生は重要なポイントや間違いやすい点を解説してくれます。
宿題は、授業で習った内容を定着させるために出されるものです。日々の授業や宿題をおろそかにしてしまうと、後から追いつくのが難しくなります。
まずは授業内容をしっかり理解し、宿題にていねいに取り組むことが、「わからない」を減らすための最も基本的な対策となります。
コツ②わからないことを放置しない
高校受験勉強で「わからない」を解決するコツとして、わからないことを放置しない点も挙げられます。とくに数学や英語のような積み重ねが大切な教科では、1つの「わからない」が次の単元の「わからない」につながってしまいます。
疑問点が出てきたら、その場ですぐに教科書や参考書で調べる、先生や友人に質問するなど、早めに解決する癖をつけましょう。
「わからない」をため込まないことが、受験勉強をスムーズに進めるための鍵となります。
コツ③模擬試験や過去問で実力を試す
高校受験勉強で「わからない」を解決するには、模擬試験や過去問で実力を試すのもコツのひとつです。「わかったつもり」になっていても、実際の問題が解けないケースは少なくありません。
模擬試験や過去問は、自分の現在の実力や苦手分野を客観的に把握するための最適なツールです。大切なのは、点数だけを見て一喜一憂することではありません。
間違えた問題を徹底的に復習し、「なぜ間違えたのか」「どうすれば解けたのか」を理解することで、確実な実力アップにつながります。
コツ④塾や家庭教師に相談する
高校受験勉強で「わからない」を解決するコツの4つ目は、塾や家庭教師に相談することです。自力でどうしても解決できない場合や、そもそも「何がわからないのか」がわからない場合は、指導のプロに頼るのが効果的です。
塾や家庭教師は、生徒がつまずくポイントを熟知しており、一人ひとりに合ったわかりやすい解説をしてくれます。勉強の進め方や受験に対する不安なども相談できるため、精神的な支えにもなるでしょう。
わからないことを解決し、効率よく勉強を進めるための選択肢として検討してみてください。



「何がわからないか」がわからない時はプロに頼るのも手です。
中学生におすすめの高校受験対策向け学習塾3選
中学生の高校受験対策におすすめの学習塾を3社厳選して紹介します。各塾の特徴や指導方針、サポート体制を比較し、お子さまに最適な塾を見つけるための参考にしてください。
ひとつずつ見ていきましょう。
現論会


| 対象年齢 | 中学生・高校生・20歳までの既卒生 |
|---|---|
| 授業形態 | 個別コーチング指導(対面またはオンライン) |
| 入会金 | 55,000円 |
| 料金 | 49,500円~ ※コースによって料金は異なります。別途システム維持費が必要です。 |
| 無料体験 | ◯ |
| 講師 | 東大・京大・医学部・早慶などの難関大学に在籍する現役大学生コーチ |
| 特徴 | ・志望校合格から逆算したオーダーメイドの年間学習計画を作成 ・週1回のコーチングで学習の進捗管理と勉強法を指導 ・「スタディサプリ」の映像授業が見放題で、参考書学習と組み合わせる ・受験科目全てを対象に、総合点を最大化するための戦略的な指導 |
中学生におすすめの高校受験対策向け学習塾の1つ目は、現論会です。現論会は、志望校合格から逆算したオーダーメイドの「年間計画表」を作成し、専属コーチが週1回の面談で勉強法や進捗を徹底的に管理してくれるのが特徴です。
一般的な授業は行わず、「何からすればいいか」を明確にして自学自習の効率を最大化する指導を行います。「何からすればいいか分からない」人や、計画通りに勉強を進めるのが苦手な中学生におすすめです。
\ 資料請求・無料受験相談はこちら /
森塾


出典:morijuku.com
| 対象年齢 | 中学生・高校生・既卒生 |
|---|---|
| 授業形態 | 先生1人に生徒2人までの個別指導 |
| 入会金 | 20,000円 |
| 料金 | 小学生 5,880 円〜/30分 中学生 1 1,700円/30分 高校生 1 5,300円/30分 |
| 無料体験 | ◯ |
| 講師 | 大学生講師中心(一部社会人) |
| 特徴 | ・講師変更制度あり ・毎回の確認テストと無料補講「特訓部屋」 ・成績保証制度(1科目20点アップ保証) ・学校授業や定期テストに直結したカリキュラム |
中学生におすすめの高校受験対策向け学習塾の2つ目は、森塾です。森塾は、「先生1人に生徒2人まで」の個別指導で、学校の授業の「予習」を中心に進めてくれるのが特徴です。
授業で習う前に塾で理解を深めることで、学校の授業がわかりやすくなります。また、定期テストの「成績保証制度」があり、入塾後2学期以内に学校のテストで必ず1回以上+20点を保証しています。
まずは学校の授業をしっかり理解し、内申点対策(定期テストの点数アップ)から始めたい人におすすめです。
\ 無料体験・お問い合わせはこちら /
明光義塾


| 対象年齢 | 小学生・中学生・高校生 |
|---|---|
| 授業形態 | 講師1名に対し生徒3名程度の個別指導 |
| 入会金 | 11,000円(税込) ※キャンペーンにより無料になる場合あり |
| 料金 | 学年、受講教科、週の授業回数、学習プランに応じて個別に設定 |
| 無料体験 | ◯ |
| 講師 | 大学生、大学院生が中心。採用時に学力試験や面接を実施。 |
| 特徴 | ・一人ひとりに合わせたオーダーメイドの学習プランを作成 ・「わかる・話す・身につく」を重視した対話型の授業(MEIKO式コーチング) ・全国No.1の教室数で、豊富な受験情報を提供 ・定期的なカウンセリングで生徒・保護者をサポート |
中学生におすすめの高校受験対策向け学習塾の3つ目は、明光義塾です。明光義塾は、講師による一方的な解説ではなく、生徒自身が学んだことを「話す」ことを重視する「MEIKO式コーチング」という対話型の個別指導が特徴です。
これにより「わかったつもり」を防ぎ、入試で必要な「考える力」を育てます。対面指導だけでなくオンライン個別指導も選べるため、ライフスタイルに合わせた学習が可能です。
自分の言葉で説明する練習を通して、知識を確実に定着させたい人におすすめです。
\ 資料請求・無料体験はこちら /
中学生の受験勉強は何からすればいいかに関するよくある質問(FAQ)
「中学生の受験勉強は何からすればいいか」に関して、受験生や保護者が抱きがちなよくある質問と回答をまとめました。受験勉強を始める際の疑問や不安を解消しましょう。
中学生の受験生は1日何時間くらい勉強すればいい?
中学生の1日に必要な勉強時間は、学年や目指す志望校、部活動の状況によって大きく異なります。中1・2年生であれば「学校の授業+1〜2時間」、中3生であれば「平日3時間以上、休日5〜8時間」を目安にする人が多いようです。
ただし、大切なのは時間数よりも「質」と「継続」です。時間ばかり気にするのではなく、「今日は問題集を3ページ進める」のように、その日にやるべき計画を確実に終えることを意識しましょう。
中学生の受験勉強は中3の夏休みや冬休みからでも逆転合格できる?
中学3年生の夏休みや冬休みから本格的に受験勉強を始めても、逆転合格することは十分に可能です。ただし、1・2年生からコツコツ勉強してきた生徒に追いつくためには、効率的な学習計画と高い集中力が不可欠です。
とくに夏休みは、中学1・2年生の総復習ができる最後のまとまった期間です。冬休みからの追い込みは、志望校のレベルや現在の学力との差を冷静に分析し、やるべきことを絞り込んで取り組む必要があります。
どうしても高校受験の勉強をする気になれなくて焦る時はどうしたらいい?
どうしても高校受験の勉強をする気になれなくて焦る時は、まず「5分だけ英単語を覚える」「計算問題を1問だけ解く」など、ごく簡単なことから手をつけてみるのがおすすめです。
心理学で「作業興奮」と呼ばれるように、行動し始めると脳が活性化し、次第にやる気が出てくることが期待できます。
勉強する場所を図書館や塾の自習室に変えたり、勉強した時間を記録して「見える化」したりするのも、気分転換になりモチベーション維持に役立ちます。
まとめ
中学生が受験勉強で「何からすればいいか」を迷った際の始め方や、教科別・時期別のポイントについて解説しました。
高校受験の勉強は、まず「勉強の習慣化」から始め、志望校と現状の学力を把握したうえで学習計画を立てることが大切です。
とくに習得に時間がかかる「英語」と「数学」の基礎固め(1・2年生の復習)から優先的に取り組みましょう。とはいえ、長期間の受験勉強ではやる気が出ない時期や、自力では「わからない」問題に直面することもあります。
もし一人で計画を立てたり、苦手分野を克服したりするのが難しい場合は、塾や家庭教師といったプロの力を借りるのも一つの有効な手段です。
この記事で紹介した内容を参考に、まずは「今できること」から第一歩を踏み出し、志望校合格を目指しましょう。

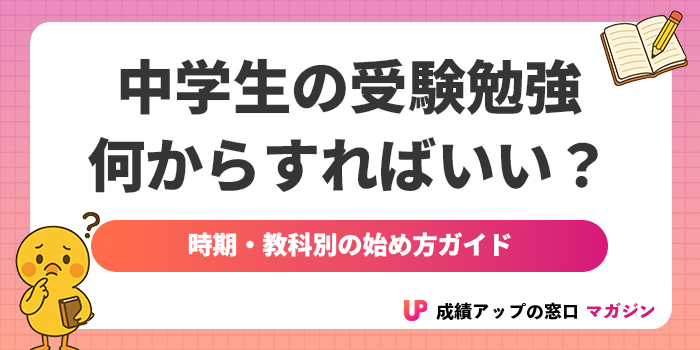
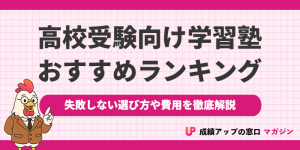

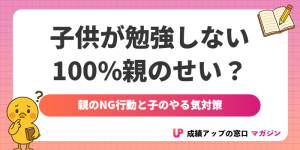
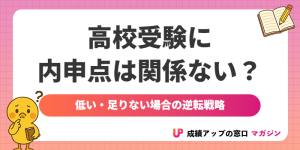
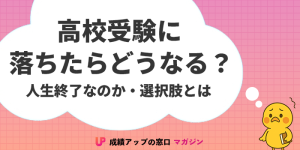
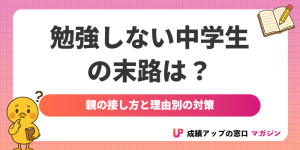
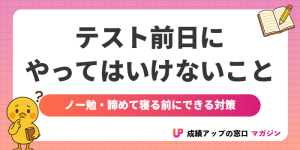
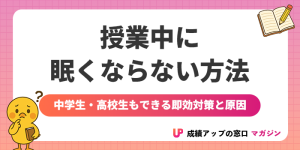


コメント