 ひよこ生徒
ひよこ生徒受験が終わったけど、塾へのお礼はやっぱり必要?
塾の先生に合格のお礼をしたいけど、どんなお菓子がおすすめかな?
お礼の金額相場や渡すときのマナーも知りたい!
受験が終わり、お世話になった塾の先生へ「合格のお礼」をしたいけれど、品物は必要なのか、お菓子などどんなものが喜ばれるのかと悩んでいる人も多いと思います。
この記事では、塾の先生へのお礼は必要なのかという疑問から、渡す場合の金額相場、おすすめのお菓子や品物、タイミングなどのマナーについて詳しく解説します。



塾へのお礼の品物は必須ではありませんが、感謝の気持ちを伝えることはとても大切です。
マナーや相場を知って、先生方に喜んでもらえる形で感謝を伝えましょう。
- 塾の先生へのお礼は必要か(塾講師の本音)
- 塾へのお礼の金額相場と選び方のポイント
- 【中学受験・合格後】塾へのお礼におすすめのお菓子や品物
- 塾のお礼を渡すタイミングやマナー(のし・手紙の書き方)
塾の先生へのお礼は必要?保護者の悩みと塾講師の本音
結論からいえば、塾の先生へのお礼の品物は必須ではありませんが、感謝の気持ちを伝えることは大切です。ここでは、塾講師の本音や一般的な考え方を解説します。
ひとつずつ見ていきましょう。
結論|お礼は必須ではないが感謝の気持ちは伝えるべき
塾の先生へのお礼の品は、結論として必須ではありません。塾側は月謝という形でサービスを提供しており、合格もその対価に含まれるため、追加のお礼をしなくてもマナー違反にはなりません。
しかし、受験は親子と塾が一丸となって乗り越える一大イベントです。とくに中学受験など、長期間にわたり手厚くサポートしてもらった場合、「何か形にして感謝を伝えたい」と思うのは自然な感情です。
お礼の品を渡すかどうかよりも、まずは合格の報告とともに、これまでの感謝を言葉でしっかりと伝えることを最優先にしましょう。
「品物は迷惑?」塾講師の本音
塾の先生へのお礼について「品物を渡すのはかえって迷惑かも?」と心配になる保護者もいます。 塾講師の本音としては、高額すぎるものや受け取りに困るもの(現金、手作り品など)は負担に感じる可能性がありますが、心のこもった手紙や、日持ちする個包装のお菓子などは素直に嬉しいと感じる講師がほとんどです。
講師にとって一番の喜びは、生徒の合格と成長です。「おかげさまで合格できました」という報告と感謝の言葉だけでも、十分な「お礼」になります。
品物は、あくまでその気持ちに添えるものと考えましょう。



お礼をしたいけど、迷惑じゃないか心配です…。



大丈夫ですよ。高額な品物より感謝の言葉が一番嬉しいものです。
塾へのお礼をしないのは失礼にあたる?
塾の先生へのお礼をしないことが、失礼にあたるのではないかと不安に思う必要はありません。前述のとおり、塾への対価は月謝として支払っているため、合格後にお礼の品がないからといって失礼と捉えられることはまずないです。
とくに、高校受験や大学受験では、中学受験に比べてお礼の品を渡す習慣は少ない傾向にあります。 大切なのは、お子さまが塾を卒業する際に、親子で合格の報告と感謝の気持ちを直接伝えることです。
あいさつさえしっかり行えば、品物がなくても良好な関係のまま終えられます。
お礼の品を禁止・辞退している塾もある
塾へのお礼を考える際、そもそも塾のルールとしてお礼の品を禁止・辞退しているケースもあるため注意が必要です。
大手進学塾や一部の個別指導塾では、講師が保護者から金品を受け取ることを社内規定で厳しく禁止している場合があります。
これは、講師と家庭間の特別な関係性を防ぎ、他の生徒と公平性を保つためです。 せっかく用意したお礼の品を受け取ってもらえないと、かえって気まずい雰囲気になりかねません。
事前に塾の公式サイトを確認したり、受付スタッフにそれとなく尋ねたりしておくと安心です。



塾によってはルールで禁止の場合も。事前に確認できると安心ですね。
無理にお礼の品を渡す必要はない
塾の先生へのお礼は、感謝の気持ちを伝える手段であり、義務ではありません。無理にお礼の品を渡す必要はない点を理解しておきましょう。
合格した喜びや感謝の気持ちは、品物の有無や金額で決まるものではありません。受験の結果に関わらず、これまで親身になって指導してくれた先生方への感謝を、お子さま自身の口から伝えることが何よりのプレゼントになります。
経済的な負担を感じてまで高価な品を用意したり、「渡さなければ」と義務感に駆られたりする必要はまったくないのです。
塾のお礼の品を選ぶ4つのポイント
塾へのお礼の品を選ぶ際は、相手に負担をかけず喜んでもらうためのコツがあります。 高価すぎたり、扱いに困るものを選んだりすると、かえって迷惑になる可能性もあるため注意が必要です。
以下4つのポイントを解説します。
ひとつずつ見ていきましょう。
選び方①塾全体(教室)宛てか先生個人宛てか
塾のお礼の品を選ぶポイントの1つ目は、塾全体(教室)宛てにするか、お世話になった先生個人宛てにするかを決めることです。
どちらを選ぶかによって、適切な品物や予算が変わってきます。たとえば、集団塾や複数の先生にお世話になった場合は、教室のスタッフ全員に行きわたるよう「塾全体」宛てがおすすめです。
一方、個別指導塾や特定の先生にていねいに見てもらった場合は、「先生個人」宛てに別途用意すると喜ばれます。 まずは、感謝を伝えたい範囲を明確にしましょう。
選び方②金額相場は2,000円から5,000円程度
塾のお礼の品を選ぶポイントとして、金額相場は2,000円から5,000円程度を目安にすることが挙げられます。これは、塾の先生に気を遣わせないための配慮です。
10,000円を超えるような高額な品物は、かえって相手に心理的な負担を与えてしまう可能性があります。一般的な目安としては、以下のとおりです。
| 宛先 | 金額相場の目安 |
|---|---|
| 塾全体(教室)宛て | 3,000円~5,000円程度 |
| 先生個人宛て | 2,000円~3,000円程度 |
感謝の気持ちを伝えることが目的なので、金額の高さよりも心のこもった品選びを優先しましょう。
選び方③日持ち・個包装など分けやすさを重視
塾のお礼の品を選ぶ3つ目のポイントは、日持ちがして、個包装になっているなど「分けやすさ」を重視することです。
とくに教室全体宛てに贈るお菓子などは、この配慮が欠かせません。塾の先生方は忙しく、すぐに食べられないことも多いため、賞味期限が短いものや、切り分ける必要があるホールケーキなどは避けるのがマナーです。
その点、個包装の焼き菓子や飲み物なら、好きなタイミングで手に取ってもらえ、スタッフ間でも簡単に分けられます。



個包装のお菓子は講師室で分けやすく、とても助かりますよ。
選び方④近所のお店の商品はかぶる可能性も
塾のお礼の品を選ぶポイントの4つ目として、塾の近所のお店の商品は、他の方とかぶる可能性がある点も考慮しましょう。
合格や卒業のシーズンには、同じように考える保護者の方からお礼の品が集中することがあります。塾の最寄り駅にある有名なお菓子屋さんの品物を選ぶと、「また同じものだ」と思われてしまうかもしれません。
もちろん気持ちがうれしいことに変わりはありませんが、少し配慮するなら、デパートや専門店、オンラインのお取り寄せなどを利用するのがおすすめです。
塾のお礼におすすめの品【塾全体・先生個人】
塾のお礼に何を選べばいいか迷う人のために、塾全体(教室)宛てと先生個人宛てに分けて、おすすめの品を紹介します。
相手に負担をかけず、喜んでもらえる品物選びの参考にしてください。
- 【塾全体】個包装の焼き菓子・お菓子
- 【塾全体】コーヒー・紅茶のギフトセット
- 【塾全体】ジュースの詰め合わせ
- 【先生個人】文房具やハンカチ
- 【先生個人】大学生講師には図書カードやスタバカードも
- 【先生個人】お菓子のカタログギフト
- 【最強のプレゼント】生徒本人からの感謝の手紙
詳しく解説します。
【塾全体】個包装の焼き菓子・お菓子
塾全体へのお礼におすすめの品の定番は、個包装の焼き菓子やお菓子です。講師や事務スタッフなど多くの人がいる教室では、全員で分けやすいことが最も喜ばれます。
理由は以下のとおりです。
- 日持ちがする(賞味期限が短い生菓子は避ける)
- 常温で保存できる
- 個包装になっていて分けやすい
クッキーやフィナンシェ、せんべいなど、授業の合間や休憩中に手軽につまめるものを選ぶと、忙しい先生方にも負担をかけません。
【塾全体】コーヒー・紅茶のギフトセット
塾全体へのお礼におすすめの品として、コーヒーや紅茶のギフトセットも挙げられます。職員室での休憩中に飲んでもらえるため、実用的で喜ばれる品物のひとつです。
お菓子と一緒に贈るのもいいでしょう。スティックコーヒーやティーバッグの詰め合わせなら、手軽に淹れられ、個包装のお菓子と同様に分けやすいメリットもあります。
カフェインが苦手な先生がいる可能性も考慮し、デカフェ(カフェインレス)の詰め合わせを選ぶのも配慮が行き届いています。
【塾全体】ジュースの詰め合わせ
塾全体へのお礼の品には、ジュースの詰め合わせもおすすめです。コーヒーや紅茶を飲まない先生もいるため、どなたにも喜ばれる選択肢となります。
とくに、果汁100%のジュースや、少し高級感のある瓶入りのジュースセットは、特別感があり喜ばれます。冷蔵庫で冷やしておけば、授業後の疲れを癒やすひとときにも役立ちます。
お菓子と同様に、常温で保存できるものが持ち運びや保管の負担にならず安心です。
【先生個人】文房具やハンカチ
塾の先生個人へのお礼におすすめの品として、文房具やハンカチが挙げられます。お菓子などの食べ物とは別に、形に残るものを贈りたい場合に適しています。
講師は授業でペンを使ったり、板書を消した手や汗を拭いたりする機会が多いため、実用性が高いです。たとえば、質のいいボールペンや、ブランドのハンカチなどは、高額すぎず相手に気を遣わせません。
男性講師か女性講師かにあわせてデザインを選びましょう。
【先生個人】大学生講師には図書カードやスタバカードも
塾の先生個人へのお礼として、大学生講師には図書カードやスターバックスカードもおすすめです。お世話になった先生が大学生アルバイトの場合、現金や高額な商品券はかえって困らせてしまいますが、少額のプリペイドカードは実用的で喜ばれる傾向にあります。
大学の勉強に必要な参考書を買ったり、カフェで休憩したりするのに役立ちます。2,000円~3,000円程度を目安に、感謝の手紙と一緒に渡すとスマートです。



大学生の先生には、何が喜ばれますか?



実用的なカード類は、勉強や休憩に使えるので喜ばれますよ。
【先生個人】お菓子のカタログギフト
塾の先生個人の好みがあまりわからない場合、お菓子のカタログギフトもおすすめのお礼の品です。食べ物の好みがわからず何を選べばいいか迷ったときに、とても便利な選択肢です。
主なメリットは以下のとおりです。
- 相手の好みがわからなくても、好きなものを選んでもらえる
- カードタイプならかさばらず、持ち帰りの負担にならない
- 予算(3,000円程度)にあわせて選べる
「ご迷惑でなければ、お好きなものを選んでください」と一言添えて渡せます。甘いものが好きかどうかわからない場合は、グルメ全般のカタログギフトを選ぶといいでしょう。
【最強のプレゼント】生徒本人からの感謝の手紙
塾のお礼として、品物以上に喜ばれる最強のプレゼントは、生徒本人からの感謝の手紙です。講師にとって、生徒の合格と成長が何よりの報酬です。
「先生のおかげで苦手だった算数が得意になりました」「励ましてくれてありがとう」といった、お子さま自身の言葉で書かれたメッセージは、講師の疲れを吹き飛ばすほどの喜びがあります。
お礼の品を渡す場合も、ぜひお子さまからの手紙を添えてください。これまでの苦労が報われる、最高の贈り物になります。



やはり生徒さん本人からの手紙が、私たちにとって一番の宝物です。
塾のお礼で避けるべき・注意が必要な品
感謝の気持ちを伝える塾のお礼ですが、品物によってはかえって相手を困らせてしまうケースがあります。ここでは、塾のお礼として避けるべき・注意が必要な品を4つ解説します。
ひとつずつ解説します。
現金・高額な商品券
塾へのお礼で避けるべき品の代表例は、現金や高額な商品券です。多くの塾では、講師が保護者から金品を受け取ることを規則で禁止しています。
生々しい印象を与えてしまい、受け取った講師も「受け取ってしまった」と心理的な負担を感じたり、規則違反として処分されたりする可能性があります。
図書カードなどであっても10,000円を超えるような高額なものは避け、あくまで感謝の気持ちとして負担にならない範囲に留めるのがマナーです。



気持ちは嬉しいですが、現金や高額な品は規則で受け取れないんです。
お酒類
塾へのお礼として、お酒類も避けるべき品に挙げられます。講師陣のなかに、お酒が飲めない人や苦手な人がいる可能性は十分に考えられます。
また、塾はあくまでも子供たちの教育の場であり、お酒を持ち込むこと自体がふさわしくないと判断される場合もあります。
個人の好みがはっきりとわかっていない限り、お酒類は選ばないのが無難です。
手作りの食べ物
塾へのお礼で注意が必要な品として、手作りの食べ物(お菓子や料理)が挙げられます。感謝の気持ちを込めた手作り品は、衛生面やアレルギーの観点から、塾側が受け取りをためらうケースが少なくありません。
とくに大勢のスタッフがいる教室では、万が一の事態を考慮し、市販されていない食べ物は受け取らない方針を決めていることもあります。
気持ちはありがたいものの、相手を困らせてしまう可能性があるため、避けるのが賢明です。
大きすぎる・重すぎるもの
塾へのお礼で避けるべき品には、大きすぎるものや重すぎるものも含まれます。たとえば、大きな花束や、重い飲み物の詰め合わせ(瓶ジュースのケースなど)は、受け取った後の持ち帰りや置き場所に困らせてしまいます。
講師は授業後に他の業務があるかもしれませんし、電車通勤の可能性もあります。お礼の品は、相手が気軽に受け取れ、持ち帰りやすいサイズ感を意識して選ぶ配慮が求められます。
塾のお礼を渡すタイミングとマナー
お世話になった塾へのお礼は、タイミングや渡し方のマナーも大切です。先生方は日々の授業や面談で忙しいため、迷惑にならないよう配慮して感謝の気持ちを伝えましょう。
- いつ渡す?|第一志望の合格発表後が基本
- 塾に行く最後の日(卒業日)がベスト
- 訪問時間は授業が始まる前の夕方まで
- 誰に渡す?|教室長かお世話になった先生へ
- 親と子供どちらが行くべき?
- 事前に電話連絡すると確実
ひとつずつ解説します。
いつ渡す?|第一志望の合格発表後が基本
塾へのお礼を渡すタイミングは、第一志望校の合格発表後が基本です。すべての受験結果が出そろい、進学先が確定した後に、お世話になった報告とあわせてお礼を伝えます。
受験期間の途中や発表前に渡してしまうと、塾側もかえって気を遣ってしまいます。また、万が一残念な結果になった場合、お互いに気まずい雰囲気になりかねません。
すべての受験日程が終了し、親子ともに落ち着いた段階であらためて感謝を伝えるのが、最もスムーズなタイミングです。
塾に行く最後の日(卒業日)がベスト
塾へのお礼を渡すタイミングとして、塾に行く最後の日(卒業日)がベストです。合格報告や退塾の手続きなどで、お子さまや保護者の方が塾を訪問する最後の機会が、お礼を渡すのに最も適しています。
最後のあいさつとあわせてお礼を伝えることで、感謝の気持ちがより一層伝わります。卒業後、あらためてお礼のためだけに訪問するのもていねいですが、先生方の忙しさを考えると、何かの用事とあわせるほうが相手の負担になりません。
訪問時間は授業が始まる前の夕方まで
塾へのお礼を渡すための訪問時間は、授業が本格的に始まる前の夕方までがマナーです。多くの塾では、夕方以降は授業や生徒対応で非常に慌ただしくなります。
先生方が比較的落ち着いている時間帯を狙うのが配慮です。
| 訪問タイミング | 具体例 |
|---|---|
| おすすめの時間帯 | 平日の授業が始まる前(例:16時~17時頃)、土曜日など比較的ゆとりのある日中 |
| 避けるべき時間帯 | 授業の真っ最中、授業間の短い休憩時間、生徒が入れ替わるピーク時 |
この時間帯であれば、先生も手を止めて、ゆっくりと合格の報告や感謝の言葉を受け取りやすくなります。



先生が忙しくない時間って、いつごろですか?



授業が始まる前の夕方までなら、比較的ゆっくりお話できますよ。
誰に渡す?|教室長かお世話になった先生へ
塾へのお礼を渡す相手は、まずは教室長(塾長)か、受験でお世話になった担当の先生へ手渡すのが基本です。教室全体宛てのお礼であれば、教室の責任者である教室長に「皆様で召し上がってください」と一言添えて渡すのが最もスムーズです。
個別指導などで特定の先生に特にお世話になった場合は、その先生に直接渡しても構いません。ただし、その先生が授業中の場合もあるため、近くにいる別の先生や受付のスタッフに「〇〇先生に(皆様に)お渡しください」と預ける形でも失礼にはあたりません。
親と子供どちらが行くべき?
塾へのお礼を渡しに行く際は、可能であれば親と子供が一緒に行くのがベストです。合格の報告と感謝の気持ちを、親子そろって伝えることが最もていねいな形となります。
お子さま自身の口から感謝を伝えることは、先生にとって何よりもうれしいものです。また、保護者の方からも直接お礼を述べることで、これまでのサポートに対する謝意が深く伝わります。
もし都合がつかない場合は、お子さまだけでも問題ありません。その際は、保護者からのお礼の手紙を添えると、より気持ちが伝わります。
事前に電話連絡すると確実
塾へのお礼を渡しに訪問する際は、事前に電話連絡を一本入れておくと確実です。塾は授業以外にも面談や会議などで、教室長や担当の先生が不在にしている場合があります。
せっかく訪問しても、感謝を伝えたい相手が不在では二度手間になってしまいます。「〇〇(子供の名前)の母ですが、明日の〇時頃、合格のご報告とお礼に伺わせていただきたいのですが、教室長(〇〇先生)はいらっしゃいますか?」と簡潔に伝えておきましょう。
アポイントを取っておくことで、先生側も数分時間を作って待機してくれるため、慌ただしくならずに済みます。



訪問前に電話をもらえると、先生も時間を作りやすいので確実です。
塾のお礼に添えるのし・手紙の書き方
塾へのお礼の品を渡す際、のし(熨斗)や手紙を添えることで、よりていねいに感謝の気持ちを伝えられます。ここでは、のしの必要性や書き方のマナー、保護者とお子さまそれぞれの手紙の例文を紹介します。
ひとつずつ見ていきましょう。
のしは必要?|基本はなくても失礼にあたらない
塾へのお礼の品に、のし(熨斗)は基本的にはなくても失礼にあたりません。デパートなどで購入した際のフォーマルな包装や、リボンがけのラッピングでも十分感謝の気持ちは伝わります。
とくに卒業シーズンは多くの家庭からお礼が届くため、堅苦しくない形のほうがかえって塾側も受け取りやすい場合があります。
ただし、教室全体に宛てて渡す場合や、中学受験などで特にていねいな形で感謝を伝えたい場合は、のしを付けると「お礼の品である」ことが明確に伝わり、よりフォーマルな印象になります。
のしを付ける場合の書き方|紅白蝶結び・表書きは「御礼」
塾へのお礼でのしを付ける場合の書き方として、水引は「紅白の蝶結び」を選び、表書きは「御礼」とするのが一般的です。
合格は何度あっても喜ばしいことのため、何度も結び直せる「蝶結び」の水引を使います。表書きや名前の書き方は、以下のとおりです。
| 項目 | 書き方 | 意味・ポイント |
|---|---|---|
| 水引 | 紅白の蝶結び | 合格や卒業など、何度あってもいいお祝い事に使います。 |
| 表書き | 御礼 | 最も一般的で、感謝を伝えるのに適しています。 |
| 名前 | お子さまの氏名(フルネーム) | 塾に通っていた本人の名前を書くのが基本です。 |
名前は、表書きの真下に、少し小さめに記載しましょう。



もし「のし」を付けるなら、「御礼」と書くのが一般的ですね。
保護者から塾の先生への手紙の例文
塾へのお礼に添える保護者から先生への手紙は、指導への感謝と子供の成長を具体的に伝えるのがポイントです。長く堅苦しい文章である必要はなく、メッセージカードなどに簡潔にまとめるだけでも心が伝わります。
【例文】〇〇塾 先生方(または 〇〇先生)
このたび、長男〇〇(子供の名前)が〇〇中学校に無事合格することができました。先生方の熱心なご指導のおかげと、親子ともども心より感謝しております。入塾当初は苦手意識の強かった算数も、先生の励ましのおかげで最後には得意科目と言えるまでになりました。
つきましては、心ばかりの品をお送りいたします。皆様で召し上がっていただければ幸いです。
末筆ながら、先生方のますますのご活躍と、〇〇塾の発展をお祈り申し上げます。
本当にありがとうございました。
令和〇年〇月〇日 (保護者氏名) (生徒氏名)
子供から塾の先生への手紙の例文
塾へのお礼として、品物以上に講師がうれしいのが、子供本人からの感謝の手紙です。上手な文章である必要はなく、お子さま自身の素直な言葉で書かれていることが何よりも喜ばれます。
【例文】〇〇先生へ
ぼく(わたし)は、〇〇中学校に合格することができました。〇〇先生が、いつもやさしく(きびしく)教えてくれたおかげです。とくに苦手だった理科の計算も、先生のおかげで解けるようになってうれしかったです。先生の授業はとても楽しかったです。
中学校に行っても、先生に教わったことを忘れずに勉強をがんばります。今まで、本当にありがとうございました。
令和〇年〇月〇日 (生徒氏名)
お礼状の封筒の宛名の書き方
塾のお礼状を封筒で渡す場合、宛名は塾(教室)の責任者か、お世話になった先生個人宛てに書きます。渡し方によって、以下のように使い分けましょう。
| 宛先 | 表面(宛名)の書き方 |
|---|---|
| 塾全体・教室長宛て | 〇〇塾 教室長 〇〇様 (または「〇〇塾 先生方」) |
| 特定の先生宛て | 〇〇塾 〇〇先生 (「様」でも間違いではありませんが「先生」が自然です) |
裏面には、差出人として保護者の住所・氏名と、お子さまの氏名を併記しておくと、誰からのお礼かすぐにわかりていねいです。
【ケース別】塾のお礼で知っておくべきポイント
塾へのお礼は、合格したときだけでなく、さまざまなケースで悩むことがあります。志望校に不合格だった場合や、補習塾を辞める際など、状況別のお礼のポイントを解説します。
- 志望校への受験が不合格だった場合も塾にお礼は伝えるべき?
- 受験ではなく補習塾を辞める時のお礼は必要?
- 個別指導塾と集団塾でお礼は違う?
- 中学受験・高校受験・大学受験でのお礼の違い
- お礼の品を断られた時の対処法
ひとつずつ解説します。
志望校への受験が不合格だった場合も塾にお礼は伝えるべき?
塾へのお礼で知っておくべきポイントとして、志望校への受験が不合格だった場合でも、感謝の気持ちは伝えるべきです。
結果がどうであれ、先生方がお子さまの受験を親身にサポートしてくれた事実に変わりはありません。「残念ながらご縁がありませんでしたが、これまで熱心にご指導いただきありがとうございました」と、結果報告とあわせてお礼を伝えるのがマナーです。
この場合、お菓子などの品物を渡すことに抵抗があれば、無理に用意する必要はありません。親子で直接あいさつに伺うか、ていねいな手紙や電話で感謝を伝えるだけでも十分です。



もし不合格だったら…お礼は言いにくいです…。



結果に関わらず、頑張った報告と感謝の言葉は伝えるといいと思いますよ。
受験ではなく補習塾を辞める時のお礼は必要?
塾へのお礼で知っておくべきポイントとして、受験目的ではなく、学校の補習などで通っていた塾を辞める時のお礼は、必須ではありません。
ただし、長期間お世話になった場合や、先生にていねいに指導してもらい成績が上がった実感がある場合は、感謝の気持ちを伝えるのがおすすめです。
受験の合格お礼ほどのフォーマルさは必要ないため、最終日に「これまでありがとうございました」と、お子さまから個包装のお菓子やハンカチなどを手渡す程度でも喜ばれます。
個別指導塾と集団塾でお礼は違う?
塾のお礼で知っておくべきポイントに、個別指導塾と集団塾での違いがあります。関わり方の深さが異なるため、お礼の仕方も少し変わる傾向があります。
| 塾の種類 | お礼の傾向 |
|---|---|
| 集団塾 | 教室長や事務スタッフを含めた「塾全体(教室)宛て」に、全員で分けられるお菓子などを贈るのが一般的です。 |
| 個別指導塾 | 塾全体宛てのお礼に加え、とくに長く担当してもらった特定の先生個人宛てに、手紙や2,000円程度の品物(文房具やカード類)を別途用意するケースも多く見られます。 |
中学受験・高校受験・大学受験でのお礼の違い
塾へのお礼で知っておくべきポイントとして、中学受験・高校受験・大学受験での違いも挙げられます。最もていねいなお礼(品物や手紙)が行われる傾向にあるのは、親子と塾の関わりが最も密接で、長期間にわたる中学受験です。
高校受験、大学受験と進むにつれて、生徒本人の主体性が増すため、お礼の習慣は比較的簡潔になる傾向があります。大学受験では、お子さま本人が合格報告に行き、あいさつだけ済ませるケースも少なくありません。
お礼の品を断られた時の対処法
塾へのお礼で知っておくべきポイントの最後は、お礼の品を断られた時の対処法です。塾の規則で金品の受け取りを厳しく禁止している場合、せっかく用意した品物も辞退されることがあります。
その際は、無理に渡そうとせず、相手の方針を尊重して潔く引き下がりましょう。「規則で決まっておりますので」と断られたら、「承知いたしました。皆様には本当にお世話になりました」と、あらためて感謝の言葉を伝えるだけで十分です。
手紙であれば受け取ってもらえる場合が多いため、品物の代わりに手紙だけ渡すのもひとつの方法です。



塾の規則で受け取れない場合も。その時は言葉だけで十分ですよ。
塾へのお礼に関するよくある質問(FAQ)
塾へのお礼に関するよくある質問と回答をまとめました。感謝の気持ちを伝える際の疑問や不安を解消しましょう。
塾の先生がもらって嬉しいプレゼントは?
塾の先生がもらって嬉しいプレゼントは、何よりも生徒本人からの感謝の手紙です。講師にとって、生徒の合格や成長が一番の喜びであり、心のこもったメッセージは大きな励みになります。
品物であれば、日持ちする個包装のお菓子やコーヒー・紅茶のセットなど、職員室で分けやすい実用的なものが喜ばれます。
高額なものや好みが分かれるものは避け、相手に気を遣わせない配慮が大切です。
塾の先生へのお礼はメールでもいい?例文は?
塾の先生へのお礼は、直接または電話で伝えるのが最もていねいですが、メールで送っても失礼にはあたりません。
とくに、訪問する時間が取れない場合や、塾の規則で品物を受け取らない方針が明確な場合は、メールで感謝を伝えるのもひとつの方法です。
合格の報告とあわせて、具体的なエピソードを交えながら感謝の気持ちを綴りましょう。
【メール例文】件名:〇〇(生徒名)の母より(合格のご報告)
〇〇塾 〇〇先生
ご無沙汰しております。〇〇(生徒名)の母です。このたび、〇〇(生徒名)が無事に〇〇学校に合格することができました。これもひとえに、〇〇先生をはじめ先生方の熱心なご指導のおかげと、心より感謝しております。
(ここに具体的なエピソードや感謝の言葉を簡潔に記載)
本来であれば直接お礼を申し上げるべきところ、メールでのご連絡となり失礼いたします。先生方のますますのご活躍をお祈りしております。本当にありがとうございました。
塾へのお礼で商品券やクオカードは迷惑になる?
塾へのお礼として、商品券やクオカードは迷惑になる可能性があるため、避けるのが無難です。現金と同様に、金券類は多くの塾で受け取りを規則で禁止している場合があります。
受け取った講師が規則違反になったり、心理的な負担を感じたりするリスクがあります。大学生講師へのお礼として図書カードやカフェのカードを贈るケースもありますが、その場合も2,000円~3,000円程度の少額にし、高額なものは避け、相手に気を遣わせない配慮が求められます。
まとめ
塾の先生へのお礼は必須ではありませんが、合格の報告とともに、これまでのサポートに対する感謝の気持ちを伝えることが何よりも大切です。
もし品物を贈る場合は、以下のポイントを参考に、先生方に負担をかけず喜んでもらえるものを選びましょう。
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 金額相場 | 2,000円~5,000円程度(塾全体宛ては3,000円~5,000円、個人宛ては2,000円~3,000円) |
| 選び方 | 日持ちがし、個包装で分けやすいお菓子やコーヒーなどが定番 |
| 避けるべき品 | 現金・高額な商品券、手作りの食べ物、大きすぎるもの |
| タイミング | 第一志望の合格発表後、塾に行く最後の日(卒業日)がベスト |
| 注意点 | 塾によっては規則でお礼の品を禁止・辞退している場合もある |
品物以上に喜ばれるのは、生徒本人からの心のこもった手紙です。この記事で紹介したマナーや例文も参考にして、お世話になった先生方へ、ぜひ親子の言葉で感謝の気持ちを伝えてみてください。




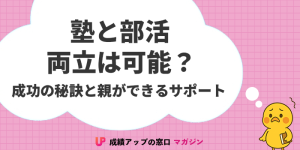
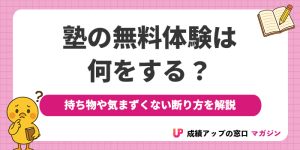


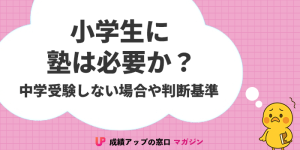


コメント